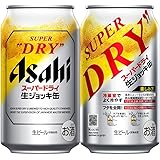「中流幻想」ははるか彼方の過去の夢。
1980年前後に始まった日本社会の格差拡大は、もはや後戻りができないまでに固定化され、いまや「新しい階級社会」が成立した。
講談社現代新書の新刊・橋本健二『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』では、2022年の新たな調査を元に「日本の現実」を提示している。
本記事では、〈日本で起きている「未婚化と少子化を促進する悪循環」…「アンダークラスの出現」が日本社会にもたらすもの〉に引き続き、五つの階級における、それぞれの生い立ちと日常について詳しく見ていく。
※本記事は橋本健二『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』より抜粋・編集したものです。

両親の学歴と出身階級
『新しい階級社会』第一章では、五つの階級の間のさまざまな格差や違いについて概観した。本章ではさらに幅を広げ、それぞれの階級に属する人々が、どのような家庭で生まれ育ち、どのような経歴を経て現在の階級にたどり着いたのか、そして現在、どのような日常を送っているのかについてみていくことにしたい。
人は自分の親を選べない。したがって、生まれ育つ家庭環境を選ぶことができない。ところが自分の親がどのような人物であるか、生まれ育つ家庭環境がどのようなものであるかは、その人の人生を大きく規定する。これは人生における最大の、根源的な不条理である。いつごろからか主に若者たちの間で使われるようになった「親ガチャ」という言葉は、古くから知られるこの不条理に対して与えられた、新しい名称である。

図表3・1は、所属階級別に、両親の学歴と父親の所属階級をみたものである。両親の学歴は、父親と母親の学歴を組み合わせて「両親とも大卒」「両親の一方が大卒」「両親とも非大卒」の三つに分類した。両親とも大卒の比率がもっとも高いのは、予想されるとおり新中間階級で、36.3%に上っている。両親の一方が大卒という人も23.8%おり、合計すれば約6割の人の親が大学を出ていることになる。これに対してアンダークラスでは、両親とも大卒という人が25.2%しかおらず、両親とも非大卒の比率が53.4%と過半数に達している。
両親の一方が大卒との合計では資本家階級と正規労働者階級の両親の学歴は、新中間階級とアンダークラスの中間で、資本家階級の両親の方がやや高い。旧中間階級はアンダークラスとほぼ同じだが、これは旧中間階級に年齢の高い人が多いことによる部分が大きい。年齢を59歳以下に揃えれば、両親とも大学を出ている旧中間階級の比率は29.3%で、アンダークラスより高くなる。
父親の所属階級は本人の育った家庭環境を大きく左右するので、出身階級と呼ばれることが多い。これをみると、まず目をひくのは資本家階級の父親の所属階級で、資本家階級の比率が29.0%と非常に高くなっていることだろう。回答者の父親が働いていた時期は、中小零細企業が非常に多かった高度経済成長期を含むので、すべての階級で10%を超えるのだが、その2倍を大きく上回っている。
これはもちろん、中小零細企業経営者が、その子どもにあとを継がせるケースが多いからである。旧中間階級の父親の所属階級で、旧中間階級が31.4%と多くなっているのも、同じ理由からである。
被雇用者の三つの階級を比較すると、新中間階級では父親も新中間階級であるケースが多いのに対して、正規労働者階級とアンダークラスでは父親も労働者階級であるケースが多い。正規労働者階級とアンダークラスには、大きな違いがない。
両親の学歴の違いと父親の所属階級の違い
こうした両親の学歴の違いと、父親の所属階級の違いは、その子どもたちに学歴の違いを生んだ。そのようすをみたのが図表3・2である。いちばん進学率が高いのは、新中間階級出身者で、両親とも大卒の場合の進学率は85.5%にも達している。

図には示さなかったが、これ以外に短大・高専・専門学校など短期高等教育を受けた人が10.9%いるので、高卒後の進学率はほぼ100%に近い。両親の一方が大卒の場合は74.4%、両親とも非大卒の場合でも62.1%が大学に進学している。二番目に進学率が高いのは資本家階級出身者で、とくに両親とも大卒の場合の進学率は81.1%と8割を超えている。
これに対してもっとも大学進学率が低いのは、旧中間階級出身者である。両親とも大卒の場合でも進学率は70.3%、両親とも非大卒だと43.1%にとどまっている。労働者階級出身者の進学率は旧中間階級出身者よりは高いが、両親とも非大卒の場合は44.9%で、旧中間階級出身者と大差がない。
このように両親の学歴の違いと父親の所属階級の違いは、子どもたちの大学進学を左右し、結果的に子どもたちの所属階級の違いを生み出す。概していえば、新中間階級の子どもたちは大学を出て新中間階級になり、労働者階級の子どもたちは労働者階級(正規労働者階級またはアンダークラス)になりやすい。
資本家階級の子どもたちは大学進学率が高く、旧中間階級の子どもたちは大学進学率が低い。しかしこの二つの階級の子どもたちには、大学に進学してもしなくても、親のあとを継いで親と同じ階級に所属できる可能性がある。
*
さらに【つづき】〈「格差拡大」により日本に出現した「新しい下層階級」…現代日本の「階級社会」のしくみ〉では、「新しい階級社会」とはどのような社会なのか、詳しく見ていく。

橋本 健二
1959年、石川県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。現在、早稲田大学人間科学学術院教授(社会学)。データを駆使して日本社会の階級構造を浮き彫りにする。また、趣味と研究を兼ねて「居酒屋考現学」を提唱。著書『階級社会』(講談社選書メチエ)、『新・日本の階級社会』(講談社現代新書)ほか