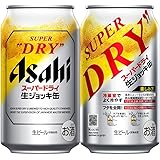人気エリアでおこなわれた調査
いま、マンション業界で「ある調査」の結果がひそかに話題になっている。
それは、練馬区による、区内の分譲マンションについての調査である(=「練馬区分譲マンション実態調査(令和6年度)」)。
調査は昨年6〜9月に実施され、今年5月にその結果が発表された。
「今回の調査は専門紙でも言及されるなど、業界内での注目度はそうとうに高いと考えられます。
調査では、そうした言葉遣いはしていませんが、『限界マンション』が思ったよりも身近な存在になりつつあるという厳しい現実が示されています」(全国紙経済部記者)
練馬区といえば、東京23区内にしてはマンション価格が比較的リーズナブルで、「穴場」と言われることも多い。そんな人気エリアで、どんな実態が明らかになったのか。

「高経年マンション」への注目
前出の記者がつづける。
「今回の調査がとくに熱心に調べているのが、建設から40年以上経過している『高経年マンション』についてです。かんたんに言えば、建ってからかなりの時間が経った、古いマンションのこと。
練馬区内では、この『高経年マンション』の割合が、じつに11.1%に達することが明らかになったんです。11%と聞くと『少ない』と思う方もいるかもしれませんが、練馬区のマンションは全体で約5万6500戸。かなり大雑把な推計になりますが、単純に計算すると、6000戸以上が築40年を超えている。
さらに、大規模修繕の必要が差し迫っているなど、管理維持上の課題を抱える可能性が高いと考えられる『築30年以上のマンション』が26%にのぼることも示されています」
「限界マンション」の問題点
高経年マンションは一般に、さまざまな問題やリスクを抱えやすい。
たとえば、区分所有者(≒住民)の高齢化が進むなかで空き住戸が増加し、修繕積立金がたまりにくくなる。
修繕積立金が不十分な状態でマンションが老朽化していけば、マンションの躯体がボロボロになっても、おカネがないので修繕をすることはできない。

また、そうした問題を解決しようとしても、高齢化が進んだり、賃貸化が進んだりするなかで、マンション管理組合の担い手が少なくなっているので、対策を打つのが難しい。
巨大な問題を抱えながら、抜き差しならない状態になってしまうのだ。
「建物がボロボロになっているにもかかわらず、どうにも対応しようがない。そんな状態を迎えたマンションは『限界マンション』と呼ばれることがあります。
今回の調査は、『限界マンション』が、23区内の人気エリアのなかにあっても、意外にも身近なものになりつつあることを示したといえるのではないでしょうか」(同前)
実際、調査レポートにはこんな生々しい数字が並んでいる。
「空き家化」物件は22.2%
前出の記者がつづける。
「たとえば今回の調査では、マンションの5%以上が空き家になることを『空き家化』としていますが、高経年マンションの22.2%で『空き家化』が見られるとしています。
さらに、高経年マンションの41.1%で、管理費などを滞納する組合員が見られるとのこと。そのうち半数にあたる22.2%は、督促をしても徴収できないということです。修繕積立金の積み立てが難しいマンションが、これほどの規模に達しているのです。
ほかにも、こんな指摘があります。マンションには、計画期間30年以上の長期修繕計画を作成しているところが多いですが、高経年マンションでは、28.9%が長期修繕計画を作成していないということです」

すごいスピードで進む「高経年化」
もう一つ、こうした「現状の問題」にかぎらず、「未来の問題」への懸念も募る。
「報告書の16ページには、令和5年度の高経年マンションの数を1とした場合に、令和15年、令和25年にそれぞれ高経年マンションはどれくらいの量になっているかが示されています」
「東京都区部全体でも、令和15年には1.86倍、令和25年には2.88倍と、相当なスピードで『高経年マンション化』が進んでいることがわかりますが、練馬区では、それぞれ2.35倍、4.34倍と、区部全体を大きく上回る勢いで『高経年マンション化』が進むことが見込まれています」
「限界マンション化」を避けるために、なにができるか。住民、行政、企業の緊密な協力が求められている。
*
さらに【つづき】「千葉の大型マンション「大規模修繕」で「まさかのトラブル」が発生…住民どうしが「正面衝突」した「意外な理由」」の記事では、巧妙化する修繕積立金を狙う業者について記している。