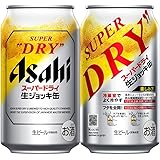『群像』は2025年5月号から、デジタル印刷で刷られることになりました。オフセット印刷からデジタル印刷に切り替わる「DX」によって、『群像』はどう変化していくのか? デジタル印刷の台頭によって、出版の未来はどうなるのか? ライターの宮田文久さんが、オフセット印刷とデジタル印刷双方の現場を取材し思考したルポルタージュ記事を、『群像』2025年7月号よりお届けします(Web記事化にあたり、一部表記を改めています)。

デジタル印刷という未知の領域
雑誌や本の未来なんて、誰も知らない。そのことは、ときに私たちを不安にさせ、ときに期待感を抱かせもする。2025年3月中旬、ある依頼を『群像』編集部から受け取った筆者も、不思議な気持ちになったのだった。
メールには、『群像』を刷ってきたオフセット輪転印刷機が役目を終えるとTOPPANから編集部に通達があった、と書かれていた。それを受けてオフセット印刷は4月号が最後、4月7日発売の5月号からは講談社の関連会社・株式会社KPSプロダクツが保有する「DSR(デジタル・ショート・ラン)」なるデジタル印刷・製本工程で本文ページを手がけることになる。ついては、デジタル/オフセット印刷双方の関係者に話を聞き、「印刷方法が切り替わることで何が変わるのか」考えるルポルタージュを掲載したい、という。
活版印刷で同誌が刷られるのが最後となった2009年12月号では、特集「活版印刷の記憶」が組まれた。既にオフセット印刷が主流の時代にあって、『群像』は商業文芸誌のなかで最後まで活版印刷にこだわっていたが、機械の老朽化とメーカーの製造終了という事情を前に、当時も決断を迫られ、翌2010年1月号からオフセット印刷に切り替えたのだ。以降、オフセット印刷と共に歩んできた歴史が一区切りを迎えるにあたり、改めて印刷や雑誌・本の来し方行く末を考えてみたいというのが、今回の企画趣旨であるようだった。
筆者が不思議な気持ちになったのは、「もう」デジタル印刷なのかという驚きと、「まだ」デジタル印刷ではなかったのだという思いが、同時に胸のうちに湧き上がったがゆえだ。
「もう」の理屈は、シンプルだ。まだ雑誌や書籍のほとんどがオフセット印刷で刷られているなか――その環境に変化が訪れつつあることは薄々察知しながらも――たとえばこの『群像』がデジタル印刷される可能性が頭に浮かばずにいたがゆえの驚きだった。
徐々に広がりつつあるデジタル印刷という営み自体、ほぼ未知の領域だった。それは筆者はもちろんのこと、これからデジタル印刷に踏み切る『群像』編集部も同様だったようで、だからこそ現場を見て、関係者の話を聞きながら考えていこうとしているのだった。
一方のオフセット印刷にしても、どれだけのことを知っているだろうか。もちろん、次のような教科書的記述は、幾度も目にしてきた。
オフセット印刷は、版面から一度インキを離して(off)、柔軟なゴムブランケットの表面に転写し、それから紙面に印刷する(set)間接印刷方式です。(…)刷版から一度ゴムのローラーに刷り、それをまた紙に刷る(…)。この刷版はPS版と呼ばれる、親水性を持たせたアルミ板に感光剤を塗ったものです。これにフィルムを密着させ、光を当てて感光させます。これを現像するとインキが付く部分ができあがり、光の当たった部分はスポンジのように水を含んだ親水性のアルミ板となって、インキをはじく性質を持ちます。
(岩波書店編集部編『カラー版 本ができるまで 増補版』岩波ジュニア新書)
しかし、説明を頭でなぞってきただけで、やはり現場は知らないに等しい。そんな「理解できていないのに日常的な環境となっていた技術」が、また別種の「理解できていない新技術」へ切り替わる(少なくとも、『群像』では)。「もう」という驚きは、これらのふたつの無知のなかで湧き上がったのだったし、それがもし筆者特有の状況でないならば、このルポルタージュの意味もあるはず、と感じたのだった。
商業誌をデジタル印刷で刷るという挑戦
「まだ」デジタル印刷ではなかったのだという思いにかんしては、とある文章を目にしていたことが関係している。『季刊・本とコンピュータ』1999年春号に掲載されている、「オン・デマンド印刷がやってきた」(中西秀彦筆)という記事だ。
「速度、両面印刷、製本の機能を兼ね備えたプリンタ」であるゼロックス社の「ドキュテック」を前年に導入した、印刷会社から見た現状報告という趣。「やってきた」と表現されるほど、当時最先端のテクノロジーだった。しかし、この記事から四半世紀が過ぎた現在でも「まだ」、商業出版の場でデジタル印刷はそこまで一般的にはなっていない。そんな状況下、『群像』に「デジタル印刷がやってきた」のだ。
さて、同誌がオフセット印刷からデジタル印刷に切り替わる経緯にかんしては、本文の全ページがDSRで印刷された2025年5月号の「編集後記」で、戸井武史編集長が綴っている。
お気づきになりましたでしょうか。今号の「群像」の体裁がすこし変わったことを。折り込みの目次がありません。さらっとカラーページが存在します。などなど、細かいところはいずれ特集記事を作れたらと思うのですが、簡単にお伝えしますと、これまでTOPPANさんにあった「群像」のようなA5判を刷る輪転機が老朽化のためなくなります。「すわ廃刊か」と(本当に)焦ったのですが、KPSさんと弊社業務部の研究・実験によって、デジタル印刷機で刷ることで継続できるようになりました。今号から、表紙周りがオフセット印刷(TOPPANクロレ)、本文がデジタル印刷となります。来年創刊80周年を迎えるオールドメディアのDXです。デザイナーや印刷所のみなさんと一緒に、「紙の雑誌」の可能性を探究していければと思います。

小さな「あとがき」に経緯が圧縮されているため、現場から見ればその行間にはさまざまなニュアンスが潜んでいることを、後に私たちは取材を進めるなかで知っていったのだが、いずれにせよ事の要点は示されている。このルポルタージュが掲載されている2025年7月号はデジタル印刷に切り替えて三号目。オフセット印刷とは似て非なる誌面の様子を、読者も各々実感している頃だろう。
「オールドメディアのDX」――デジタル・トランスフォーメーションという文言も見える。これも取材の過程で明瞭になっていったことであるが、小ロットの部数に適したデジタル印刷という技術、実際に従来は少部数のフレキシブルな印刷に活用されてきたDSRで、月刊商業誌である『群像』を刷るということは、非常にチャレンジングな試みだったようなのだ。関係者たちが、DSRが想定してきた部数より遥かに多い『群像』を刷ることの技術的な課題をクリアし、その挑戦の意義を見定めている様子を、私たちは知っていくこととなった。
断っておくと、本稿で書かれる現場のリアリティや関係者の発言は、あくまでいまの出版界・印刷界の一部の例にすぎない。DSRにしてもKPSプロダクツの専売特許ではなく、各印刷会社などで試行されているし、デジタル印刷をめぐる動きは各所で目まぐるしく展開されている。たとえばこのルポ企画の進行中にも、大日本印刷が2025年5月、POD(プリント・オン・デマンド)による少部数対応を礎に、書店起点で本を復刊・販売できる「DNP復刊支援サービス」を開始、というニュースが飛び込んできた。
そうした最中にあって、『群像』のデジタル印刷は、商業誌におけるインクジェット印刷の先駆的な取り組みとなった。以降は、2025年の春から初夏にかけて断続的に行われた、印刷と出版をめぐる小さな旅の記録だ。
インクの匂いがしない印刷工場
3月31日、月曜日の午後。埼玉県ふじみ野市の郊外に位置するKBF(講談社ブックファクトリー)の前のバス停に、私たちは降り立った。メンバーは『群像』編集部と、社内の他の小説誌などの編集者たち。『群像』の面々はDSRに切り替える準備・テスト段階で一度見学に訪れたというが、この日は2025年5月号を前週に校了した直後。これから初めて『群像』がデジタル印刷されつつある様を目撃するのだ。
講談社の製造拠点であるKBFには、関連企業が集結している。そのひとつが、DSRを手がけるKPSプロダクツだ。オフセット印刷と製本ラインという従来の工程と、DSRというデジタル印刷工程が隣り合う、国内では数少ない書籍専門「オフセット・デジタル ハイブリッド工場」なのだという。
敷地内の、どうやらコミックを刷っている最中らしいオフセット印刷機の横を、インクの匂いを吸いこみながら通り抜け、KPSプロダクツの建屋へ入っていく。
インクの匂いが、すっと遠のいた。
デジタル印刷の現場に足を踏み入れたとき、最初に驚いたのはそのことだった。ここは、インクの匂いがほぼしない印刷工場なのだ。
二十五メートルの水泳プールが優に収まりそうな屋内で、その製造ラインは稼働中だった。大きさだけで言えば、まるで大蛇が、こちらに腹を見せながら逆U字の形に横たわっているよう。けれども、その比喩が含む生々しさはない。機械の騒音も多少声を張れば会話も普通にできるほどで、予想よりはずっと静か。スタイリッシュ、という言葉が浮かぶ。

製造ラインは、印刷と製本加工、ふたつの機械が一体化している。印刷はHP社製のインクジェットプリンター「HP PageWide Web Press T370 HD」、その先に製本加工を行うミューラー・マルティニ社製「シグマライン」が直結されている。
『群像』の本文用紙、リーズナブルなザラ紙「苫特クリームN」の巨大なロールが高速で送り込まれ、印刷が進む。従来の用語で言えば、予めカットされた用紙に印刷する「平台(枚葉機)」ではなく、「輪転機」然としている。
ひとつの折=十六ページであり、一折、二折……と複数の折で雑誌や書籍が構成されるのは、デジタル印刷でも同様。オフセット印刷では刷版を切り替えるために折ごとに印刷していた(まずは一折をひたすら印刷し、終われば二折以降へ移る)のに対し、刷版が存在しないDSRでは、最初のページから最後のページまでを、長いロール紙のまずは表に、次は裏に、両面印刷していく(同じ機械が二台、横並びになっている)。設定部数の分、超高速で一冊ずつ、全ページが刷られるのだ。
案内をしてくれたKPSプロダクツ印刷製造部・部長の古郡弘さんが、ロール紙の表側を印刷する機械の一部を指し示した。
「いまここで、印刷した紙にドライヤーをかけています。インクジェットは、文字通り紙にインクという水分を含ませますが、『群像』さんは用紙がザラ紙なので、水分量が重要になってきます。多すぎると紙が破けてしまうので極力落としつつ、かといってインクの濃度が落ちすぎてしまうのもよくないため、ギリギリの数値にするんです。さらにドライヤーをかけるのですが、かけすぎても破れてしまう。紙にダメージを与えないよう、これもギリギリのところを設定しています。
テンション(編注:ロール紙の張力)にも、かなり気を遣いました。これまで扱ってきた紙では設定したことがないほど数値を落としたのですが、落としすぎてしまうとインクがうまく乗らない。テストを繰り返して、ようやくいま、こうして印刷できているんです」
編集部にとってデジタル印刷が初めてならば、デジタル印刷する側も『群像』は初めて。通常、講談社文庫や講談社現代新書の増刷分などを手がけているDSRだが、『群像』の印刷がチャレンジングだったことはたしかなようだ。
刷版が存在しないので、DTPで制作されたPDFデータが、そのまま全ページ印刷されていくことになる。よほどのことが起きない限り、一度刷り始めたラインは、設定部数を刷り終えるまで止められることはない。だからこそ、今回は事前のテストに腐心した。TOPPANのDTPチームから校了データを受け取ってから、この見学の直前の週末にテスト日を設け、発行部数の一部も既に刷ったという。私たちは工程の二日目を目撃していたのだ。
デジタル印刷への転換による変化
両面に印刷が施されたロール紙が、誌面の様子が瞬間的に確認できるスピードで先に送られる。戸井編集長が思わず声を漏らす。
「この光景は、頭では理解していてもやっぱり驚くなあ」
目の前をあっという間に通り過ぎる誌面の大半はモノクロの文字ページだが、その最中に一瞬、写真やイラストがカラーになっているのがチラホラ見える。オフセット印刷にはない、異様な光景。ひとつの折全体がカラーなのではない。折のなかにモノクロページとカラーページが混在しているのだ。
C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(キー・プレート=ブラック)の4色のみですべてを表現するデジタル印刷では、自然な光景だ。オフセット印刷のように折単位でモノクロとカラーを切り替える必要もない。家庭用インクジェット・プリンターと同様、一ページのなかにモノクロとカラーが両方あっても支障はない。戸井編集長は、早くもあれこれとアイデアを練っている。
「対談ページのトビラの写真は、以前はどうしてもモノクロだったけれど、デジタル印刷だとカラーにできる。人の顔も予想以上に綺麗に出力される。書評の本の写真だけカラーにするとか、可能性も広がりそうですね」
オフセット印刷でよく用いられてきた「特色」のインクは存在せず、繰り返すがすべてをCMYKで表現するほかない。しかも理想の色味を出すのと同時に、ザラ紙と水分量の問題もクリアしなければいけない。
「『この紙にカラーだなんて……そんなご無体な』と正直、最初は思いました(笑)」と冗談めかして明かしてくれたのは、ベテランらしい飄々とした語り口のDSRエンジニア・Iさんだ。

『群像』の本文用紙「苫特クリームN」は、オフセット印刷時代から続けて使用しているもの。デジタル印刷の過程で「ボンディング・エージェント」なる定着剤をふきつけることで、インクジェット適性をもたせているのだという。
「そうしないとインクを吸いこみすぎて、発色が悪くなってしまうんです。定着剤を使うのは、感覚的には五色印刷(編注:オフセットにおけるCMYK+特色)に近いですね」
後日、講談社業務企画部・土井秀倫部長(後述)の話でさらにわかったのは、この定着剤は紙全体でなく、一文字ごと、そのかたちでふきつけられているということだった。K(ブラック=墨色)のインクを、そのうえに重ねていく。私たちが読むこの文字は、ミクロな技術で、インクがそのかたちに二重にふきつけられたものなのだ。
デジタル印刷が苦手とするのは、デザインの意匠やイラストのためにスミベタ(Kの濃度100%の色)を広範囲に施すこと。インクジェットの縦の線がどうしても出てしまいがちだ。紙の表裏でスミベタが重なってしまう場合は、水分量をめぐる調整の難度も跳ね上がる。むしろこれは、編集側がつくる台割(雑誌や本のページ設計)や、デザイナーの側に託される問題かもしれない。
オフセット印刷でカラーページ入稿後に確認する色校正も、デジタル印刷では存在しない。本番の印刷前に、印刷会社に色味の調整をお願いする工程はないのだ。基本的にはデザイナーがDTPで制作したデータがそのまま出力される。デジタル印刷の特徴を予めデザイナーの側が摑み、適したデザインにしておく必要がある。Iさんは語る。
「インクの粒は、オフセット印刷の『網点』(編注:小さな点のパターン)の密度とは異なるので、シャープさを出そうとするのではないイメージのデザインのほうが、向いているかもしれません。文字にかんしては、視力がよい若者だと、シャープではないと感じる人もいますが、まあルーペで見ればたしかに、というぐらいです。このほうが目に優しくて読みやすいという方もいますし、好みにもよるのかな、と思いますね」
印刷されたロール紙は、DSRの製造ラインの後ろ半分、製本加工のセクションへ。ひとつの折=十六ページ分が、A5のサイズに折り畳まれ、さらにカットされていく。製本が進み、別途TOPPANがオフセット印刷で手がけた表紙と合わせて、私たちが知る『群像』ができあがる。DSRで可能なのは並製本(ソフトカバー)、そして無線綴じ(本文の背に糊を塗布し表紙を貼り付ける)のみだ(5月号から折り込みの目次がなくなった所以だ)。

一冊の『群像』が刷り上がるのにかかる時間は、製造ラインの各セクションのタイムスパンが異なるため、単純計算はできないようだ。とはいえ、DTPデータから刷版、印刷、製本と、最短で数日かかるオフセット印刷に比べて、わずかな分数で刷り上がることは間違いない。
できたてほやほやの『群像』を、古郡さんが「どうぞどうぞ」と手渡してくれる。編集者たちから小さな歓声が上がる。背糊がまだ、じんわりとあたたかい。本文の文字は、今年四十歳の筆者がオフセット印刷時の『群像』と見比べた限り、目立った違いはなかった。
見学が終わり、建屋の出口へ向かう。その脇に、前身機導入時にHP社から贈られた「日本国内第一号機稼働記念」のパネルが飾られていた。それを見ていた私たちの傍で、Iさんが照れくさそうに「一号機の最初のオペレーターだったんですよ」と、ベテランの矜持を微かに滲ませながら笑みをこぼした。
屋外へ出ると、またふっと、オフセット印刷のインクの匂いが漂ってきた。私たちは、技術の狭間を歩き、帰りのバスへ向かった。戸井編集長に「どうでした?」と訊ねる。
「『触ってみてくださいよ、あたたかいでしょう』と『群像』を手渡してくださったあの感じは、生まれたての赤子を抱かせてくれるのと同じ。デジタルというと冷たいイメージがあるけれど、いろんな職人さん一人ひとりの”顔”が見えて、勇気づけられましたね」
デジタルによる小ロット印刷の可能性
「デジタル印刷が進化してオフセット印刷の領域に到達するのではなくて、私は初めから別物だと考えているんです」
4月8日、講談社。DSRに十年以上携わってきた、先述の土井・業務企画部部長に話を聞くと、工場見学での体験が肉づけされていく感覚があった。
十年以上? そう疑問に思った人もいるかもしれない。実は講談社が国内の出版社として初めてHP社製の大型インクジェット輪転印刷機を導入したのは、2012年のこと。土井部長は2014年から、業務部の一員としてその印刷機を担当し、DSRの可能性を追求し始めた。焦点を当ててきたのは、小ロット印刷がもたらす利点だった。
DSRによって、文庫や新書、あるいは社内の他のレーベルでも、余分な在庫をもたなくてよくなる。必要なときに即日で製品を完成させ、ロングテールの売上維持に貢献できる。その意味では、たしかにオフセット印刷とは目指す先が異なる「別物」の技術だ。

「DSRはオフセット印刷と比べて、どれくらい安く刷れますかと聞かれることは度々あります。でもこれは、『少なく、早くつくる』ことでトータルのコストを下げるための機械なんです。在庫をもたなくていいから、廃棄しなくてよくなる。極端にいえば、明日売るものを今日つくればいいんです」
小ロット印刷に基づく経済的なメリットこそが、DSRの本懐だ。大量印刷に適したオフセット印刷に比べ、DSRに向いているのは、最少五十部から最多二千部ぐらいのあいだの部数だという。しかし『群像』の発行部数は、この適した小ロットの部数を遥かにしのぐ。同誌のデジタル印刷への転換は、土井部長曰く「これまでのロジックとは異なる」ものだったのだ。結果として、『群像』はおそらく初めてデジタルのインクジェット印刷で刷られた商業誌となった。
デジタル印刷の先にある未来
今回の転換の直接のきっかけは、2024年の秋頃にTOPPANから講談社へ、『群像』を含めてA5判を刷ってきたオフセット輪転印刷機を近いうちに廃台にするという知らせが届いたこと。刷れなければ、雑誌は世に出ない。戸井編集長が「すわ廃刊か」と焦ったのも道理ではある。土井部長は即座にさまざまな代替案を検討していった。その結果、十年以上かけて技術を磨いてきたDSRに賭けるのがベストだと判断した。
折しも2022年、DSRの印刷機を現行のものへアップデートし、解像度が600dpiから1200dpiへと上がっていた。「写真が綺麗になるのは予想通りでしたが、明朝体の横棒がすごくシャープに、スッキリ見えるように刷ることができることもわかった」のが、後押しとなった。TOPPANからの突然の知らせではあったが、文字がみっちり並ぶ文芸誌をデジタル印刷する気運が、にわかに高まった。
とはいえやはり、『群像』の本文用紙の件はネックだった。リーズナブルなザラ紙「苫特クリームN」は、定着剤を用いればインクジェット適性をもつことはわかっており、継続使用は可能だったが、実際の印刷の品質がどうなるかは不透明だった。土井部長はKPSプロダクツと共にすぐにテストを行い、2024年末にはサンプルを制作。戸井編集長に掛け合い、年明け2025年1月には、編集部一同がDSRの工程を見学し、決断に至ったという。十年以上のDSRの歴史を踏まえつつ、いざとなれば突貫といえるスピードでの、デジタル印刷への転換。カラーページの面白さは、副次的に発見されていった。

土井部長は、この『群像』デジタル印刷化のさらに先を見据えている。世の印刷も製本も、すべてが現状のままで続くことはそうそうない、とは誰でもわかる。ならば、どんな本や雑誌のかたちが可能なのか?
その応答を筆者なりに引き受けつつ記すとすれば、要は、このデジタル印刷化された『群像』が、未来の雑誌や本のサンプルのひとつとなるかもしれない――ということだ。大げさに聞こえるかもしれないし、商業印刷に限った話ではあるが、一定のリアリティはあると思う。
並製本・無線綴じが、ほとんどの本や雑誌の姿になる、そんな将来を想像してみるということ。ほぼすべての本がペーパーバック化する未来。他社の事例であれば、小学館が昭和文学の作品を掘り起こしている「P+D BOOKS」のようなかたちが、文芸誌や文芸書の基本となるということである(「P+D」は「ペーパーバック&デジタル」の略)。
土井部長は、熱をこめて語った。
「海外のデジタル印刷の最新トレンドは、一冊ずつ厚みや判型を変えて刷っていく『バリアブル』と呼ばれる印刷の仕方です。最新の機械は自動的に、一冊ごとに厚みも判型も変えて連続で刷っていってくれる。デジタル印刷には、そういう可能性もあるんですね。DSRは判型までは変えられないのですが、手動で厚みを変えることはできます。
いまDSRは文庫や新書を中心に印刷していますが、ゆくゆくはカラーページを入れ込んだ単行本も刷ってみたいですね。実際にいま、『群像』ではカラー印刷を生かしたいろんなアイデアが出てきているようですが、それを単行本化するときにもカラー印刷することができるわけです。DSRが真価を発揮するのはこれからだ、と私は信じています」
『群像』オフセット印刷の思い出
5月7日、私たちはTOPPAN川口工場へ向かった。『群像』を2010年1月号から刷り続け、間もなく役目を終えるA判用のオフセット輪転印刷機と向き合い、同誌を手がけてきたオペレーターたちの話を聞くために。
広い敷地に、大きな建屋がいくつも立ち並ぶ。2023年10月にTOPPANへ社名変更する前のこと、凸版印刷は2016年12月、点在していた出版生産拠点をこの川口の地へ集約・効率化し、約百億円を投じて総合的な拠点として再構築した。現在も生産拠点の効率化の真っ最中。機械の更新や移設、いわば工場内の大々的な引っ越しが進む。
そのプロセスのなか、『群像』を刷ってきた印刷機、その名も「AW13号」がいま、廃台秒読みという段階にある。
「AW13号」は「Aタテ倍」と呼ばれる仕様で、A5判とA4判を――A4判の1色印刷の雑誌は少ないので実質的にA5判を中心に――、ふたつの折を巨大なロール紙にタテ方向に並べ、一気に印刷していくことができる。

ちなみに戸井編集長が編集後記に書いた「老朽化」という廃台の理由は間違いないようだが、筆者が現場で言外に感じ取ったのは、出版・印刷界全体の環境の変化もまた大きな背景となっているのではないか、ということだった。推測も含めつつ記すが、現在も元気に稼働している「AW13号」がいますぐ壊れるわけではなさそうだ。どうやら印刷機メーカーによる部品製造や修理がだんだん難しくなっているようで、その意味ではたしかに避けられない「老朽化」の途にあるのだろう。と同時に、「AW13号」が刷ってきたA5判雑誌というのは主に文芸誌・小説誌や総合誌(以前であれば論壇誌も)であるという事実、昨今の雑誌市場の動向を踏まえた将来的な採算性……今回の廃台という決断の裏に想定しうる複合要因のことを、私たちみんなが考えていかねばならないはずだ。
川口工場第一印刷部第二課・課長の伊藤淳さんをはじめとしたTOPPAN社員の皆さんは、いくつも『群像』にまつわる思い出話を披露してくれた。活版印刷からオフセット印刷に切り替えた最初の『群像』、2010年1月号では、実は折によって印字濃度にバラつきがあるという。今回のデジタル印刷同様、かつてのオフセット印刷機のオペレーターにとっても『群像』を刷るのは初めての経験だった。早い折のページではインクが濃く刷られすぎてしまい、三折、四折と作業を重ねるなかでなんとか調整をしていった。改めて当該の号をパラパラめくると、たしかに冒頭のほうのページの文字は濃く、後半へ向かってだんだんと安定していくのがわかる。実は濃度管理が機械化されたのは、いまから十年ほど前、ポータブルの濃度計が発売・導入されてからのこと。それまではオペレーターが目視で確認・調整していたそうだ。
「苫特クリームN」という本文用紙も、実は2021年10月号以降のもの。それ以前の用紙をつくっていた製紙会社の工場が生産中止となり、TOPPANがテストを重ねた結果、現行の用紙を使うことができている。
2024年6月号の印刷直前、編集部に急遽確認を入れた話には、思わずクスッとさせられた。第67回群像新人文学賞を受賞した豊永浩平「月ぬ走いや、馬ぬ走い」の本文に、ダーッと大々的に打ち消し線が引かれている個所があった。伊藤さんが振り返る。
「校了紙にあるものなので大丈夫かなとは思ったのですが……。オペレーターの目からすれば正直怪しい文面だったので(笑)、念のため問い合わせさせていただいたところ、ママOKということでした」
驚いたのは2023年6月3日、台風二号による水害のエピソード。工場の真横には新芝川が流れているのだが、納期目前、翌朝から製本という段階で、水位上昇のあおりを受けて「AW13号」が設置されている棟のマンホールから水が溢れ出てしまい、設備の稼働を一時停止。水害を受けておらず同様の機能をもつ「AW10号」で急いで刷り、なんとか納期に間に合わせたという。
オペレーターたちと共に、修羅場も潜り抜けてきたオフセット輪転印刷機「AW13号」。案内のもと工場のなかを進むと、轟轟と音を立てて稼働中のその姿があった。DSRの二倍はありそうな背丈。見学時は、当該機では珍しいというコミック誌の印刷をしていた。特色インクの入った缶が置いてあり、その粘り気と匂いがオフセット印刷の光景を成す。

印刷機の廃台が意味するもの
「AW13号」とは、もうすぐお別れ――しかし、意外にも寂しさは感じられなかった。思い至ったのは、廃台という出来事が、TOPPANをはじめ印刷業界にとっては日常の一端なのでは、ということだった。いや、一台の印刷機が工場から消えるのは一大事ではある。廃台にしようとしても繁忙期の細かな波があり、難しいこともあるようだ。だがTOPPANの説明によれば、川口工場は「活輪」からの「オフ化」(活版輪転印刷機からオフセット印刷機への転換)が完了している。にもかかわらず同じオフセット機の「AW13号」が廃台となるのは、今後の構想から抜け落ちたのだ、と筆者の目には映った(「AW10号」も含め複数台あったAタテ倍のオフセット輪転印刷機は、ここ数年で徐々に廃台となってきたのだという)。
そこにはむしろ、印刷の未来を切り開こうとする人々の姿が見える。川口工場内の大規模な引っ越しは、おそらくそのためだ。「TOPPAN」のロゴが外壁に掲げられた巨大な建屋の内部には、もうひとつの印刷の未来が胎動していると言えるのかもしれない。
この日は、『群像』の活版印刷が最後となった2009年12月号でオペレーターを務めていたという、三沢清さんも帯同してくれた。
「活版印刷最後の号と、オフセット一発目の号は二冊ずつ私物として購入して、両親に一セット渡しました。やっぱり、自分の仕事には誇りをもってやってきましたから。今日は自分の手元のセットを持参したんです。十六年の歳月を経て、まさかこうした場に立ち会えるとは、思ってもみませんでした」
新しい本のはじまり
帰路のバス車中。見学に参加していたデザイナーで、『群像』のアート・ディレクターを務める川名潤さんが、「いまさらかもしれないけれど、ちゃんと見に来られてよかった」と感想を口にしながら、刺激的な言葉を漏らした。
「オフセットも含めて、私はこれまでの印刷技術それぞれに味わいを感じてきたし、愛着があります。だからDSRには当初、思うところはあったんです。印刷の質はオフセットとは別物なので、カラーの部分などはDSRの特性に合わせたデザインにしています」
川名さんが連想するのは、かつて写研が写植用に開発し業界で多用された美しい書体が、DTPが普及して三十年この方、使えなかった期間のこと。モリサワと写研が共同開発した「写研フォント」が2024年以降ようやくDTPでも使えるようになってきたが、現状のDSRをめぐる感覚は、写研の書体が不在だった期間のそれに近いのは否めないという。
「でも、SNS上で『群像』のカラーページを読者の皆さんが喜んでいて、目がひらかれたところもあるんです。自分がこだわっている領域は、とても限られたものかもしれない、って。改めてDSRならではの可能性は追求したいですし、DSR自体もどんどん更新されていってほしい。私は写研フォントをDTPで使えるようになったいまが、デザイナー人生で一番楽しいんです(笑)。DSRとも、そんな付き合いができるようになればいいですね」
文字の話になったのは奇遇で、取材を進めながらいつも念頭にあったのは、前掲の『季刊・本とコンピュータ』で編集長を務めた津野海太郎さんによる文章「レイ・ブラッドベリ再読」だった(『電子本をバカにするなかれ 書物史の第三の革命』国書刊行会)。
本の終焉をめぐる物語だと世に思われ、津野さん自身もかつて批判したレイ・ブラッドベリ『華氏四五一度』を読み直すテクストだ。滅んだ本を記憶した老ブックマンたちは、それを「旧式の印刷機」を使って文字に写し取ることはない。そして津野さんは「この物語が終ったあとの世界にこころをひかれる」と言い、変わりゆく記憶と共に世界を放浪するブックマンたちの姿を夢想する。それこそブラッドベリが描きたかったことだろう、と。
むしろかれは本の新しいはじまりについてこそ語りたいと考えていたようなのだ。もし本が滅びなければならないとすれば、その理由は本の外側(国家権力やハイ・テクノロジー)だけではなく、きっと本の内側にも準備されているはずである。そう考えたからこそブラッドベリは、この物語の最後で、ブックマンたちにかれらの愛する古い本のかたちを捨てさせたのではないだろうか。しいられた本の死を自分からすすんでえらびとる。私が想定する『華氏四五一度』の後日談はそこからはじまる。
そして、謎めいた一節で文章は終わる。
では文字は?
文字はいちど死んだ。そして何百年かたったあとに、ふたたび生まれてくる。そのとき文字は以前あった文字とは別のものになっている。ローマ字アルファベットでも「あいうえお」でもない。吟遊詩人に変身した未来のブックマンたちは、かれらが語りついできた物語をその新しい文字によって書きしるす。いつ実現するともしれない新しい本のはじまり。おそらくそれが老ブックマンのいっていた「最後の勝利」ということの本当の意味だったのだろう。
筆者には、この「文字」をめぐる結びの一節の意味が、何度読んでもわからない。が、どうやら今回の、『群像』という文字だらけの文芸誌の印刷をめぐる小さな旅は、この「新しい文字」と「新しい本のはじまり」にかかわりがあるらしい、ということだけは察せられる。何百年とはいわない、せめて数十年経った後、本稿の記録が何かしらの「はじまり」に連なっているのならば、そのときには老ブックマンでさえなく、この世から消え去っているかもしれない筆者にとっても嬉しい。