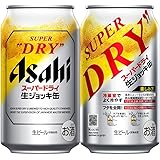このままじゃ、地球がまずいーー。
“気候変動”という言葉が、いつしか“気候危機”と呼ばれるようになり、数年が経つ。地球温暖化による環境破壊は、遠い世界の話ではない。それは、私たちの暮らしに直結する問題であり、生活するすべての人が“当事者”なのだ。
マイボトルを持ち歩く。脱プラを意識する。家庭ゴミを減らす。環境にやさしい生産背景のプロダクトを選ぶ。そんなふうに、“無理なくできること”を模索しながら、小さなアクション、ときに大きな挑戦に取り組んできた人も、少なくないはずだ。でも、それってどれほどの力を持つのだろうか? 地球のためになっていると、自信を持って言えるだろうか? そんな疑問や不安を抱えている人もいるだろう。中には、その葛藤に疲れて、気持ちが離れてしまった人もいるかもしれない。
これから紹介するのは、そうしたアクションを“暮らしそのもの”として楽しみながら取り組んでいる、ある若者たちのストーリー。東京・吉祥寺にある一軒家で共同生活を送りながら、環境やジェンダーをはじめとする社会課題と向き合う。そんな彼らの日常と、その背景にあるぶれない眼差しを通して、どんな小さなアクションでも、それを続けること。そして、隣にいる誰かと対話すること。そこに大きな意味があるということを伝えたいーー。
▶︎お話をうかがったのは
メイン写真・左から
中村萌さん(環境NGO職員)
立山大貴さん(写真家)
小林七海さん(編集者)
尾崎靖さん(編集者)
※尾崎さんはこの家では暮らしていません。
この家に暮らす、彼らの素顔
東京・吉祥寺。緑道の沿いに佇む、立派な一軒家。この家で、20〜30代の若者たち6人が、共同生活を送っている。そのうちの3人は、「Spiral Club」というオープンコミュニティの中心メンバーであり、“対話”を軸に、地球の未来について、誰もが自分ごととして考えられる場づくりを行っている。

Spiral Clubが誕生したのは、2019年のこと。環境NGOでボランティア活動をしていた8人が集まり、「もっと自由に、自分の関心や得意な表現を活かしながら活動できる場所がほしい」という思いのもと、はじまったオープンコミュニティ。立ち上げメンバーのひとり、中村萌さんは当時をこう振り返る。
「NGOでの活動は、みんながひとつの課題に向かって、同じ方向にアプローチするのが基本。それはそれで大きな力にはなるけど、一人ひとりの個性を100%活かすことができない。当時、ボランティアグループを率いていたスタッフの1人がそんなモヤモヤを抱えていて。だったら、それぞれの個性を活かしながら活動できる場を自分たちで作ろうよって。そこからSpiral Clubが生まれました」(中村さん)
絵を描くのが得意な萌さんをはじめ、モデル業に携わりながら気候危機の発信に情熱を注ぐ人や、自然界の魅力を音楽で伝えるラッパー。イルカやウミガメと泳ぐのが大好きなメンバーなど、「当初は、本当に個性が強くて、ちょっと変わったメンバーばかりでした」と、中村さん。
立ち上げ時は8人だったメンバーは、今では20人を超えるまでに広がった。変わらず活動を続ける人もいれば、ライフステージの変化や、自分の個性を活かして、巣立っていった人もいる。東京という都会の真ん中で、地道に活動を続ける中村さんによると、「Spiral Clubは、ボランタリーな集まりなので、心は”そこ”にあっても、活動に関わっていない人もたくさんいます」とのこと。

現在、Spiral Clubのコアメンバーとして活動する立山さんがメンバーとして加わったのは、今から5年ほど前。地元、熊本の大学で地球環境学を学んでいた頃のことだった。
「当時、大学で地球環境学を専攻していて、本当にまずいかもという危機感がどんどん強くなっていって。でも、まわりを見ても、同じように“ヤバさ”を感じている人がいないどころか、関心もなさそうで……。もっと危機感を共有できる仲間がほしいと思って、ネットでいろいろ調べていたところ、Spiral Clubのインタビュー記事を見つけたんです。コレだ!と思って、すぐにコンタクトを取ったのが、メンバーになったきっかけです」(立山さん)
小林さんが、Spiral Clubのメンバーとして、環境問題に本格的に取り組むようになったのは、この家で暮らし始めてから。それまでは、クィアの権利やフェミニズムには関心があったものの、環境問題については、「知ってはいるけど、正直、心が動いていなかった」と振り返る。
そんなある日、もともと知り合いだった中村さんから「一緒に住んでみない?」と誘われ、迷わず引っ越しを決意。そこから、日々の暮らしの中で少しずつ環境問題への眼差しが変わっていき、気候危機がようやく自分ごととして腑に落ちていったという。
「“地球とのつながり”を感じながら生きている人たちが、目の前にいる。最初はその状態が、すごいなと思ったんです。そんな人たちと生活をしているうちに、『私ももっと知りたい』って、自然と思うようになっていきました。それまでは、植物はすぐ枯らしちゃうタイプ。部屋に入ってきた虫もすぐにつまみ出してたけど、最近では優しくなれるように。
この家では、日常的に農、政治、生き物のことなどを話すのが当たり前。そんな恵まれた環境のおかけで、気候危機がだんだん自分ごとになってきた気がします。いわゆる勉強ではなく、住みながら、ゆっくりと腑に落としていった感じですね」(小林さん)

引っ越す前も、家の電力を再生可能エネルギーに切り替えたりはしていたものの、気候危機については、どこか他人事のように感じていた。でも、この家での暮らしを通じて、少しずつ“痛み”を、リアルに感じるようになっていった、と小林さんは語る。
Spiral Clubの初期メンバーである尾崎さんは、この家には暮らしていないものの、活動の立ち上げ当初から関わっている存在だ。年齢はほかのメンバーよりずっと上だが、取材を通じて感じたのは、それをまったく感じさせない、あたたかくてフラットな信頼関係だった。
「6年前。Spiral Clubが立ち上がったばかりの頃に、カリフォルニアのレストラン<シェ・パニース>でヘッドシェフをしていたジェローム・ワーグが、日本で料理イベントをするっていう話を聞いて、遊びに行ったんです。<シェ・パニース>は、アリス・ウォータースがはじめたレストランで、オーガニックとか地産地消とか、そういう“サステナブルな食のあり方”を世界中に広めた店。
そのとき自分は何も考えずに割り箸を持って行ったら、まわりを見るとみんな“マイ箸”を持ってきていて。環境意識の高いかっこいい若者がたくさん集まっていて、ちょっとショックでした。(笑)で、そのときに出会ったのが、ジェロームのパートナーであり、徳島・神山町の『森の学校みっけ』で代表理事を務める松岡美緒ちゃん。美緒ちゃんから、Spiral Clubの構想を聞いて、面白そうだなと思って。メンバーに入れてもらったんです」(尾崎さん)
価値観の違いが想像力を育む。対話の尊さ。
Spiral Clubの原点にあり、今でも変わらず大切にしているのが“対話”。環境をはじめとする社会課題は、一人で解決できるものではない。多様な立場や考えを持つ私たちみんなの心が、同じゴールへ向いていくためには、自分とは異なる価値観を知り、認め合うこと。対話は、互いに歩み寄るきっかけを与えてくれる。
「気候危機をはじめ、どの社会課題も、“ひとつの対話”が連鎖していくことが、課題解決の糸口につながっていくんじゃないかと思うんです。たとえば、パレスチナに対するイスラエルの戦争犯罪もそう。今この瞬間にも、多くの人が命を落として、子どもたちが飢えている。だけど、東京で暮らしていると、それを“ないこと”にするのって、簡単なんです。
ニュースを見なければ、知ろうとしなければ、一見すると自分の生活に影響がないと感じるから。そうしない、させないためにも、誰かとの対話を絶やさないことが大事。頭の中で一人で考えているだけでは、何も変えられないんです」(中村さん)
Spiral Clubが主催するオープンミーティングでは、あらかじめ対話のテーマを設けることもあれば、“今感じていること”をざっくばらんに話すこともある。そして、ときには、1冊の本を議題に意見を交わすこともある。
メンバーでなくても、誰でも気軽に参加できるが、なるべく全員が安全だと感じられる状態で対話を進めるために、いくつかのグランドルールがある。そのひとつが、「自分と異なるアイデアも、まずは否定せずに聞いてみること」。

対話は、そうした姿勢を、日々の暮らしのなかでも忘れないためのリマインドのような役割も果たしているのだという。
「たとえば、気候変動に危機感を持っているもの同士でも、ビーガンの人も、そうじゃない人もいます。動物の肉を食べないことが絶対だという人もいれば、植物だって同じように大切な命だと感じる人もいる。でも、それでもいいんです。私たちが対話で重要視していることは、“分かりあう”ではなく、”自分とは違う価値観に触れること”。対話の尊さは、その“価値観のズレ”の中にこそあると思います。
たしかに、同じ価値観を持つ人たちと一緒にいると、そこでしか得られない安心感や心地良さはあります。でも、誰もがみんな自分とは違う尺度を持っている。そのことをちゃんと認めて、どんな声にも耳を傾けようとしなくては、この運動は広がっていかない。なぜなら、思いを誰かに伝えるためには、相手のことを理解しようとする“想像力”が必要だから。対話とは、その“想像力”を育むためのものなんじゃないかとも感じています」(立山さん)
そして、彼らの対話は、自分の価値観を押しつけあったり、正しさをぶつけあう場ではない。
「対話は、決して誰かを説得するためじゃない。自分の考えを深めたり、新しい視点に触れたりするためにあるもの」だと、中村さんはいう。
とはいえ、置かれた環境や立場、価値観の異なるもの同士の対話は、ときに反発が生まれたり、すれ違ったりもあるだろう。相手の話を真っ直ぐに聞くことは、きっと簡単なことではない。ときには、エネルギーを使いすぎて、ぐったりと疲れてしまうこともある。けれどそれこそが、自身の活力につながっている。そう小林さんは、語る。

「オープンミーティングには、いろんな属性や背景を持つ人が来てくれるんですが、みんなそれぞれ違うステップにいるから、気候変動への危機感も社会課題との向き合いかたもさまざまです。たとえば、自分がノンバイナリーだってことを言わずに話していると、やっぱりミスジェンダリングが起こることもあって。それ以外にも、『すべての線が交わっているわけではない』と感じることが、たびたびあります。それでも対話を続けていくと、ふと”分かり合える瞬間”が訪れることもあるんです。
もちろん、帰り道にすごく気持ちが沈んで、めちゃくちゃ疲れる日もあります。でもその“疲れ”が、時間が経つと不思議と活力に変わっていたりするんですよね。『ああいうことがあったけど、次はもっとうまく話せそうだな』とか、『こういうとき、あんなふうに言える自分でよかったな』って、あとから気づいたりして。ときにしんどくなることもあるけど、結果として自分にプラスになっていると思います」(小林さん)
オープンミーティングのあと、家に帰ってもなお3人(ときに尾崎さんも)の対話は止まらないという。「あのとき、こう思ったんだよね」なんていう話から、また新たな対話が生まれるーー。
「家に帰っても、ずっと話しています。もっというと、自分たちは“対話ばかりしているグループ”と言っていいほど、対話が日常です。対話が続けば続くほど、“自分の知らないこと”に気づけるんですよね。Spiral Clubのオープンミーティングは、主催者側である自分が“伝える側”で、参加者が“受け取る側”という構図じゃなくて、自分にも相手にも、誰にでも知らないことがあるよねっていうフラットな関係性が心地いいんです」(小林さん)
課題は「地球との接点」が見えにくいこと
月1回のオープンミーティングを開催するようになって、2年近く経つ。少しずつ参加者は増えてはいるものの、気候変動に関しては、まだまだ”自分ごと”として捉えることのむずかしさを感じている人は、少なくないという。
「やはりどれだけ対話を重ねても、なかなか実感が伴わないというか……『最近暑いよね』とか『雨が増えた気がする』とか、そのくらいで話が止まってしまうことが多いんです。とくに都内に住んでいると、その範囲で完結してしまうというか。自分の生活の延長線上で話すって、むずかしいなと感じます。
たとえば、何か行動を起こしたり、暮らしを少し変えてみたりしても、その結果がすぐに見えるわけじゃない。だからこそ、“地球との接点”みたいなものが、見えにくいんですよね。気候変動に危機感を持っている人でさえむずかしいのだから、そうじゃない人にとっては、もっとハードルが高い。自分の場合は、大学で地球環境学を学んだから、考えるきっかけを得られたと思うし、もしそれがなかったら、まだ気づいていないかもしれない」(立山さん)
自分ごととして環境問題を考えるには、実際に地球へのダメージを目で見ることも、もちろん大切。けれど、身近な人から受ける影響のほうが、気づきに繋がることもある。

「『この人と一緒に心地よく過ごしたい』とか、『この人の話をもっと理解したい』という気持ちが芽生えることって、あると思うんです。それってやっぱり、対話があってこそ生まれるものだと思っていて。だからこそ、まわりとつながることが、環境に関心を持つための一歩になるんじゃないかな」(立山さん)
「見た目や肩書き、立場など、条件で人を判断しない。どんな発言も否定はしません」と、中村さんは語る。また、「Spiral Clubの集まりは、いつも笑顔がある」そう尾崎さんが語るように、このコミュニティには、誰もが心にある思いをそのまま言葉にできる、あたたかい空気が流れている。
後編「地球温暖化が本当にヤバい。平成生まれのグループによる「デモではないアクション」」では、そんなSpiral Clubが手がける、オープンミーティング以外の活動について紹介する。
撮影/近藤沙菜 構成・文/大森奈奈