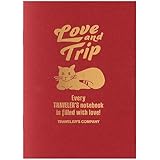今年、連盟結成100周年の節目を迎えた東京六大学野球で、例年以上に注目度が高いのが東京大学だ。
昨秋のリーグ戦で、2017年以来7年ぶりにシーズン2勝を挙げた。現メンバーには、ベストナインに選出された経験のある野手が3人揃い、投手陣もプロ野球・千葉ロッテマリーンズで活躍した渡辺俊介を父に持つ渡辺向輝を中心に力をつけている。そうした戦力の充実ぶりから、やはり2017年以来となる勝ち点獲得も狙えるとして期待感が高まっているのだ。
その東大野球部に、チームを陰ながら支える集団がいる。データ分析などを手掛ける「アナリスト部門」だ。
部門創設5年目の今年は総勢14名が所属する(取材時点)。アナリストを置く大学チームは今や珍しくはないが、東大は言わずと知れた日本の最高学府。頭脳明晰な彼らはいったいどんな活動をしているのか、取材した。

東大野球部アナリストならではの「2つの強み」
まず意外だったのは、アナリストの半分ほどが文系の学生だということ。4年生の内田倖太郎(工学部)が言う。
「論理的に考える力さえあれば、全然、文理は関係ない。選考などはしていませんし、うちのアナリストには野球未経験者もいるくらいです。野球を見るのが好きだったり、スポーツのデータサイエンスに興味がある人だったり。そういう野球オタクやパソコンオタク、数学オタクのような人材が混在していて、野球以外の文脈からもアプローチできるところはうちの大きな特徴かもしれません」
もう一つ、東大野球部アナリストならではの強みがあると内田は話す。
「アナリストの活動の中では、やっぱりプログラミングが肝になるんです。人数だけならうちよりも多い大学があるようですが、プログラミングの知識があり、自分で(コンピュータに命令を与える)コードが書ける人はほかの大学より圧倒的に多い。そこは自信を持っているところですね。部門のメンバーになってから、先輩の手ほどきを受けつつプログラミングを習得する人が多いです」
大学レベルといえど、扱うデータの量は膨大だ。日々の練習では弾道測定分析機器の「ラプソード」や、バットのグリップエンドに取り付けることでスイングのスピードや角度などを測れる「ブラスト」を駆使してデータを計測・蓄積しているほか、試合もデータ収集の重要な機会となる。
東京六大学では2019年秋のリーグ戦から弾道測定器「トラックマン」が採用され、試合中の計測データを各大学が分析に用いることができるようになった。東大ではそれに加え、オープン戦でも(相手チームの了解を得たうえで)データと映像を収集している。


こうして集めた“材料”をどう“料理”するかが重要となるわけだが、プログラミングの技術がないと、その整理や分析は手作業となり非常に手間がかかる。だがプログラミングができれば、膨大なデータを活用・閲覧しやすい形に整理するようなシステムを構築することができる。運用しながら自前で改善を重ねていくことも可能だ。
選手自身もデータ活用に精通する
東大では、試合中の特定の1球のデータを即座に確認し、かつ当該の場面の映像をすぐに呼び出せるシステムや、野球部員専用のデータサイトなどが整備されている。内田は言う。
「実は東大の場合、相手チームを分析するのは選手自身なんです。特に主力の選手たち。どの大学のどの選手を見るか、それぞれ担当が決められていて、対策の素案をつくります。アナリスト部門がなかった時代は、各々の選手が自分で分析対象の選手のデータを調べたり、映像をチェックしたりする必要がありました。でも今は、分析に必要なデータや映像はアナリスト部門が整理したうえで提供している。我々がプログラミングを使うことで効率化し、選手の負担を減らしてるんです」
要するに、アナリスト部門がデータ活用の基盤整備を担うことで選手による分析をサポートしているのだ。

データは、相手チームの分析だけでなく、自チームの選手のパフォーマンス向上にも有効活用される。選手自らデータを確認して自身の課題を探ることもあれば、アナリストに意見を求めることもある。そんなときに交わされる会話の内容が、なんとも東大生らしい。
例えば物理を履修してきた学生同士なら、こんなやりとりが成立する。
アナリスト「ボールに働く力は、回転のベクトルと速度のベクトルの外積。それは分かるよね」
投手「ああ。確かにデータを見ると、俺のスライダーがああいう曲がり方をするのも納得だ」
アナリスト「だからもし曲げ方を変えたいなら、この数値に意識を向けていろいろ試してみたらいいんじゃないかな」
野球部員の中でもとりわけデータへの造詣が深いのがアンダースローの右腕エース、渡辺向輝だ。内田は感心した様子で語る。
「渡辺はデータを使いこなしていて、もはやアナリストの側面も持っているのかなと感じます。自分が操る変化球一つひとつに関しても、『こういうデータが出ているときは良い』『こういう傾向があるということはいまいちなのかな』と、もう全部自分で分かってるんです。データを測っている僕らに向かって『今日の回転数なんぼ?』と尋ねてきて、答えを聞くと『ああ、なるほどね』って感じ。僕らの解釈は必要ないというか」
VRシミュレータを独自に開発
データ活用の基盤整備の部分は、東大野球部アナリスト部門にとっては、いわばルーティンワークだ。それとは別に、各アナリストがそれぞれの興味に沿って多様な取り組みをしている。例えば、「将来は物理の研究者になりたい」と話す内田は、VR(仮想現実)技術を利用したシミュレータを独自につくり上げた。
「VR機器を野球に応用するというアイディア自体は前から世の中にあるものですが、相手チームへの対策として使うなら自分でつくるのが一番かな、と。基本的なVRの技術は大学の授業で学びました。そのときに『VRは体験をプログラミングできる技術だ』という話が出てきて、印象に残りました」
空間コンピューティングで体験を創造する――内田は「これだ」と閃いた。東大野球部のメンバーがライバルチームに比して圧倒的に不足しているのは、強豪校との対戦経験。それをVRで補えると考えたのだ。
開発したシミュレータは打者向けのもので、ゴーグルをつけると、投手がマウンドから球を投じてくる映像が視界に映し出される。他大学に在籍する実際の投手のデータを基につくられており、投球フォームや各球種の球筋がリアルに再現されている。
東大史上初の野手としてのプロ入りを目指す酒井捷をはじめ、選手からは好評を得ており、現在は東大野球部の合宿所「一誠寮」の共用スペースに2台のゴーグルを常時用意している。試合が近くなると、それを装着して、対戦が予想される投手の球筋やタイミングを確認する打者陣の姿が頻繁に見られるという。

「変則の投手だとか、球のクセが強い投手と対戦するうえでは特に有効ですし、一度見ておくことで得られる心理的な効果も大きいのかなと思います。僕が予想していた以上に使ってもらえているので、すごく嬉しいですね」
「ミスすること」を前提に対策を練る
一方で、忘れてはならないのが「実践」という観点だ。
データ分析で相手打者の弱点が分かったとして、実際の試合でそこに投げ込めるのか。VRで相手投手の球筋をつかめたところで、本当にそれを打ち返せるのか。対策を「実践」する力量がなくては、せっかくの分析も意味をなさない。
内田は苦笑しつつ「そういう問題は間違いなくあります」とうなずいた。
「使えるような分析をしなくてはいけない、ということだと思っています。『ここに投げれば打たれない』と仮に分かっていたとして、うちのピッチャーがそこに投げ続けられるかというと、やっぱりそうではないので。だから僕たちは、投げミスがあることを前提で考えます」
投げミスした場合はどういうコースに球がいきやすいか。それを打ち返された場合は、どこにどんな打球が飛びやすいか。そこまで読んだうえで、打球が飛んでくる可能性が高い野手に注意を促す。「『できないよね』で終わるんじゃなくて、『できなかったときはこういうことが起こるから気をつけようね』というところまで考えることが大事」と内田は言う。
東京六大学の中ではスキル、フィジカルともに他大学に後れを取りがちな東大野球部だからこそ、より深い分析、より周到な対策がおのずと求められるのだ。

ただ、今年のメンバーに関しては他大学に引けを取らない実力を持った選手が多い。それゆえにむやみに計略を巡らせたり、突飛な作戦を使ったりする必要性は低そうだ。
「我々としては、いかに選手の能力を引き出せるかということを考えるのがいちばん大事だと思っています。今年の東大が勝ち点を獲得できる確率は、70%ぐらいあるんじゃないでしょうか。チームのみんなが、ここまでつくり上げてきたという自信を持っていますし、野球ですから『運』の要素も少なくない。相手のミスにつけ込んで点を取ったり……70%という数字も決して言い過ぎじゃないと思います」
現在開催中の春のリーグ戦で、東大は早稲田大学、明治大学(慶應大学)とすでに対戦を終え、いまだ勝利を挙げられていないものの、善戦を見せている。残る法政大学と立教大学とのカードで、今季初勝利、そして待望の勝ち点獲得のチャンスは十分にある。
陰ながら部を支えてきたアナリスト集団も、快挙達成の瞬間を心待ちにしている。

・・・・・・
【もっと読む】時間やお金はどうしてる?年間100試合参戦する「プロ野球の応援団」驚きの生活スタイルから懐事情まで…その「知られざる実態」