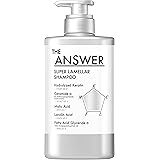第二次世界大戦時のドイツを代表する傑作戦闘機として有名なフォッケウルフFw190。ドイツ機として珍しい星型空冷エンジンを装備してあらゆる任務に活躍した航空史上に残る名機である。そのフォッケウルフFw190を特集したミリタリー雑誌「丸」6月号が航空機ファンの間で話題を呼んでいる。実は日本陸軍も戦時中に1機のFw190を研究用に輸入している。当時このFw190をテストした元陸軍航空審査部部員の荒蒔義次氏(元陸軍中佐)の手記「第一級戦闘機Fw190をテストする」から一部抜粋・再構成してお届けする。歴代の陸軍戦闘機を審査してきたベテランパイロットが語ったFw190の貴重な試乗インプレッションをご覧あれ。

「疾風」との乗りくらべ、実力はFw190に軍配
私は陸軍の航空審査部員としての経歴が長く、海軍機や外国の機体に乗る機会が多かった。フォッケウルフFw190に乗ったのは昭和18年秋のことであるが、その直前、私は南東太平洋方面に出ており、東部ニューギニアに集中したばかりの飛行機が敵の朝駆けに会って、狭い飛行場の中で無惨な姿に変わり果てたのを見、戦争の行方に暗いものを感じた。
この後、私は本国の審査部に呼び戻されたわけだが、そこに私を待っていたのがFw190と、本格的な審査が始まろうとしていたキ八四「疾風」であった。
こういうわけで、はからずも「疾風」とFw190を乗りくらべるような形になったのだが、戦闘機としての実力は、どうもFw190の方が上だったのではないかという気がする。
Fw190を初めて見た時の印象は、これは良さそうな飛行機だ、ということであった。最新式の「疾風」とくらべても遜色がないというか、古さを感じさせなかった。「疾風」は2000馬力級の最新鋭機であったが、Fw190は1700馬力で(日本に来たのはA-5型だった)、すでに完成いらい3年ほどたっている機体だったから、数字的にはもちろん「疾風」の方がいいに決まっているが、軽快さという点ではFw190の方が上だったと思うし、その他の、たとえば信頼性とか操縦性とか、数字に表われない要素も考えに入れると、どうしてもそんな気がする。
「疾風」の相手はムスタングを想定
「疾風」は2000馬力、Fw190は1700馬力である。ところが、「疾風」の方が重い感じがする。もちろん速度は「疾風」の方が出る。しかし、翼面荷重や馬力荷重などの数字を見ると腑に落ちないのだが、どうも「疾風」は重い。上昇も旋回もFw190の方が上である。これで格戦闘をやったら「疾風」が負けるだろう。
これは、一つには「疾風」のエンジンが規定通りの馬力を出していなかった可能性がある。しかし、それよりも、「疾風」はどちらかというと、高空を高速で侵入する敵機を迎え撃つような役割の、つまり格闘戦一本槍ではない戦闘機の必要が感じられはじめたころに計画された機体である。そして実際にも「疾風」の相手はムスタングあたりであったし、これとはまずまず互角に近い戦闘をしているのだから、それはそれでよいのであろう。
ジェット機のようなすばらしい上昇力
空戦では上昇力、旋回中の余裕馬力というものがきいてくる。この点でもFw190は一級品だった。
飛行機の離陸上昇は、性能計算や飛行実験で求められた最適の速度、迎角で行なうのが原則である。特殊な場合を除いて、パイロットは一定の速度を維持して上昇飛行を行なうのである。もちろんこの数字は機体によって、またその時の重さによって違ってくるわけだが、経験をつめば、離陸何秒後には今離陸してきた滑走路がどのへんに見えるか、というようなことはだいたいわかる。
ところが、最初にFw190に乗った時には少々びっくりさせられた。それまでの経験で見当をつけていた迎角が上昇飛行に入ったのだが、Fw190はどんどん加速してしまう。つまり、一定の速度ではなくなってしまうのである。それで、迎角をさらに大きくしてやる。オーバーな言いかたをすれば、今のジェット機のように機首を急角度にした姿勢でも速度が落ちずに、そのまま上昇してしまった。これは実に快適というか、愉快な感じであったが、このへんで水平飛行に入ろうというので、ふいと後方を見ると、飛行場の見え方が全然違うのである。これは上昇のよい飛行機だ、と感心したものである。