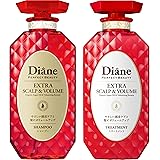うちの猫は「おすわりができない」
なぜ“うちの猫”は「おすわり」ができないのか。
飼い犬の多くは「おすわり」や「待て」ができる。中には、おやつを見つけた瞬間に、何も言わずとも、おすわり、お手、おかわりまでの一連をすごい速さでやる犬もいる。
対して猫の「おすわり」や「待て」はあまり見ない。でもSNSに投稿された動画では、皆無ではないことを教えてくれる。
では、なぜうちの猫はできないのか。できる猫とできない猫は何が違うのか。
東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生にペットにまつわる謎を解説いただく連載。
今回は、なぜ犬には簡単に教えられる「おすわり」を、猫ができないのか。インタビューでお話いただいた。
「できない」ではなく「やらない」
――「おすわり」「待て」ができる猫をネットで見ました。でもうちの猫に教えても、全くできません。できる仔は、できないうちの猫より頭がいいのでしょうか。
「何をもって頭がいい、と言うかはさておき、コマンドがわかる仔は、言葉を理解しているのは確かです。同じような環境下でも、すぐに言葉を覚えられる仔とそうでない仔がいますが、頭の良し悪しというより、個体差、性格の違いが大きいです。
また、言葉を知っていても、やるかやらないかは、別。猫は自分のやりたいことを優先する動物です。
犬が簡単に『おすわり』などのコマンドを習得できるのは、集団行動を基本とする共感力からくるものです。飼い主や家族と積極的にコミュニケーションを取るため、言葉を聞き取り、自分や仲間の置かれた状況を読み取ろうとします。
ちなみに、家族間で険悪な出来事があった時に、犬が仲を取り持ってくれたり、なぐさめてくれたりした、という話をよく聞きますよね。これも、群れで暮らす、犬らしい行動のひとつです。
一方、猫は、たとえ『おすわり』の意味がわかっていても、やるかやらないかはその子の気質次第、気分次第というところがあります。中には、飼い主に付き合って、コマンドを覚える仔もいますが、それは共感力の高い珍しいタイプ。
単独行動で生きてきた猫は、犬のように『飼い主を喜ばせたい』気持ちよりも、『自分がどうしたいか』を優先する仔がほとんどです。
とはいえ猫も、『ごはんだよ』の呼びかけに飛んできたり、『遊ぼうか』とおもちゃを取り出すと張り切ってみせたりします。反対にあまり好ましくないこと、たとえば、お風呂の前に『お風呂に入ろうね』とか、『爪切りしようか』などと声を掛けていると、隠れたり、逃げたりもします。
小さな子どもが、『ママ』『パパ』『ごはん』など好きな言葉から覚えるように、動物も好きなことと嫌いなことに関連した言葉によく反応することから、猫も言葉を理解はしていることがわかります」

食べ物に執着のある子は覚えやすい
――うちの猫にも、コマンドを教えられますか。
「猫の気質や性格によるものなので、一概には『できます』とは言いづらいですが、食べ物に執着のある猫は、覚えやすいかもしれません。食べ物がごほうびになるからです。
『犬は置き餌ができない』というのを聞いたことはありますか。犬に餌をあげると、ほとんどの仔がその場で食べきってしまうので、ごはんは時間を決めてあげてね、という意味です。これは、集団で狩りをし、食べられるときに食べられるだけ食べようという習性が残っているためです。犬は目の前に食べ物を見せられると、つい欲しくなってしまいます。
また、ごはんやおやつ以外にも、犬には『楽しい』『嬉しい』というごほうびもあります。ごはんやおやつをもらえて『おいしい』、遊びや散歩で『楽しい』、飼い主さんに褒められて『嬉しい』。こうしたごほうびが欲しくて、犬はコマンドを覚えるのです。
けれども猫には、こうしたごほうびがあまり効きません。たとえば、ごはんは飼い主が時間を決めて器に入れても、気分の向いた時に食べにくる。満たされれば、器に残したままでも、ふいっと立ち去る。遊びもごはんと一緒で、遊びたいときと遊びたくないときがある。猫の気分次第です。
また、猫は犬に比べて、飼い主との関係に依存していません。基本的には自分優先です。飼い主が不機嫌そうにしたり、望んでいないことをやらせようとすれば、距離を置く。めんどくさそうなことは避け、だったら寝よう、それが多くの猫の気持ちなのです」

なぜ、猫に言葉を教えるのか
「どちらが良い悪いではなく、習性も優先順位もまったく違う犬と猫。
人に近く、パートナーとしての関係を作りやすい犬に比べて、猫との関係は飼い主の片思いに近いものがあります。猫は自分の気持ちが乗っている時しか呼ばれても来ません。望んでいないときに触られたり、呼びかけられてもそっけない。いつも人と関わっていたい犬とは、違う生き物なのです。
もちろん、人間の性格がいろいろあるように、犬も猫も生き物なので、犬のように『構ってほしい』猫もいれば、あまりべたべたされるのを好まない犬もいます。
私は、猫に言葉を教えることには賛成ですが、無理に芸をさせるのは、お勧めできません。
言葉を教えるのは、人がペットの気持ちを理解したり、ペットにも今、置かれた状況を理解してもらうためです。猫がまだ若く、元気なうちは信頼を深めるために、そして、老いて、体が不自由になった時に、知っている言葉をかけてあげることで、動物たちの不安を軽減してあげたいからです。
犬も猫も、つねに言葉をかけてあげれば、生活に必要な言葉は理解します。コマンドをやるかやらないかは、猫任せでいい、そうやって猫の気持ちを尊重してあげることで、より絆は深まると思っています。
人間に飼われる以前、猫は自分の安全は自分で守り、自分の餌は自分で獲る、独立心旺盛なプライドの高い動物でした。猫の気持ちに逆らって何かさせることは、猫との関係にマイナスにしかならないことを忘れないでいてあげてください。
◇単独行動で独立心旺盛な猫と、集団行動で人間ともうまく共存していく犬とでは、気質が大きく異なる。飼い主と少しでも関わっていたい犬にとって、コマンドを出されることは楽しい遊びに感じられても、マイペースに過ごしたい猫にとっては、面倒のひとつと感じるのかもしれない。
後編「呼んでも来ない、抱っこも嫌がる飼い猫に『好かれているかどうか』を見極めるたったひとつの方法」では、抱き上げようとすれば逃げ、呼んでもなかなか出てこない飼い猫は本当に自分のことを好きなのか。不安になる飼い主に、「飼い猫が自分を好きかどうか」を見極める方法をお伝えする。