東畑開人さんが自身の総決算として書き上げた『カウンセリングとは何か 変化するということ』(講談社現代新書)。その刊行を記念して、9月23日に代官山 蔦屋にて神学者の森本あんりさんとのトークイベント「人生における物語とは何か?-心理学者と神学者が話し合う」が開催されました。
そのトークイベントの内容を、全三回にわたってお届けします。第一回では、森本さんが自身の人生を振り返った『魂の教育 よい本は時を超えて人を動かす』(岩波書店)をもとに、自分の物語を生きること、人が変化することについて話します。
(構成・文/小沼理)
※この記事はキリスト新聞12月25日号に掲載された対談の再録です。
宗教と心理学の共通点を探る
東畑:森本さんはこれまで「人が信じるとはどういうことか」を大きなテーマにして、そこにあるロジックをとりわけアメリカのキリスト教を素材として沢山書かれていて、僕は著作を追いかけてきました。というのも、それはまさに、僕が日々のカウンセリングで考え続けてきたことと重なるからです。宗教と心理学には似ているところがある。じゃあ、どこが似ているのか、あるいはどこは似ていないのか。このことを森本さんとお話ししてみたいと思っていました。今日はよろしくお願いします。
森本:こちらこそ、よろしくお願いします。
東畑:今回の対談の直接のきっかけになったのは2024年11月に出版された『魂の教育』(岩波書店)でした。この本では森本さんの歩んできた半生と、人生の節目に出会った本がリンクするように進んでいきます。後で触れますが、クライマックスでは森本さんの個人的な物語が一気に立ち上がってくる。その迫力に圧倒されました。
森本:ありがとうございます。東畑さんの読売新聞書評には、こちらも魂を打ち抜かれました。あの本でひとつの核になったのは、自分の名前です。実は、僕はずっと自分の「あんり」という名前が好きじゃなかった。『魂の教育』では、「あんり」という名前と自分の人生との因縁やつながりを綴っています。その意味で、自分の人生を振り返り、ひとつの決着をつけるような本です。
名前で言えば、東畑さんの「開人」というお名前にはどんな由来があるんでしょうか。「人を開く」って、まるでカウンセラーになることを運命づけられたような名前ですよね。
東畑:僕は親から「開く人」だと聞かされてきたんです。自分自身で人生を開拓していくイメージです。でも、結果的にはカウンセラーとして「人を開く」道になっていました。逆ですよね。でも、けっこういい名前なんじゃないかと思って、自分でも気に入ってるんです(笑)
森本:良い名前だと思います。響きもいいし、収まりもいい。なにせ僕と違って漢字だしね(笑)。
『カウンセリングとは何か』は、さまざまなテーマを読者に問いかけながら進んでいきます。冒頭で「カウンセリングの原理論を書く」と宣言し、そこからカウンセリングとは何か、人が変わるとはどういうことかを解き明かしていく。最後に、人間には科学的な生き方と文学的な生き方があって、人生のある段階を終わらせて次に進むには過去の物語を終わらせなくてはいけないと結論づけている。読んでいて、なるほどと感じ入りました。
語られてこなかった「個人が変わる」ということ
東畑:「個人が変わる」ということについて、ずっと考えているんですけど、なかなかアカデミアの他の学問からは理解されるのが難しいなと感じていました。社会構造や歴史、国家の変化はテーマにされても、個々人の人生が変わっていくことについてはみんなあまり関心ない(笑)。誰もが個人の変化は体験しているはずだし、その集積が歴史だと思うんですけどね。
ですが、キリスト教には「回心」という、人生の行き詰まりのなかで個人が神と出会い、違う生き方をはじめる体験がありますよね。カウンセリングをしていると、ユーザーはゆっくりとある種の回心をしているんじゃないかと思う瞬間があります。カウンセリングを通して、気づいたら自分の人生が変わっている。一方で、キリスト教はある特定の体験があって、電撃的に心が変わる印象があるのですが、いかがでしょうか。

森本:いや、実際には信仰も少しずつ心が変わっていくのだと思います。ある時点で関を越えて、振り返ったときに「あれが自分にとっての信仰のターニングポイントだったんだ」と分かるときがきます。変わったことに気がついて、「じゃあここで変わったってことにしましょう」と自分でケリをつける。それまでの人生の物語に決着がつくわけです。
東畑:なるほど。森本さんは20歳で洗礼を受けてクリスチャンになっています。人生の途中で新しく信仰の道に進むのは大変なことですよね。
森本:それが『魂の教育』のテーマでもあります。基本的に人間が変わるのって、恥ずかしいんですよ。善男善女ならともかく、僕みたいに嘘と悪行だらけの人生を送っていた人間が、ある日突然クリスチャンになったなんて言い出すと、周りの人は全然信じてくれない。「なんであんなやつが」って。
東畑:『魂の教育』を読まれた方はわかると思いますが、森本さんの青春って本当にひどいんですよ(笑)。学生時代、地下鉄の線路に勝手に侵入して歩いたりしてますから。めちゃくちゃです。
心の変化という文脈で考えれば、カウンセリングだと自分が変化したことを他人には宣言しない。でも信仰の場合は宣言しますよね。
森本:たしかに「信仰告白」という、自分の信仰を外に宣言するプロセスがあります。カウンセリングの場合、ユーザーは変わったことを自覚したり宣言したりしないんですか?
東畑:自分が変わったという自覚はしていると思います。そしてカウンセラーもその変化に気づく。でも、信仰と違って外から見るとその変化はあまり分からない。
心理学者の河合隼雄はユーザーから「変わるも変わる、私は360度変わりました」と言われたというエピソードをよくしていました。360度って、側から見ると変わっていないですよね。そこがまた深い。
森本:うーん、でもユーザーが最後に「カウンセリングを終わりにしようと思います」と言うのは一種の宣言でしょ?
東畑:ああ、たしかにそうですね。『カウンセリングとは何か』では古い物語をちゃんと終わらせることの価値を書いていますが、終わるというのは「私は変わったんだ」という宣言とも言えます。
『魂の教育』では、「自分はどうして神学者をやっているんだろう」ということが問われます。なぜ現代の日本に生まれて、キリスト教の道に進んだのか。
また、本の最後には、森本さんが幼い頃に亡くなられたお母さんのエピソードが記されています。森本さんの記憶にはほとんどないんだけど、実はお母さんは亡くなる直前にキリスト教の洗礼を受けていた。その信仰告白の文書が残っていて、そこでお母さんは息子の「魂の教育を、主なる神に委ねた」と書いていました。
森本:そうです。
東畑:そのことを、森本さんは大人になってから知るんですよね。そして、実際に自分がキリスト者になっている事実に気づいて、初めて自分が自分であることを受け入れる。すごく強度の高い文章で、このくだりを読んだときには思わず泣いてしまいました。
森本:僕にとって、それはどこまでも個人の物語なんですよね。でも、母とのエピソードはたしかに僕の信仰とつながっているのですが、ある意味で後付けとも言えます。
東畑:後付けなんですか?
森本:うん。そうなっていたことに後になって気がついた。現実はそんなものです。
母のエピソードと自分の物語がつながったのは50歳ぐらいのときです。きっかけは、当時流行していた「ラストレクチャー」でした。ラストレクチャーというのは、ガンで余命宣告を受けたランディ・パウシュというカーネギーメロン大学の教授が、人生を振り返って学生たちに最後の講義を行ったものです。彼は実際にその後まもなく亡くなるのですが、それから「死を目前にしたら何を語るか」という設定で講義をするのが一般的になって、ひとつのジャンルになりました。
僕も学生に依頼されて大学祭でラストレクチャーをやったのですが、そのとき初めて自分の人生を振り返りました。そうすると、やっぱり出てくるのは物語なの。ラストレクチャーって、みんな自分の学問的業績とかじゃなくて人生全体を語るんです。生まれたときからどういうふうに生きてきて今の自分につながったのかを話すから、いきおいみんな物語になっちゃうんですね。ちょうどその頃、母の再発見が重なったので、僕もこのラストレクチャーを通して、人生がどのように展開してきて今の自分に至るのかを発見したというわけです。
諦めたあとに残るもの
東畑:小説のようなフィクションじゃないのに、僕らの人生でも、自分を貫く物語が見つかっていくのが不思議です。そこで起きることは、ある種の象徴です。森本さんの場合、母が祈ってくれていたということと、神が後押ししてくれていることが重なっていく。僕は心理学者なので、これを人間の心の象徴機能として捉えてしまうのですが、いかがでしょうか。
森本:ええ、「象徴」って政治でも文学でも芸術でもよく使われますが、実は本質的に宗教的な行為なんです。見えないものを見えるもので代用表現するから。そして、それは人間だけがもつ機能です。壁を緑のペンキで塗ったからといって、それを森だと思う動物はいない。だから宗教も人間に固有の営為です。
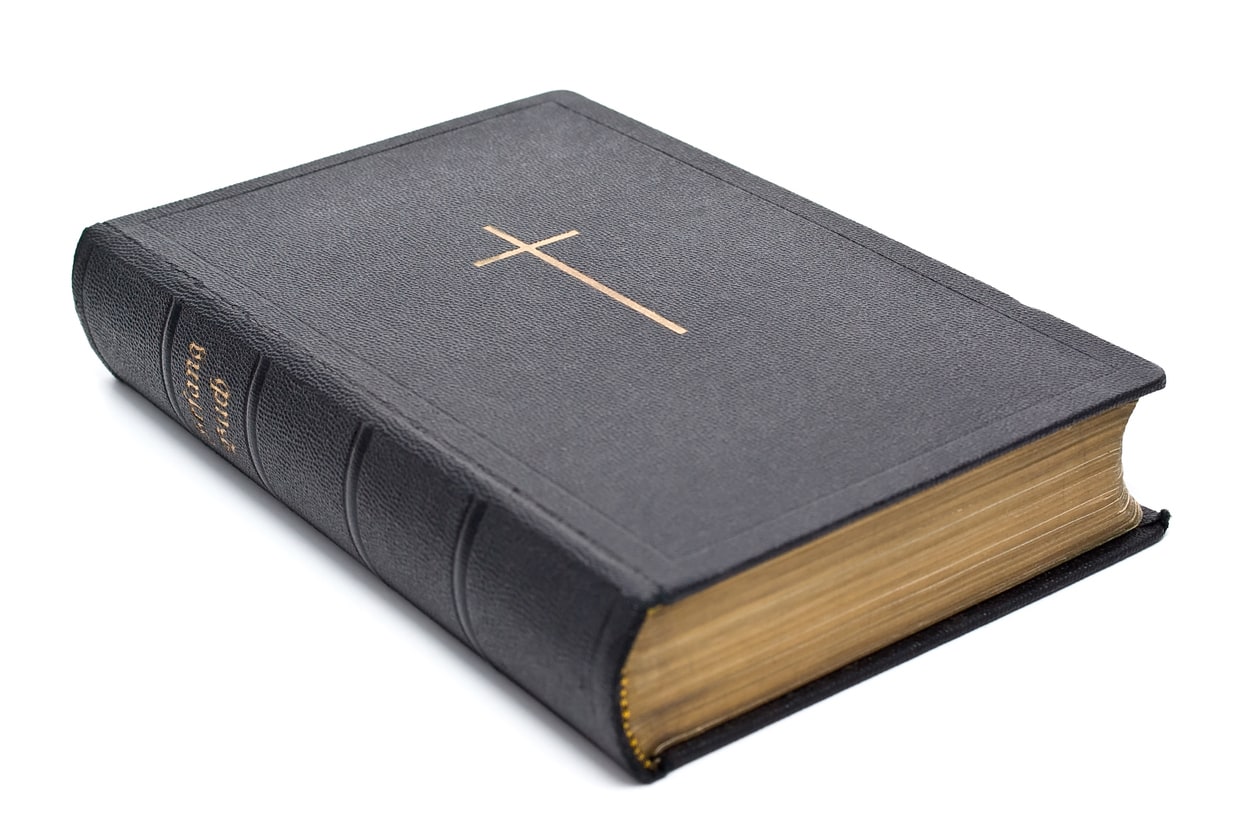
今の僕からすると、母の祈りは「神さまに与えられた人生の種」だったのだろうと思います。誰でもそうなのでしょうが、人生の種って自分でも気がつかないうちに胚胎して育っていって、あるときぱっと開花する。でも、その種は途中で育たなくなってしまうこともあるんです。なぜなら、人間にはいろんな可能性があるから。そのなかの一つを選ぶことは、他のものを選ばないということです。選ぶといっても、常に自分で意識して選んでいるわけではない。でもどこか内にあるものが自分を促して、何となくそういう道を歩き始める。そして気がついたら、それが自分の本質をいちばんよく実現していた、ということなのだろうと思います。本の中では、それを「運命の成就」と書きました。自分が選んだことなのだけれど、同時に自分の内側から自然と育っていったもの。その重なりがあると、人は深い充足感を覚えます。
東畑:人は人生のなかでやむにやまれずいろんなことを諦めていくんだと思うんです。「こうなりたかったのに、それができなかった」と、いろんな可能性を断念し続け、それでも何かが自分に残されている。それが消極的なものではなく、必然だったと思えるときに物語や文学性が立ち上がってくる。
森本:昔はよく「おじいちゃんが酔っ払うと必ずこの話になる」なんていうことがありましたよね。周りの人はうんざりしてるし、実話かどうかもわからないんだけど、それはその人が自分の人生を物語的に総括しているのであって、それがあったから今の自分があるんだ、という自己確認の作業なのだろうと思います。その中には嬉しかったことだけでなく、諦めや後悔もきっと含まれているでしょう。でもそうやって人はようやく自分の人生と折り合いをつける。しょうがない、もうこれでやっていくしかないと肚をくくる。
東畑:『魂の教育』に、自分の苗字も名前も嫌いだけど、「もし嫌いだからといってすべてを取り替えてしまったら、それでもわたしはわたしであり続けることができるのだろうか」とありました。面白いですよね。名前って、自分で選んだものではないじゃないですか。
森本:与えられたものですよね。その与えられたところに、親の気持ちが入っている。それが自分の人生とクロスしたとき、大きな何かとつながっていると感じる。現代人って、こういう「所与」の感覚が希薄になっていると思います。何でも自分の力でゲットしてこよう、ともがき続けているというか。でもだんだん与えられたものを受け入れる気になる。それで「神さまありがとう」になるんです。結局、単に歳を取ったってことかな。
続きの対談第二回〈毒にもなれば薬にもなる…人間にとって根源的な「何かを信じる」とは一体どういうことなのか〉では反知性主義や陰謀論に触れながら、良い物語と悪い物語の違いや、信じることの価値について、二人が語り合います。




