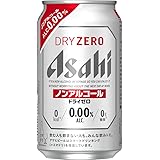2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。
しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。
2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。
日本酒の代表的な産地として知られる、兵庫県神戸市灘区から西宮にかけての「灘」の地。今回は、なぜ、灘が酒造りに向いているのかを見ていきます。
*本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。
六甲おろしが、酒造りに最適な低温をつくる
前回の記事でご紹介した「寒造り」は神戸市から西宮市にまたがる沿岸地域、灘(なだ)より起こりました。東から今津郷(いまづごう) 、西宮郷(にしのみやご)、魚崎郷(うおざきごう)、御影郷(みかげごう)、西郷(にしごう)の地区を合わせた 一帯の酒造地を灘五郷(なだごごう)とよびます。灘における寒仕込みと生酛造り(『最新 日本酒の科学』の第5章で詳述しています)が、日本酒の品質を牽引してきました。

昔は冬至酛(とうじもと)といって、冬至(旧暦では11月の中旬:新暦では12月下旬)の日に一気に酒母 (醪)を造りました。ほかにも仕込み過程では何度も冷やす作業(冷まし)をしなければならないのですが、冷蔵設備のない時代は外気に頼るしかありませんでした。
灘では六甲山から身を切るような北風(六甲おろし)が吹きます。酒蔵はその六甲おろしが入るよう、北向きに窓があります。日本酒を仕込む際には、とにかく醪(もろみ)を冷やすことに気を遣います。寒風に恵まれた灘にある私どもの酒蔵でさえ、とくに生酛造りとなると、仕込み後5〜6℃ にまで冷やして数日間置きます。製氷機が登場してから、作業がずいぶん楽になったと聞いています。
(高橋俊成氏)

気温が下がらない南九州では、焼酎づくりが盛ん
宮崎県や鹿児島県の居酒屋で「お酒をください」と注文すると、たいていは焼酎が出てくるそうです。実際、南九州の蔵元はほとんどが焼酎メーカーです(焼酎メーカーは宮崎県36軒、鹿児島県にじつに111軒ありますが、清酒の蔵元はそれぞれ2軒にとどまります)。なぜでしょうか。
理由は、南九州は温暖な気候のため、冬でも、寒造りができるほどの気温には下がりにくいからです。
「清酒醸造では低温で発酵を行います。気温があまり下がらない南九州では、雑菌に汚染されやすく、清酒造りはむずかしかったからです。一方、焼酎酵母は高温に強い。つまり焼酎造りのほうが南九州の土地柄に合っていたということでしょう」
(独立行政法人酒類総合研究所主任研究員・金井宗良氏)

蒸留酒の焼酎に比べて、醸造酒である清酒は多様な成分を含んでいるので味わいが多彩で深い半面、酒質が劣化しやすく、製品管理上も低温発酵のほうが望ましいのです。焼酎は蒸留するため高温での発酵でも酒質への影響は小さいですが、醪の温度が高いと、雑菌は繁殖しやすくなります。
こうした理由で、南九州では昔から清酒よりも焼酎が造られてきました。もちろん、温度調節機能や空調設備などが発達した現代では、南九州にも評判のよい清酒の日本酒の酒蔵がいくつもあります。
*「南九州では昔から焼酎が造られてきました」参考記事:どちらが甲類でどちらが乙類?「本格焼酎」ってなに? さまざまな「焼酎」の違い、説明できますか(鮫島 吉廣・髙峯 和則)
「天与の霊水」と呼ばれた宮水
全国各地の酒どころを訪ねると、酒蔵によっては仕込み水を飲めるところがあります。なかには敷地内の井戸や湧水の取水場が開放されている場所もあります。ところが、日本三大酒どころ である灘の酒蔵を訪ねても、敷地の中にも外にもにそういった一角は見当たりません。
実は灘の酒屋(蔵元)のほとんどは、西宮市にある宮水井戸場にそれぞれ独自の井戸を所有していて、毎日タンクローリーで汲みに行っています
(高橋俊成氏)
「宮水」とは「西宮の水」の略称で、灘の酒を一大ブランドにのしあげた仕込み水として知られています。
大阪と神戸を結ぶ国道43号線のすぐ南側、海岸から1kmほど内陸に入った、西宮神社 の南東に、灘の酒蔵が各自所有(あるいは共有)している宮水井戸が集中している場所があります。ここには複数の伏流水が流れ込み、わずか数百m四方という限られた範囲にだけ水が湧き出ています。
現在、この場所には70本あまりの浅井戸が掘られており、その深さはわずか2〜5m程度だそうです。
宮水の歴史…あまりの質の良さに販売業者まで出現
その歴史は1840(天保11)年にさかのぼります。 五郷の西宮郷(現・西宮市)と魚崎郷(現・神戸市)に酒蔵を構えていた山邑家(やまむらけ。現・櫻正宗)の6代目・山邑太左衛門は、西宮郷で醸したほうが魚崎郷のものより、よい出来になることを不思議に思いました。
そこで杜氏を替えたり同じ米を使ったりなど試みた末に、仕込み水の違いに気がつきました。西宮郷で使っている水を船で運んで魚崎郷で醸造したところ、西宮郷で造る酒と同等の出来映えになったというのです。こうして宮水のよさが知れると、西宮に井戸場を持たない酒蔵に宮水を売る「水屋」まで出現したといいます。
当時、新酒は夏を越すと味が落ちるのが一般的でした。それが、宮水で仕込んだものはほどよく熟成が進み、味もまろやかになる「秋晴れ」「秋栄え」となり、好評を博したということです。
宮水は鉄分がきわめて少ない反面、酵母や菌などの微生物の増殖に欠かせないカルシウム、カリウム、マグネシウム、リンを豊富に含んでいます。なかでもリンの含有量が多く、さらに海に近い土地柄ゆえに含まれる適度な塩分も、酵母の発酵を助ける要因となっています。
花崗岩の砂礫層が濾した宮水
ところで、「天与の霊水」と呼ばれた宮水は、ミネラルウォーターの水源としても知られる六甲山系を源流の一つとする伏流水です。ミネラルウォーターとしての硬度は37。まろやかな軟水です。一方、宮水の硬度は180程度。同じ水源でありながら、宮水としての水質の違いはどの ように生成されるのでしょうか。
宮水は、井戸にいたるまでに、風化堆積した花崗岩を主とした砂礫層の岩盤*を流れた3つの伏流水が混じり合います。そのうちの2つの伏流水はかつて海だった地層を通るため、貝殻などが涵養源(かんようげん)ともなって、まれに見る仕込み水に適した水質になるので はないかと考えられています。
現代の醸造技術であれば、ミネラル分が少ない水でも、質の高い日本酒を造ることができます。それでも、宮水井戸を所有している蔵元にとって、その価値は変わりません。当蔵でもかわらず宮水を大切に使っています。
(高橋俊成氏)
*「宮水をつくる六甲山系の地質」関西地方を中心に西日本に特徴的な花崗岩についての参考記事:「銀閣寺の庭が白い」のには理由があった…!「石」が人々の心にも影響するという「納得の理由」(藤岡 換太郎)
仕込み水を守る取り組み
「日本は水に恵まれた国」とはいっても、都市化や自然災害などの影響で地下水の水脈や水質が 変動する懸念はつきものです。どの酒蔵も、仕込み水の水質が保たれているかどうか気を配っているはずです。
たとえば、人口密集地の灘や伏見の酒蔵の多くが、いまも銘酒を醸している背景には、酒造りの水を守るために地道に続けている活動があるからなのです。

灘では1954年、地元の酒蔵が中心になって宮水保存調査会を発足。いまも年2回の定期的調査を欠かしません。阪神高速道路施工の際には、酒蔵が集まっている地域では地下水にできるだけ影響をおよぼさないよう、橋脚の間隔をほかの地域より長くして橋脚の数を減らす工法を要望し、実現しています。2017年には、宮水を守っていくために宮水保全条例が制定されました。
桃山御陵からの伏流水を仕込み水とする京都・伏見の酒蔵でも、すでに1928年(昭和3年)、同地区の地下水の調査を実施。同時期に桃山丘陵に地下鉄計画(現在の近鉄京都線の桃山御陵前駅近辺の区間)が持ち上がった際には、高架式に変更する要望を出し、認められました。

*
次回より、ユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」について、杜氏たちが築きあげてきた、驚きの技について具体的に紹介していきましょう。
最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技
日本酒再発見! 「甘口」「辛口」の基準とは?
「冷や」とは「冷やした酒」のこと?
燗酒に合う酒は甘口か辛口か? 樽酒が脂っこい料理に適しているのはなぜ?
ユネスコ無形文化遺産に登録「伝統的酒造り」。水と米から造られ、かくもバラエティ豊かで芳醇な味を持つ日本酒を、科学の視点から迫る…! 日本酒をとことん知り尽くすための1冊。