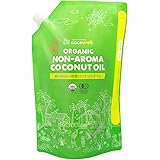文筆家としてエッセイや絵本翻訳、ナレーションなど多彩な才能を発揮している内田也哉子さんとハーバード大学医学部の准教授で小児精神科医の内田舞さん。2024年5月に真宗大谷派名古屋別院が企画したYouTube『人生講座』の座談会で出会い、瞬く間に意気投合したといいます。
「也哉子さんの育ってきた環境や物事に対する考え方には、似ているところや共感出来るお話がたくさんありました。特に、樹木希林さんから也哉子さんが受け継ぎ、大切にされている言葉や考え方は、なるほどと思うものばかりで、子育てだけでなく、自分自身どう生きるのか、ということを考えさせてくれました」
こう語るのは、新刊『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと 』が発売になったばかりの内田舞さんだ。新刊の帯には内田也哉子さんの推薦文も掲載されています。
『人生講座』の対談を記事化し、5回の前後編で掲載してきたこの短期連載は今回で最終回です。第5回では、子どもに物事を教えるときに、ご褒美や罰則方式は有効なのか? 多くの親が考える子育ての悩みについて、お二人の経験とともにお話しいただきます。
※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。
ご褒美と罰則、どちらが有効?
内田也哉子(以下、也哉子):アメリカでは、子どもが悪いことをしたときに、「Grounded(外出禁止)」などの「罰」というか、ペナルティを与えることもあるようですが、そういった伝え方は子どものメンタルや脳にどのような効果があるのですか?
内田舞(以下、舞):これは個人差があると思います。研究という視点だけでみると、「罰則とご褒美はそれほど効果がない」というエビデンスがあります。
也哉子:そうなると、やっぱり会話で子どもに理解してもらう? なぜそれが良くないのかを根気よく語り合うということでしょうか?
舞:そうですね。子どもの罰則やご褒美に関する研究は、何度も行われています。ですが、常に効果がないという結果が出ます。といっても、これはあくまでも研究レベルの話で、我が家でも子どもにご褒美あげることはありますし、ひどいものではないですが罰則的なことを与えるときもあります。
最近聞いたご褒美に関する研究で、ちょっとおもしろいものがありました。パズルを子どもたちにやらせて、「完成させたらご褒美ありですよ」と告げてパズルを始めたグループと、ただパズルをやらせただけのグループに分けて実験してすると、ご褒美ありのグループはみんな簡単なパズルばかりを選んでやっていたそうです。

也哉子:それは、早くクリアしてご褒美がほしいからですね。
クリアすることだけがすべてではない
舞:そうですね。ご褒美ありのグループは、「クリアできるものをやろう」という方向に向かっていったのですが、何も言われていないグループは、バラつきはあれど難しいパズルに時間をかけてチャレンジする子も結構いたそうです。ご褒美のすべてが悪いわけではないのですが、ご褒美ばかりが先行してしまうと、クリアすることだけが目標になってしまう場合もありますね。
夫がチェリストなので、我が家では夫が息子たちにチェロを教えています。彼は私よりも子どもの心を掴むのがとても上手です(笑)。そして、チェロのレッスンでもその力を発揮します。夫は「ひとつの曲を終わらせたら、次の曲へ、と次々進んでいくことばかりを感じさせないようにレッスンしたい」と言っていたんですね。次の曲に行きたい、という気持ちがばかり先行してしまうと、曲を終わらせる意識で音符を覚えるので、曲の意味を考えたり、この部分はもう少しこんなふうに弾きたいといった考えや思いがなくなってしまうと……。夫は長年音楽をやっていく中で、そんな現象を感じてきたそうです。
だから、達成ということよりも毎日とにかく弾いていく。「これをやる」「ここまでやった」で何かが起きるわけではなく、すべてを「continuous(連続的)」なものと捉えて意識していると話してくれました。
也哉子:チェロのレッスンだけでなく、人生のテーマにも通ずるような素晴らしいお話ですね。私も今起きたことだけに集約するのではなく、長い時間をかけて息子と対話をしながら、本当に何が大切なのかを押しつけずに、引き出すように話したいと思いました。でも、子どもに本音を吐露させるのは、技術が必要ですね。
舞:アメリカの10代は、「コントロールされること」を一番嫌います(笑)。それをちょっと逆手にとって、「あなたが長時間スマホを使い続けるのは、このアプリ会社の商業的な目的のために『もっと使いたい』と思わせるアルゴリズムや仕掛けがたくさん入っていて、そういった大企業に、あなたはコントロールされている可能性がある。大企業にもいいところもあるけれど、子どもたちまでコントロールして利用するアメリカの資本主義社会に私は怒っているのよ!」と親が言ったら、「自分はコントロールなんてされないぞ!」とスマホのつきあい方について、自分自身で考えるようになったという話を聞いたことがあります。
正解はひとつではない
也哉子:外に敵を作るのね、家の中じゃなくてね。やってみます。アメと鞭というか……、罰とご褒美は本質的な効果があるわけではないと知ることができてよかったです。
舞:そうですね。でも、最近子犬を飼い始めたのですが、子犬はやっぱりご褒美が一番効果的でした(笑)。
也哉子:やはり人と犬とでは異なるのですね。
舞:我が家は道路と庭の間に柵がないんです。急に飛び出して交通事故に遭っては大変なので、子犬に「ここから出ちゃダメだよ」とどうやって教えようと思って。「ここから出ちゃダメだよ」と何度も言い続けたのですが、対話してもダメだったんですよね。なので、道路まで出なかったときに「やった、やった!」と喜びを伝えながら、おいしいエサやベーコンをあげますよ、とやっていたら出なくなりました。

也哉子:生物学的に人間と犬は違うかもしれないけど、まったく違うのが、不思議ですね。これは長い、長い道のりの研究が必要ですね。
舞:子犬を迎えたのが、半年ぐらい前だったのですが、どうしたものかと浅い経験の中で、やっぱりご褒美か、アメと鞭も必要なんだなと学びました。人間と犬は生物学的には違いますが、人の育児も犬の育児も答えはやっぱり模索していくしかないんです。さらに”道路に飛び出る”などの安全にかかわることは、待ったなしですよね。ですから飴と鞭のように、早急にはっきりとした良し悪しがわかる形で教えなければならない場合もあると思います。
也哉子:なるほど、ひとつではないですよね。肝に銘じます。
舞:一緒に頑張っていきましょう。
也哉子:子育てをしていると本当にいろいろありますね。でも、子育てのお話で伺っていても、子どもに対する対応だけでなく、他者とどう付き合うかということのヒントにも応用できると感じます。今の時代、本当にさまざまなストレスがあって、そこから逃げようと思うと引きこもりたくなる自分もいたりしますが、やっぱり外に一歩出て、一人でも二人でも人と出会って、新たな違う角度の考え方を知る・触れるということは、いろんな扉が開きますね。今日も舞さんとお話してそんなことを感じました。
◇第5回後編『内田舞×内田也哉子「不登校の小中学生が34万人超」日本で今できること』では、内田舞さんが2024年7月に刊行した『うつを生きる 精神科医と患者の対話』のお話から、大人のうつと子どものうつの違いなど、メンタルケアに関してお伝えする。