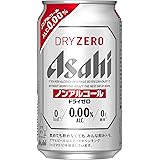落ち着いた「アイドル声優」ブーム
2020年以降、『鬼滅の刃』をきっかけに空前のアニメブームが巻き起こり、声優という職業の存在感は飛躍的に高まった。
人気作の出演声優たちがテレビ番組に登場する機会も増え、『踊る!さんま御殿!!』での「声優祭り」をはじめ、『半沢直樹』『おげんさんといっしょ』で俳優としても注目を集めた宮野真守、『ドラえもん』ジャイアン役・木村昴のバラエティ進出など、その活躍の幅は広がり続けている。
今年に入ってからは、朝ドラ『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』といった国民的コンテンツへの出演も目立ち、俳優として脚光を浴びる場面が増えてきた。かつてのような「声優=裏方」という認識は過去のものとなりつつある。

だが、その一方で、「アイドル声優」と呼ばれた存在に象徴される2010年代までの熱狂は、確実に落ち着きを見せている。
2000年代から2010年代にかけては、CDデビュー、写真集、武道館ライブ、冠バラエティ番組など、声優が“スター”として脚光を浴びた時代だった。ときに熱狂的なファンの言動がネットミーム化するほどの盛り上がりを見せ、声優はアニメキャラの“中の人”から“憧れの存在”へと進化を遂げた。
だが今、その熱狂は静かに冷めつつある。CDの売上や写真集の部数は減少傾向で、ライブやイベントに訪れるファンの年齢層は明確に上がっている。
そう、ここ数年で声優ブームを取り巻く環境は大きく変化した。いま、声優という職業はどこへ向かっているのだろうか。
VTuberの急激な台頭
「気づいたら、声優のCDをまったく買わなくなっていたんです」
そう語るのは、かつて“推し声優”の写真集を何冊も買い、武道館ライブにも通ったという都内在住の30代男性だ。数年前まで、彼の週末はライブやリリースイベントで埋まっていた。当時はアニメのキャラ以上に“中の人”への熱量が高かった。だが、いまは違う。
「たぶん、VTuberに“同じ感情”を持ってしまったんです」
VTuberの台頭によって「声+キャラクター+ライブ性」を持つ存在が新たに登場したことで、“二次元の向こう側の人間味”は、よりリアルタイムで会える存在に代わりつつある。

「VTuberは生配信で毎日話してくれるし、ファンの名前を読んでくれる。スパチャで応援すれば反応が返ってくる。リアルに “生活のそば”にいてくれる実感があります」
ライブ配信文化が普及し、推しと“つながる“ハードルは劇的に下がった。VTuberもドラマCDやライブに出演し、グッズを出し、ファンとの結びつきをより強固にしている。
いまや声優として名を上げた後にVTuberへの転身を果たす人や、声優志望者がまずVとして活動を始めるケースもある。
“アイドル声優”という概念が必要なくなった
「“顔出ししたくないから声優になりたい”という声優志望者の子の一部が、今はVTuberに流れているのかもしれません」
自身も声優として20年近いキャリアを持ち、事務所「トイプリッズ」の代表を務める古川小百合さんはこう話す。
「一時期のアイドル声優ブームは明らかに落ち着いたといえますね。コロナ禍で長期間ライブやイベントができなくなったのは、大きな影響があったと思います。会えないままの3年間は長すぎます。
一方で、VTuberは家から応援できる。見た目は年を取りませんし、正体が分からないからこそ、ファンは余計な情報を知らなくてすむメリットもあります。
ほかにもTikTokなど色々と表現の場が生まれて、直接顔出ししなくても人柄や喋りだけで勝負できる環境が整いました。役者としてではなく、自己表現のひとつの場として声優という職業を目指していた子たちが、自分に合う表現を求めて、色々なジャンルに分岐していったんだと思います」

かつては、推しの声優に恋人の存在が発覚するとネットが炎上騒ぎになったものだが、そうした事例もめっきり減った。
「ライトに楽しむ方も多くなり、声優ファンの年齢層も本当に幅広くなりました。何より、コンテンツそのものに“アイドルもの”が増えた。『BanG Dream!(バンドリ)』もそうですし、『ラブライブ』『アイマス』もそう。
キャラクターを応援するというゲーム性が最も重要で、生身の人間をアイドルのように推す“アイドル声優”という概念自体が、今の時代ではもう必要なくなったのかもしれませんね」
次世代スターの不在
さらに、声優業界は一つの大きな課題を抱えている。声優には常に“次のスター”が登場していたはずだった。
1980年代には神谷明や古谷徹、1990年代には林原めぐみや緑川光。2000年代は堀江由衣や田村ゆかり、水樹奈々、宮野真守。2010年代に入ると花澤香菜や水瀬いのり──だが、ここ数年「次世代スターが見当たらない」といった声が増えている。
その理由の一つが、若手声優が“挑戦できる場”が少ないということだろう。登竜門だった深夜アニメの主役ポジションも、既に名の知られた中堅~ベテラン声優で埋まるケースが増えている。

「キャスティング時にプロフィールが真っ白な人と、ある程度作品に出ている人であれば、それは後者を選びますよね。何より、新人の先輩にあたる中堅から大御所の方も20分前にはスタジオに入られているほど、非常に仕事に真摯な方が多い。
そして常になにか新しい表現ができないかと向上心を持って研究されている。こうした中に新人が割って入るのはハードルが高いと思います」
実際、40~50代のベテラン声優たちもキャリアのピークを維持している。神谷浩史、杉田智和、石田彰、沢城みゆき、坂本真綾…みな第一線で活躍し続けているスターばかりだ。
AI音声は手強いライバルだが…
そのうえ新たな“ライバル”として現れたのが、AI音声の存在だ。NHKニュースや鉄道の駅構内のアナウンス、自治体のナレーションなどで、AIたちは次々と稼働し始めている。
「AIはどんなに長い原稿でも息継ぎせず読めるし、調整次第ではすごく自然になる。正直、レベルはすごく高いです。とあるニュース番組は声優のナレーションと遜色ない印象です」

人間にとって手強い相手だが、現場でプロが必要とされる理由はまだまだある。
「制作側からすると、その場で柔軟に対応できて、1人で何種類も声質を持っている声優の存在は助かるそうです。現状のAIは既存のボーカロイドと同じく、編集者の能力に頼る部分が大きい。
人間の細やかな感情表現を正確に出力するのは、その編集者にも声優と同じレベルの演技力や表現力が必要で、非常に時間がかかって大変なんです。であれば、制作と声優それぞれが現場でコミュニケーションを取りながら収録するほうがスムーズですし、コスパもいい。新たな発想が生まれるのも人間ならではです」
・・・・・・
【つづきを読む】『夢は武道館、でも現実は“数万分の1”の壁…《アイドル声優ブーム》が去った時代に声優を目指す「若者たちの本音」』