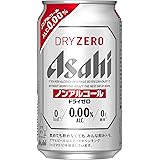『青い花』『放浪息子』などで知られる漫画家の志村貴子さんが、新作『そういう家の子の話』(小学館)で宗教2世の日常を描いている。
“ふつうの家”に生まれたかった——。同じ宗教を信仰する家庭に育った幼馴染み、恵麻、浩市、沙知子の3人が28歳で迎えた人生の岐路に立ち、それぞれが「家の事情」を抱えながら、仕事や結婚といった人生の選択と向き合う群像劇だ。
志村さんは2023年、自身も宗教2世(厳密には3世)であることを公表している。本作を描くまでの逡巡と、当時者として抱えてきた想いについて率直に語ってくれた。
周りの人に知られたくないけど、ずっと誰かに聞いてほしかった
——『そういう家の子の話』は、あくまでフィクションではありながら志村さんご自身の経験も踏まえて創り上げた作品だと伺っていますが、この作品を描くことになったきっかけを教えてください。

志村貴子(以下、志村):自分の中でずっと、家の宗教のことを周りの人に知られたくないと思う一方で、誰かに聞いてほしいという気持ちもあったんです。
実はこれまでの作品にも、そのものズバリを描くのではなく、他人事のように描いてきたことはちょこちょこありました。最初が『青い花』で、登場人物のお母さんが宗教に傾倒していく話。『淡島百景』でも、『そういう家の子の話』のプロトタイプのようなエピソードを描いています。大久保(あさ美)さんという宗教2世のキャラが登場するんですが、彼女は自分の魂の叫びを体現したような存在でした。
——宗教や宗教2世のことを描きたいという思いは、ずっとあったんですね。漫画の連載が始まる1年前、2023年3月にSNSで宗教2世であることを初めて公表されています。菊池真理子さんの『「神様」のいる家で育ちました〜宗教2世な私たち〜』を読んだことがきっかけだったそうですね。
志村:はい、7話目が菊池さん自身のお話で、我が家と同じ宗教だったんです。私も菊池さんのように、同じ立場の人に「一人ではないよ」と伝えられたら良いなと思いました。
noteにも書いていますが、私は公表するまで50年近い時を要して、家族に「ごめん、もう本当に無理です」と伝えられたのも30過ぎでした。新興宗教を信仰する家族を否定されたくないし、したくないという思いで、周囲に隠したり、仲の良い友達にも明かせないでいました。そんな自分の過去を恥じるような感情がずっとありました。

――隠していたことを恥じていた?
志村:はい。私の家族も含め、これまで出会った信者の方々は基本的に皆、善良な人々なんです。でも、自分は彼らと足並みを揃えられない。それが後ろ暗さのようなものになっていました。一方で、そういうしがらみのようなものがない状況への憧れもありました。
そんな複雑な思いをそのままブログで吐き出したことで、自分自身、少し楽になりました。でも、やっぱり漫画家としては、漫画として消化させたいという欲求も起こってきたんです。
宗教2世の物語をニュートラルに描いた理由
——今、世の中に出ている宗教2世の方の体験談は、どちらかというと自身の苦悩を吐き出す告発的なものが多いですが、志村さんは出来事をニュートラルに、淡々と描いていて、これまでにないアプローチだと感じました。

志村: 苦しまれた方の気持ちも分かるんですが、自分はそちらにあまり舵を切りたくなかった。ネガティブな感情もたくさん生まれることはありましたが、そういう悪い思い出ばかりじゃないんです。家族を嫌いになりきれない呪いのようなものもあるし、センセーショナルに描くことで、自分の信仰心を否定されがちな昨今の風潮に苦しむ人たちをさらに追い込みたくないという気持ちもありました。
――群像劇の形をとられたのは、そういった狙いからですか。
志村:そうですね。多様で複雑な感情を描く上で、群像劇がやりやすかったんです。私は宗教2世のドキュメンタリーを描きたいわけでもないし、特定の宗教の告発をしたいわけでもありません。実際、『そういう家の子の話』も我が家の宗教とはまた別の物語になっていますし、全く知らない人が、「宗教をやっているお家ってこんな感じかな」となんとなく受け止めてもらえたらと思っています。
周囲が宗教に寛容だった子ども時代
——本作には、信者の子どもたちが集まる子ども会の様子など、楽しそうな場面も描かれていますね。

志村:「だからこそ罪深い」という意見も分かるんです。当時、作品に登場する3人の回想シーンのような年齢(小学生)の時には、私も全然疑問を抱かずに楽しく過ごしていました。
周りにいろんな宗教の家の方がいたけれど、当時は大人にも子どもにも、「あの家って~」みたいな視点がなかった。「○○ちゃん家は、なんかそういう決まりがあるらしいよ」と、そういうものとして受け止めるような感じでした。無宗教のお家の親御さんからしたら、本当は複雑な思いがあったのかもしれませんが、そういう大人の思惑を一切見せない環境だったんです。
——作品の中にも宗教上の理由から体育の授業を受けられない子が登場していますが、振り返ると、身近に結構いたなと思いました。体育の授業を受けられない子やマラソン大会に出られない子などをみんなで「いいなあ」と羨ましがった経験は私にもあります。
志村:クラスメイトが家に親御さんと一緒に勧誘に来るという話を作品に描きましたけど、あれも実話で。違う宗教の家の子がクラスにいたんです。私の母親も悪い顔ができず、私も「あ、○○ちゃん!」という感じで、親越しに子ども同士で手を振ったりしていたんですよね(笑)。

――そういう宗教上の理由があることをみんな知っていて、それでもその子が人気者で友達が多いという描写も「あるあるだな」と思いました。
志村:子どもって、実際そうなんですよ。子どもにとっては(宗教2世ということは)どうでもいいというか、たぶんそんなに関心もない。今思えば、ちょっと他人と違うことでいじめたり、「あいつは何かおかしい」となったりする社会なのに、宗教に関してはみんななぜか無関心だったのは不思議な光景でした。
「小さな違和感」が作品づくりに生かされている
——志村さんはいつも作品の中で、そういった人間の微妙な感情や空気感をとても繊細に描かれますが、子どもの頃の体験が作品づくりに影響しているのでしょうか?
志村:それはあると思います。本当に些細なことなんだけど、なんとなく小骨のように刺さっている感覚が自分の中にあって。でも、それがふとしたきっかけで思い出された時に、こういう仕事の場合、モヤモヤした感情や経験も、漫画という形に起こせると思ったら、覚えている一つ一つの事象も無駄ではないだろうと思えるようになりました。

——志村さんご自身が宗教2世という境遇や家庭環境に違和感を持たれたきっかけは?
志村:うちのやっていることがどこの家でもやっていることじゃないなというのは、小学校高学年ぐらいからなんとなく感じていました。子どもの時は受け入れていたけれど、やっぱり恥ずかしいと思ったのが、父の「勤行」(仏前で一定の時間を決めて行う読経や礼拝などのこと)でした。
父は公務員で、すごくきちっとした人だったんですが、日曜日の夕方5時になるときっかり勤行を始めるんです。一番広い仏間で友達と遊んでいると、5時前に「じゃあそろそろ帰る」という感じでみんな帰っていくんですね。私も5時になるとお父さんが勤行を始めるから、友達に見られたくないなという気持ちがありました。でもある時、一人だけ「私まだ大丈夫だから」と言って、帰らない子がいたんです。
――ああ……帰ってほしいのに、「私はまだ大丈夫」という子、いますね(苦笑)。
志村:そうなんですよ(苦笑)。父は気にせず勤行を始めるタイプなので、何とかその友達を帰したいと思い、「お父さんがこれから勤行始めるんだけど、お父さんの声はでかいから、驚いちゃうかも」と言ったんです。すると、「大丈夫!」と言われてしまって(苦笑)。実際、勤行が始まっても友達は全然気にせず遊んでいるんです。私だけがハラハラしていて、父もその友達も何とも思っていないんですよね。そういうところはありがたいと言えばありがたいんですけど、私だけが気が気じゃなかった。
——学校でもそういった違和感を覚えることはありましたか?
志村:中学に入ると、学校の先生とかが私の家の宗教を知って「ムムッ」と一瞬なる感じがありました。書道の授業で家から持ってきた新聞を下敷き代わりに使っていたんですが、それを見つけた先生に「おまえんちって、〇〇(宗教団体)なの?」と聞かれて、「はい」と答えると、何か思うところがある感じでした。
直接何か言われるわけではないけれど、要所要所で周りが感じ取る違和感のようなものを、自分も感じ取るということがありました。そういう経験も、今の作品づくりに生かされているのかもしれません。
◇続く後編【「家族のグループLINEで私以外は幸せそう」漫画家・志村貴子が「宗教2世」として抱える孤独】では、初めて家族に「宗教に対する拒絶」を示したときのエピソードとともに、志村さんが考える「宗教との理想の距離感」について語ってもらった。