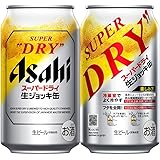この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。
日本人は移動しなくなったのか? 人生は移動距離で決まるのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか?
発売たちまち4刷重版が決まった話題書『 移動と階級 』では、通勤・通学、買い物、旅行といった日常生活から、移民・難民や気候危機など地球規模の大問題まで、誰もが関係する「移動」から見えてくる〈分断・格差・不平等〉の実態に迫っている。
(本記事は、伊藤将人『 移動と階級 』の一部を抜粋・編集しています)

6割以上の人が「移動の自由をめぐる差は存在する」と思っている
本書の主題の一つでもある「移動の自由」をめぐる差について、人々がどのように認識しているのかもみてみよう。
調査の結果、回答者の66.8%が「移動の自由をめぐる差は存在する」と認識していることがわかった。「わからない」と回答した人も16.0%いたため、「移動の自由をめぐる差は存在しない」と考えている人は17.2%ということになる。このことから、多くの人(と言ってよいだろう)は、現代日本社会には移動の自由をめぐる差が存在すると感じていることがみえてきた。
さらに、「移動の自由をめぐる差は自己責任か」と尋ねてみたところ、51.5%と半数以上がこの社会に存在する移動の自由をめぐる差は「自己責任」であると考えていることも明らかになった。つまり、「移動をめぐる自由には差があり、その差は自己責任である」という認識が日本社会の半分を覆っているというわけである。
移動の自由をめぐる認識をみていくと、ある調査結果が気になった。それが、「障害の有無」と「障害を有する家族の有無」の項目である(図表9)。

身体障害や精神障害を有していない人は64.6%が移動の自由をめぐる差は存在すると回答したのに対して、「精神障害がある人と同居している人」は78.1%、「身体障害がある人と同居している人」は75.5%、「自身が精神障害を有している人」は76.9%と、全体より10%ポイントほど高い結果となった。
興味深いのは、自身が精神障害や身体障害を有する回答者と比較して、同居する家族に精神障害や身体障害を有する人がいる人のほうが、移動の自由をめぐる差は存在すると回答している点である。移動の自由をめぐる差は、移動の困難をもたらす要因をかかえる可能性がある本人だけでなく、その家族にも移動をめぐる制限や、移動の自由の剥奪感を与えている可能性が示唆される。
本記事の引用元『 移動と階級 』では、意外と知らない「移動」をめぐる格差や不平等について、独自調査や人文社会科学の研究蓄積から実態に迫っている。

伊藤将人(いとう・まさと)
1996年生まれ。長野県出身。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。2019年長野大学環境ツーリズム学部卒業、2024年一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。戦後日本における地方移住政策史の研究で博士号を取得(社会学、一橋大学)。立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所客員研究員、NTT東日本地域循環型ミライ研究所客員研究員。地方移住や関係人口、観光など地域を超える人の移動に関する研究や、持続可能なまちづくりのための研究・実践に長年携わる。著書に『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社)がある。最新刊『移動と階級』(講談社現代新書)。