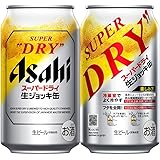ビールが美味しい季節がやってきました!
コクやキレ、さらには喉ごしの爽快さまでもが求められる。「勘と経験」に「最新の科学技術」を融合して日本のビール造りは世界に類を見ないほどの発展を遂げ、発泡酒や新ジャンルの開発へと進化を続けている。生きた酵母を使いこなすビール造りの真髄からビールがおいしくなる注ぎ方や世界各国の名ビールまで、知ればもっとビールが飲みたくなる話を多角的に解説!
ビールのおいしさのすべてがわかる!
7000年ものあいだ人類に愛されてきたビールは、最先端の科学を駆使して、
今も日々進化を続けている。その製造工程から家庭でおいしく飲むコツまで紹介!
※本記事は『カラー版 ビールの科学』(2018年刊行)を一部再編集の上、お送りいたします。
アルコールの効能を示す「ある曲線」
「アペリティフ」とよばれる食前酒を飲む習慣がなぜ存在するか、ご存じですか?
少量のアルコールを飲むことでリラックスでき、さらには胃の動きが活発になって食欲が増すからです。食事の始まりにお酒を飲むことは、理にかなっているといえます。
アルコールにはまた、善玉コレステロール(HDL)を増やすはたらきがあり、数多くの疫学調査が報告されています。血液凝固の抑制効果があることも認められており、最近の研究ではさらに、少量の飲酒にアルツハイマー病や他の認知症のリスクを下げる効果があることが、複数の疫学調査によって報告されています。
アルコール(エタノール)は日本薬局方にも収載されており、不安や気苦労などの不快な感情を抑制して陽気にする、鎮静や催眠効果などの多くの薬効が言及されています。一方、急性中毒や慢性中毒などの副作用についても、もちろん記載されています。
今からちょうど四半世紀前の1993年6月、ACSH(American Council on Science and Health:米国保健科学協議会)から、アルコールの摂取量と死亡率との関係を、複数の論文から総合的に解析した結果が発表されました。アルコールをまったく飲まない人に比べ、適量の飲酒をする人では死亡率が低くなる一方、過度の飲酒を行う人ではその摂取量に比例して死亡率が上昇するというものです。そのグラフの形から、「Jカーブ」とよばれています(図8─2)。

この結果はもちろん、もともと飲まない/飲めない人に飲酒を勧めるものではなく、あくまで過剰飲酒を戒め、適量飲酒を推奨するものです。
日本では、1990年に開始されて現在も追跡調査が続いている、全国14万人の地域住人を対象とした、さまざまな生活習慣(喫煙、飲酒、体格、食事・栄養と運動習慣、医療的・社会的・経済的な状況、女性の生理や出産など)と、がん・脳卒中・心臓病・Ⅱ型糖尿病・白内障・うつ病などのさまざまな疾病の発生との関連を明らかにするための「多目的コホート研究」(特定の集団を対象としたデータによる疫学的研究)が行われています(厚生労働省の研究班が実施)。
同研究におけるアルコールの摂取状況と健康との関係を見ると、全死亡率(疾病、不慮の事故なども含めた死亡率)、がんの死亡率などで、図8─2と同様のJカーブが得られています。男性では二日あたり日本酒を1合程度(ビールの場合は中瓶1本)飲むグループでは、飲まない人に比べ、死亡リスクが36%低く(相対危険度0・64)なりました。毎日1合程度飲むグループでは死亡リスクが13%低く、毎日2合程度では逆に4%上昇し、毎日4合程度の場合は32%上昇しました。
これらの結果から、飲酒量が多いと、量に比例して死亡率が高くなることは事実ですが、一方で、個人の体質に合った適量のアルコールは、健康にマイナスの影響を与えないともいえそうです。「少量(二日に1合から一日に1合程度)の飲酒は、むしろアルコールをまったく飲まないより健康によい可能性があり、それ以上は飲めば飲むほど死亡率、特にがんによる死亡率が高くなる」ということです。
右のコホート研究では、適度にお酒を飲むことの効果、最低週に2回は休肝日を設けるべきという、常識的な結論が導かれています。
アルコールには脳を麻痺させるはたらきがあり、特に大脳の理性や判断を司る大脳皮質の活動が低下し、抑えられていた大脳辺縁系(本能や感情を司る)の活動が活発になります。そのため、人はお酒を飲むと、上機嫌になったりします。度を過ぎることなく、個人の体質に合った適量を飲めば、リラックスし、ストレスから解放される効果が期待されるわけです。何よりビールの5000年ともいわれるその歴史が、その効用を物語っているのではないでしょうか。
アルコールはどう代謝されるか
アルコールを飲むと、約20%は胃から、残りの大部分は小腸から吸収されて、肝臓に運ばれます。吸収されたアルコールの一部は、分解されることなく肝静脈から心臓に達し、呼気や尿、汗からも排泄されますが、大部分のアルコールは肝臓で酸化されてアセトアルデヒドになり、さらに酢酸に代謝されて、最終的には二酸化炭素と水に分解されて体外に排出されます(図8─3)。

一般的に、大瓶1本分(633mL)のビールを飲むと、代謝されるのに約3時間かかるといわれています。ただし、あくまで目安にすぎず、お酒の強い人/弱い人によって、代謝速度は違ってきます。それでは、お酒に強い/弱いは、何が決めるのでしょうか?
その人自身がもともともっている「体質」と、「お酒の常飲量」に基づくアルコールの代謝速度の違いで、お酒に強いかどうかが左右されるのです。
肝臓におけるアルコールの代謝経路を、少し詳細に見てみましょう。
アルコールはまず、アルコール脱水素酵素(アルコールデヒドロゲナーゼ:ADH)によってアセトアルデヒドに酸化され、続いてアルデヒド脱水素酵素(アルデヒドデヒドロゲナーゼ:ALDH)によって酢酸に酸化されます。酢酸はさらに、ATPを介して最終的にはミトコンドリアで二酸化炭素と水に分解されます。
アルコールの中間代謝物であるアセトアルデヒドは、私たちの体にとって毒性が強く、大量にアルコールを飲むと分解が間に合わなくなって、頭痛や吐き気といった二日酔いの症状の原因となります。日本人の中でも、まったくお酒が飲めない人、飲んで顔が赤くなる人、飲んでも顔に出にくく二日酔いになりにくい人など、アルコールに対する反応は人によってさまざまです。アルコールの代謝速度は人種によっても違いますし、同じ日本人でも個人差があります。
体に有害なアセトアルデヒドを代謝する酵素(ALDH)には、少なくとも6種あるといわれており、その中でミトコンドリアに存在するALDH2が主な役割をはたしています。このALDH2の遺伝子には、活性型、低活性型、不活性型の3タイプがあり、どれをもっているかでお酒に強いかどうかが決まります。
白色人種はほとんどが活性型ですが、日本人のようなモンゴロイドは4割が低活性型、または不活性型です。日本人で調査した結果では、「活性型:低活性型:不活性型=58・1%:35・1%:6・7%」という比率でした。ALDH2活性の強くない人は、飲酒時に顔が紅潮する「オリエンタルフラッシング」とよばれる症状を呈します。
もともとアジア系民族、とりわけ日本人は欧米人やアフリカ人に比べてお酒に強くない人が多いようで、飲めない人は無理をしないほうがよいといえます。お酒に強い人も、体質的にアルコールをまったく受けつけない人がいることに留意しましょう。お酒の無理強いは絶対に禁物です。
また、低活性型の人も相当数いるということは、一気飲みや大量飲酒にも注意すべきであることを指し示しています。そして、活性型だからといって油断は大敵です。多量の飲酒を長期にわたって続けると慢性中毒症状を起こし(アルコール依存症)、肉体的にも精神的にも取り返しのつかない事態を招きかねません。