時間の罠が、真実を曇らせる…!?
「私が容疑者を見かけたのは〇時ちょうどです」
犯罪捜査ではこんな目撃証言が決定打になる場合がある。だが、もし目撃者の時計が実際より5分だけ進んでいたとしたら?
容疑者の犯行現場への立ち寄りを裏づけるはずだった供述は一転して、「その時刻その場に容疑者がいなかった」というアリバイの証拠に変わるかもしれない。時計のわずかな狂いは容赦なく過去の解釈に大きな影響を与える。
時間の罠は現代の犯罪捜査に限った話ではない。時計も、文字も存在しなかったはるか遠い昔、何千年も前の人類の営みを読み解こうとする考古学の世界でも同じ問題が立ちはだかる。
最古の土器は、何年前のものなのか
「最古の土器が出現した頃、日本列島では気候が温暖化しつつあったと少し前の考古学者は考えていました。落葉広葉樹林の森が広がり、そのおかげでたくさん手に入るようになったドングリなどの植物資源を煮炊きするために土器が発明されたのだろう、と。しかしそうではないことが近年分かってきました」
そう語るのは、「暴れる気候」研究プロジェクトの日本考古班の班長で、学習院女子大学教授の工藤雄一郎さんだ。工藤さんはこれまで日本列島の土器の出現や縄文人がどう植物を利用してきたかなどに注目して研究してきた。
縄文時代の幕開けは長らく5,000年前とも7,000年前とも言われてきたが、確たる証拠がなかった。ところが1959年、神奈川県の夏島貝塚で発掘された土器が、その常識をひっくり返す。撚糸文土器(よりいともんどき)と呼ばれるその土器が約9000年前のものであることが判明したのだ。土器の使用が縄文時代の定義であるため、この発見は縄文時代のはじまりを一気に数千年も遡らせたことになる。

この大転換を裏づけたのが炭素14年代法だ。生物が死んだ瞬間から放射性炭素(14C)が一定のスピードで減っていくという物理現象を手がかりに、その生物がいつ存在していたかを知る方法である。その方法を使い、当時最古と考えられていた撚糸文土器とともに出土した貝殻と炭化材を測定したのだ。
普通の時計(クオーツ式)の場合、一定の周期で振動する水晶を利用して電気信号を得て、電子回路で振動回数をカウントし、時間の単位に換え、「時刻」を出す。炭素14年代法が利用するのは炭素14の減り具合だが、これも一定のスピードで変化するという物理現象を利用している点では一種の時計と考えて差し支えない。
根本から揺さぶられ「後氷期適応論」
土器が約9000年前に生まれていたとすれば、氷期が終わった後に縄文時代がはじまったことになる。なぜなら最後の氷期(最終氷期)は約1万年に終わって後氷期に入ったと多くの人が考えていたからだ(後氷期は現代まで続いている)。そこで当時の考古学者たちが提唱したのが「後氷期適応論」だった。
気候が温暖化し、森が広がって草原が狭まったせいでナウマンゾウのような大型獣が姿を消した。一方で、植物は多様化し、量も増えた。それを調理し、保存しやすくするのに土器が発明され、利用されたのではないかとする説である。1960年代から90年代後半まで、多くの考古学者がこの説を採用していた。
しかし話はここで終わらない。1999年、青森県の大平山元I遺跡(おおだいやまもと・いちいせき)から出土した土器の(付着炭化物の)年代が約16,500年前であることが、炭素14年代法とそれを暦の年代に補正する「暦年較正」(後述)により明らかになった。

16,500年前と言えば、(約7万年前に始まった)最終氷期の真っ只中。結局、温暖化しつつあった環境に適応するために土器が発明されたという解釈に基づく後氷期適応論は、根本から揺さぶられることになった。
温かくなったからではなく、寒かったから土器が必要だった?! 火を使って加熱し、少しでも食材の栄養を引き出し、保存性を高める知恵として土器が発明された?! 土器は同じでも、それがいつどんな環境で登場したかによってその意味づけが一変する。土器は生きのびるためのイノベーションだったのだ。
「時間の物差し」として活躍する水月湖の年縞
大平山元I遺跡の土器(付着物)の年代を特定する決め手となったのは、炭素時計のズレを補正する較正曲線だ。
炭素14は一定のスピードで減っていくとはいえ、実は、その初期の量はいつでも同じというわけではない。太陽活動や地磁気などの変化によって、大気中の炭素14濃度は揺れ動いている。つまり、試料に含まれる炭素14の割合だけでは「いつから減りはじめたのか」がはっきりしないのだ。
この「時計の狂い」を補正するために登場したのが較正曲線だ。年輪のように「この木は何年に伐採された」と暦年がはっきりしている試料を集め、炭素14の濃度と暦年の対応関係を地道に記録した「標準時刻表」を作る。まるで時報で腕時計を合わせるように、この較正曲線を使って炭素14年代を暦年に読み替えるのだ。
年輪の他、もう一つの「時間の物差し」=年縞も過去の時間を精密に測る手がかりとして活躍している。特に水月湖の湖底から掘り出された年縞は5万年前から現在までという気が遠くなるようなスケールをカバーする最新の較正曲線の構築において決定的な役割を果たした。炭素14年代を暦年に変換する標準時刻表を、より正確に、より古い過去まで延ばす作業は今や世界中の研究者が競って取り組む最前線のテーマである。
年縞が語るのは時間だけではない。そこに含まれる花粉化石を手がかりに、過去の気温や降水量、森林の広がりといった「気候・環境の履歴書」を細密にたどる研究も進行中だ。
「中川(毅)先生たちの(水月湖の)年縞のデータも、土器が最初に出現したのは寒冷な時期だったことを示しています」(工藤さん)
現在までに中川さんが発表した水月湖の花粉化石のデータは最終氷期の終わり頃である晩氷期(1万7000〜1万1700年前)と後氷期のはじめまでだ。そのおかげで土器が最初に出現した頃である縄文時代草創期の環境が明らかになった。

それだけではない。工藤さんと同じ日本考古班のメンバーで、九州南部を主なフィールドとして縄文時代の土器などを研究している九州大学特別研究者の桒畑光博(くわはた・みつひろ)さんによれば、中川さんの花粉化石のデータを見て気付いたことがあるという。
九州南部で起きていた、2つの異変
「水月湖のデータを見ると、(縄文時代草創期に当たる)約1万2800〜1万1700年前、ブナの花粉が出現する割合が激しく増えたり減ったりしています。つまり、ある年にはブナの花粉が多く、別の年には少なかったのです。これはブナの生育環境が不安定だったことを示しています」
「実は九州南部ではこの頃の人々の生活の痕跡である遺跡が不明瞭となっているんです。この時期は、数十年のスパンで気温や降水量の急激な変動があり、食糧の確保や定着的な生活の継続が難しくなっていたのかもしれません。ちょうどその不安的な時期のはじめ頃(約1万2800年前)に発生した桜島火山の噴火史上最大規模の噴火(桜島薩摩火山灰:Sz-S)も環境の悪化に追い打ちをかけたかもしれません」(桒畑さん)
九州南部で縄文人の活動が減少したと思われる時期は他にもある。約7,300年前、九州本土の南端から約40kmの沖合の海底にある鬼界カルデラが噴火した後の数百年だ。
ちなみに、7月3日に震度6弱を記録するなど最近活発な地震が見られるトカラ列島の悪石島は、九州本土南端から約200km離れたと ころにある。トカラ列島も鬼界カルデラも琉球海溝と呼ばれる海溝の付近に位置する。琉球海溝では太平洋側のフィリピン海プレー トが大陸側のユーラシアプレートの下に沈みこんでおり、地震を引き起こすひずみが蓄積している。世界で最も火山密度の高い場所 としても知られる。
話を戻すと、約7,300年前は縄文時代の早期末に当たる。なおその火山灰が作る赤茶けた地層は、それが鬼界カルデラの大噴火によるものだと明らかになる前から宮崎の農家の人たちに「アカホヤ」と呼ばれていた。そのため約7,300年前のこの火山灰は鬼界アカホヤ、この噴火は鬼界アカホヤ噴火などと呼ばれる。
「このとき発生した巨大な火砕流は、海中に流れ込むとともに、海面を流走して九州南端の大隅半島と薩摩半島に到達しました。最新の研究成果で、噴出源に近い薩摩硫黄島の火砕流の温度は590℃または640℃以上、一方で大隅半島と薩摩半島では200〜350℃と推定しています。九州本土に達した火砕流の温度は半分に下がるのですが、当時一帯に繁茂していた樹木や草は焼き尽くされ、生態系にも壊滅的な影響を及ぼしたはずです」
「火砕流が到達した範囲では200年間程度、遺跡の空白期間が認められ、しばらくの間無人の状態だったと想定されます。その時期の遺跡を調べると、九州全体で、小規模なものばかりとなり、出土土器の点数も少ない。おそらく人口が減少するとともに定着的な生活が困難となり、移動性の高い生活に変わっていたのでしょう」
このときの噴火の規模は、火山爆発指数(VEI。噴出物の総堆積量によって火山爆発の規模をランク分けしたもの)でVEI7と推定されている。VEIは0から8までに区分けされ、1増えると噴出物の総堆積量が10倍になる。1991年の雲仙普賢岳噴火がVEI3で、鬼界アカホヤ噴火はその1万倍に相当し、過去1万年では世界最大である。空高く舞い上がったその火山灰は偏西風に乗って遠く運ばれ、東北地方まで飛来した。

水月湖の年縞にも残されていた鬼界カルデラの火山灰
もちろん福井県の水月湖の年縞にもこの大噴火の火山灰が含まれている。年縞博物館の年縞展示コーナーでそれを確認できる。「7253±23年前 鬼界カルデラの火山灰」の手書き文字が記されたテープのある箇所の年縞を見ると、他の部分よりもとりわけ灰色の濃い層がある。自然が解き放つ巨大な力を時を超えて伝える痕跡だ。しばし眺めていると畏怖の念がわいてくる。

さて、火山灰が分厚く降り積もったはずの九州南部から人が離れるのは、ある意味当然だ。
しかし、もしかすると鬼界カルデラの噴火だけが人を遠ざけた理由ではないかもしれない。
そう思わせる発表が、中川さんの報告の中にあった。先に触れたように中川さんが水月湖の花粉化石のデータは後氷期のはじめまで。具体的には約1万年前までだった。しかし今回の領域会議に向けて花粉分析に取り組み、約6500年前までのデータを用意していた。
それは「(今回の前に開催された会議での)工藤さんとの約束を果たす」「桒畑さんにお土産を渡したかった」ためだった。
「(グアテマラの)ペテシュバトゥン湖を調査している間もホテルの部屋に顕微鏡セットを持ち込んで日本にいるときと同じペースでサンプルの分析を継続しました」
旅先でくつろぐ代わりに、スライドと格闘し、数千年分の花粉の記録を読み解いていたのだ。
さらに分析済みのデータも再度分析しなおしたという。
「気候の不安定性を議論するぞと思って自分で分析して作ったグラフを見た時に恐怖が芽生えてきたんです。分析が下手でノイズとシグナルを区別できていないんじゃないか。自信を持って、『これが暴れる気候です』って世に問うためにもう一度試料を取り直して、処理をして、顕微鏡を見ました」
結果として得られるのはグラフ上の1点に過ぎない。しかしその裏には、研究者の責任感と矜持が幾重も積み重なっているのだ。こうして中川さんは、新たな「暴れる気候」の兆候を見つけた。
「スギの花粉の変動を見ると、鬼界アカホヤの前の約120年、植生は、そしておそらく気候はそれほど変化しなかった。ところが鬼界アカホヤの後の200年は気候が『暴れていた』可能性があります」
人々が九州南部を去ったのは、単に火山災害からの避難のためだけではなかったのかもしれない。次に何が起こるか分からない。そんな気候の「裏切り」により、森の恵みが失われ、祈りは天に通じず、じわじわと人々の暮らしは追いつめられていったのだろう。明日の生活に希望を持てず、その地を捨てざるを得なかった 。そんな可能性が見えてくるのだ。
年縞と最先端の分析技術が追い込む「時間のズレ」
過去を遡れば遡るほど、いつ何がどんな環境で起こっていたかを明らかにするのは難しくなる。だから数千年以上も前の出来事については研究者すら100年単位の時間のズレや気候の微妙な変動は無視する他なかった。しかし年縞と最先端の分析技術が手を組んだ今、ズレの範囲はついに「数年から数十年」レベルに絞り込める時代に突入しつつある。
その意義は極めて大きい。なぜなら100年のズレなら数世代かけて経験する出来事しかわからないが、数年から数十年のズレなら一人が一生の間に経験する気候や環境の変化まで捉えられるからだ。「暴れる気候」研究プロジェクトの目標は「人生の時間スケール」で先史時代の出来事を詳細に再現することだという。
時間や長さの測定精度の向上は人類の技術や社会に大きなインパクトをもたらしてきた。
18世紀に大航海時代をもたらしたクロノメーター、現代のスマホや自動運転システムなどを支えるGPS、半導体、医療用デバイスに応用されるナノテクノロジーなど、測定精度の向上がもたらしたイノベーションの例は枚挙に暇がない。
何とも壮大な試みだが、もしこれが実現すれば、これまで「およそ何千年前」として扱われていた出来事が、まるで現代の出来事のように語れるようになるかもしれない。火山の噴火、干ばつ、冷害、集落の移動ーーそれらが「同じ世代の中で続けざまに起こったのか」「親の時代と子の時代で分かれていたのか」といったことが見えてくれば、人々が環境の変化にどう適応しようとしたのかを、より精密に読み解くことができる。
そしてそれは単なる歴史の再構築ではなく、現代に生きる私たちが、同じように気候の“暴れ”に直面したとき、何を感じ、何を選ぶべきかを考える手がかりにもなる。
参考文献:工藤雄一郎『縄文時代草創期の年代学』
本記事で登場した中川毅さんの書籍はこちら
人類と気候の10万年史
過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか
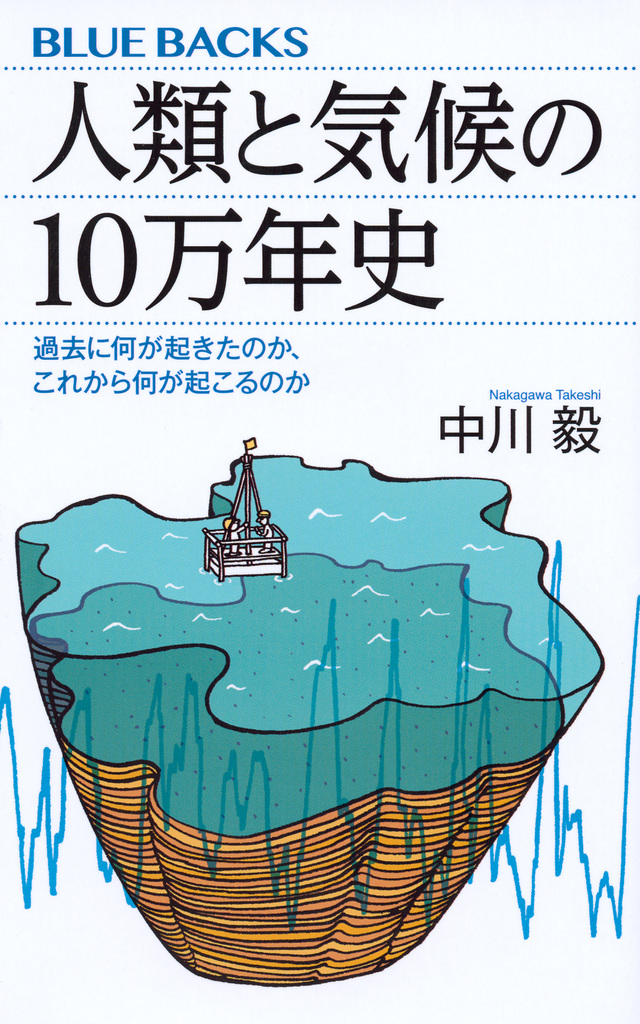
人類は、たいへんな時代を生きてきた…!
福井県・水月湖に堆積する「年縞」。その年縞が明らかにしたのが、現代の温暖化を遥かにしのぐ「激変する気候」だった。過去の詳細な記録から気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめ直す!




