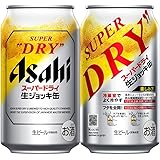この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。
日本人は移動しなくなったのか? 人生は移動距離で決まるのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか?
発売たちまち3刷重版が決まった話題書『 移動と階級 』では、通勤・通学、買い物、旅行といった日常生活から、移民・難民や気候危機など地球規模の大問題まで、誰もが関係する「移動」から見えてくる〈分断・格差・不平等〉の実態に迫っている。
(本記事は、伊藤将人『 移動と階級 』の一部を抜粋・編集しています)

「気候難民」とは誰か?
前回まで、移動が地球温暖化や気候変動に与える影響をみてきたが、気候変動も移動に影響を与え、新たな移動をめぐる課題を生じさせている。象徴的な問題のひとつが、近年、世界的に関心が高まる「気候難民」問題である。
「気候難民」とは、海面上昇や洪水、干ばつなど、地球温暖化や気候変動で住む場所を追われる人たちを意味する。気候難民は、大きく二つに分けられる。一つは気候変動により激甚化した災害により住まいを失った人たち、もう一つは温暖化による海面上昇や砂漠化により住む場所を失った人たちである。
では一体、気候変動はどれだけの人たちの移動に負の影響を与えているのだろうか。 世界的な人の移動を専門に扱う国際移住機関は2022年に、次のように推計している。
・過去10年間、台風や洪水、干ばつなどの天候に関連した災害により生じた避難民は、年間平均2160万人で、60%以上が中東、北アフリカ、東アジア、太平洋地域に集中
・2030年までに世界人口の50%が洪水や嵐、津波に晒される沿岸に住む
・気温が2度上昇する場合、2050年までに3億5000万人以上が居住不可能な気温に晒される
・気候変動による直接的な影響と農業生産力の低下などの二次的な影響をあわせると、2050年までに4400万人から2億1600万人の国内移住者が生じる
・気候の人の移動への影響は、地域や社会階層により異なり、特に最貧困層の移住が阻害される
数字だけではイメージが湧きづらいかもしれないが、危機的な状況にあることは伝わるだろう。気候難民をめぐっては、日本でも突然の豪雨や豪雪、猛暑などで感じ始めた人もいるのではないだろうか。
気候難民を粒立てることの問題
ただし、気候難民と呼ばれる人たちの存在を過度に強調し、粒立てることにも気をつけなければならない。
たとえば、私たちは「気候難民」と「気候難民ではない難民」を区別することが可能だという前提でここまで話を進めてきたが、果たしてそれは本当に可能なのだろうか。日々の自分の移動を振り返り、その原因を明確に特定することは可能だろうか。
また、気候変動のなかで人々が移動する方法は意外と多様だったりする。国境を越える移動だけでなく、国内の他の地域に移動する人のほうが多いという指摘もある。(Farbotko:2017)。さらに、多くの予測は問題を単純化しすぎており、科学的厳密さに欠け、官僚的で西洋中心的な考え方に根ざしているという批判もある(Farbotko:2018)。
気候難民は、意外と国境を越えておらず、国内の移動者も多いのでは?という議論は、国家間の貧富の差からも説明できる。気温の変化やさまざまな自然災害の結果として生じる移動は、中所得国からの場合は国境を越える移住が増加する一方で、貧困国だと逆に国外への移住が減少するという研究結果がある(Cattaneo and Peri:2016)。これは、「閉じ込められた人口」などと呼ばれる。なぜそうなるのかと言えば、移動資本やネットワーク資本は人によって異なり、移動にあてられるお金や移動の自由さが相対的に低い人たちほど、気候変動や自然災害の影響を大きく受けているからである。要するに、消極的移動(「○○からの移動」)のチャンスも、人によって差があるというわけだ。
話は少々ややこしくなってきたが、気候難民をめぐる立場や認識の違いは、本書のテーゼでもある「移動とは、社会的で政治的である」を通して考えると理解しやすくなる。
まず、気候変動による緊急事態は実際に生じている。人間の移動に直接的・間接的に影響を与えていて、今後、影響が大きくなる可能性もある。しかし、センセーショナルに伝えられる気候難民については、「その要因をすべて気候で説明すること」は難しく、慎重でなければならない。なぜなら、政治的な決定や、経済資本の多寡、どこに住んでいるかという地理的な側面も移住の意思決定と実現に影響を与えているからである。移動をめぐり、どんな困難があるのか、どんなふうに眼の前の状況を認識しているのか、丁寧に声を聞いていくことが求められている。
政治的に利用される気候難民
異常気象や気候変動などに由来する災害時の政治的な決定は、ときに緊急性を盾に「ショック・ドクトリン」の形で決定を下すことがある。ショック・ドクトリンとは、戦争、自然災害、政変などの惨事につけこみ、人々が茫然自失している間に過激な政治や経済の改革を行うことを指す(Klein:2007)。
気候変動によって住む場所を失った人たちが、その地を離れざるをえなくなったり、再建に関する決定をしたり、立ち退きを余儀なくされても構わないという気持ちになるとき、政府やその関係者の影響は計り知れない。
気候難民を過大に見積もる発言や言説は政治的であり、ときに気候変動の影響を受けやすい人たちを他の地域に移動させることを「正しいこと」のように演出する論理として、気候難民という言葉が利用されたりもする。危機に乗じて、あたかも気候難民のためかのように政権が有利な政策を推し進めることは多々あるのである。
むろん、これは政治だけに留まらない。すべての人が、気候難民問題に間接的に影響を与えているし、ときには問題の要因でもある権力関係を再生産する共犯関係になっている。
一例として、気候難民と人種の問題がある。気候変動と移住に関する言説は、多くの場合、白人中心的な人間観や先進国視点を土台としており、気候難民というカテゴリーを通じて特定の集団に対して、人種的な意味と立場を刻み込む傾向がある。その結果、人種的な他者との間で二項対立の社会的ヒエラルキー——発展している側/遅れている側、支援する側/支援される側——という関係が再生産され、固定化されてしまうのである。
本記事の引用元『 移動と階級 』では、意外と知らない「移動」をめぐる格差や不平等について、独自調査や人文社会科学の研究蓄積から実態に迫っている。

伊藤将人(いとう・まさと)
1996年生まれ。長野県出身。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。2019年長野大学環境ツーリズム学部卒業、2024年一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。戦後日本における地方移住政策史の研究で博士号を取得(社会学、一橋大学)。立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所客員研究員、NTT東日本地域循環型ミライ研究所客員研究員。地方移住や関係人口、観光など地域を超える人の移動に関する研究や、持続可能なまちづくりのための研究・実践に長年携わる。著書に『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社)がある。最新刊『移動と階級』(講談社現代新書)。