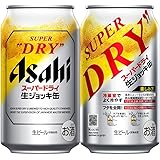日本人の幸福度は60%と、他国に比べて低い。国や文化により幸福の原因は異なるが、共通の傾向もある。日本人が幸福の原因として挙げるのものは何か? 統計データ分析家・統計探偵の本川裕氏(ウェブサイト『社会実情データ図録』主宰、近著『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』星海社新書)が解説する。
【前記事よりつづく】『幸福を感じる「原因」を徹底調査…日本人が「人生で最も大切に思うもの」とは?』
国別でみる幸福要因ランキング
さて次に、幸福を感じている人が上位3つまでに挙げる幸福の要因ランキングを各国別に見てみよう。国の並びは左から所得水準順に並べた。図の左側、あるいは右側の国に特徴的な幸福要因があれば、所得水準、あるいは国の経済発展度による違いを読み取ることが可能である。
この国別の幸福要因ランキング図を見ると以下のような興味深い特徴を読み取ることができよう。

〇家族・子ども、感謝・愛の2項目がトップランクの国がほとんど
自分を取り巻く人たちとの親しく、また充実した交流をあらわす「家族と子どもたち」および「感謝され、愛されている感じ」が幸福の2大要因であるが、ほとんどの場合、日本を含め各国で1~3位となっており、世界的な共通性が認められる。両方とも1~3位に登場してはいない例外はタイ、インドの2か国だけである。
〇家族・子どもにパートナーが含まれる国とそうでない国
「家族と子どもたち」は幸福要因として多くの国でトップランクにあるが、「パートナーとの関係」のランキングとの関係はさまざまである。
両者のランキングが近いのはオランダのようなケースであり、両者のランキングが大きく異なっているのはトルコのようなケースである。前者では家族にパートナー(配偶者)が含まれ、後者では家族にパートナーが含まれず、幸福要因としては子どもたちが中心と考えられる。
パートナーを重視しないトルコのような国は所得水準の低い途上国中心に非欧米国に多い。その場合、パートナー以外の家族として、子どもたちだけでなく同居している親や兄弟なども幸福要因となっている可能性があろう。
一方、パートナー重視のオランダのような特徴の国は、そのほか、カナダ、ポーランド、ハンガリーなどが当てはまる。反対に、欧米諸国でもアイルランド、米国、オーストラリアといった国ではパートナーは幸福要因としては余りランクが高くない。米国人夫婦の相思相愛はタテマエの側面も大きいのであろう。
〇幸福の経済的要因が強いかどうかは国の所得水準とほぼ無関係
貧しい国ほど、すなわち右側の国ほど「経済的な状況」を幸福の要因としてランキング上位となっているかと言うとそうではない。各国の所得水準の高低との相関はほぼないといってよい。
〇経済的な要因が強いのはアジア諸国
「経済的な状況」が幸福の要因ランキングが4位より高いのは、韓国、日本、マレーシア、タイ、インドネシア、インドといずれもアジア諸国(特にタイは1位と高い)。シンガポールは5位とアジアの中ではやや低い。
〇国によって特にランキングが高い幸福要因がある
・「経済的な要因」タイで1位
・「自分の人生を送れているか」シンガポールで1位、南アフリカで2位
・「精神的健康」ブラジルで1位、スペインで2位(ちなみに日本は最も低い11位)
・「友人」インドで1位、フランスで2位
〇世界パターンとかけ離れたアジア諸国
各国がどのくらい幸福の要因観についての世界パターンからかけ離れているかは、図3のランキング図で順位が一般と異なっている程度からもうかがえるが、これをより厳密に測るには、各要因に関する各国の回答率と世界平均の回答率との相関度を示すR2値を計算し、その値がどのくらい低いかを調べる方法がある(値0~1、1で完全同一パターン)。
図4にそれを示したが、世界パターンからの乖離度が大きいのは、インドネシア、インド、韓国、タイ、トルコといったアジア諸国である。幸福観においても欧米VSアジアの文化差が垣間見える。上記の「経済的な要因が強いのはアジア諸国」というのもその一環である。
アジア諸国の中でも日本、マレーシア、シンガポールはこの順番に世界パターンとの共通性が増していく。世界パターンは欧米影響下で形成されていると考えられるので、こうした国は欧米的価値観の影響が強いと考えることも出来よう。

〇信仰生活が幸福の要因である国は限られる
線の色付けが及んでいないので分かりにくいが、「信仰や精神生活」の順位は、インドネシアが5位でもっとも高く、マレーシア、ブラジル、南アフリカが6位、コロンビアが8位で続いている。その他の国はすべて10位以下である(日本は14位で最低)。イスラム教国や原始宗教を残した国で宗教生活の意義が大きいといえよう。
〇日本は健康要因が強くなく、また案外パートナーとの関係を重視
表1で日本の要因ランキングについて、世界順位との差を確認すると「精神的健康」の順位が11位と世界の4位から7位も低いのと「パートナーとの関係」の順位が5位と世界の10位より5位も高いのが目立っている。日本人は、案外、配偶者を幸福要因として大きくとらえているのである。米国の順位の世界順位との差を参考までに表に掲げたが米国の方が大きな差の要因がなく、世界標準パターンに近くなっている。
まとめ
このように、直接、調査対象者に聞いた幸福の要因ランキングの結果は、世界共通の側面もあるものの、国により、また文化圏により異なる特徴もかなりあることが分かる。
幸福とその要因に関する世界共通のパターンを見出すことも然ることながら、こうした世界各国の人びとの多様な幸福観を丸ごと受け止めることがより重要なのではなかろうか。人が何に幸福を感じるかについてはそれこそ自由なのであり、大切なのは、自分と異なる理由での幸福であってもそれを尊重し合うことだからである。
【こちらの記事も読む】『ストレスのない人生は存在しないが「ストレスを強力に減らしてくれるもの」は存在した…「幸せな人生」を送るために必要な「小さなこと」』