「借金を返すこと」、本当の意味
私たちは日々、「借りたカネは返す」ことを前提に生きている。しかし、そんな道徳観(負債返済道徳=返済を絶対視する規範))を、借金によって身内が人間性を失っていく体験をしたブレイディみかこさんは“呪い”として見つめてきた。
そんな思いを込めた彼女の新作が『私労働小説―負債の重力にあらがって―』(KADOKAWA)である。
前編『その借金、本当に返すべきなのか…?社会の“負債道徳”に問いかける「生きるために大切な考え方」』に続き、作家・ブレイディみかこさんのインタビューをお届けする。
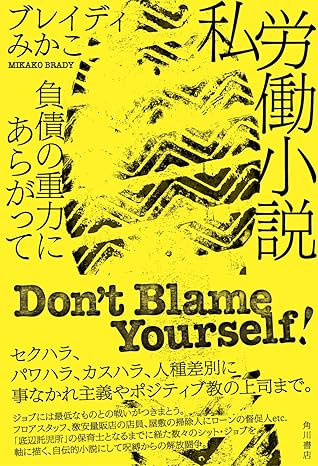
日本の多重債務者はコロナ禍を契機に増加傾向が続いており、約147万人(2025年3月末時点)に上る。
かつて「サラ金地獄」と呼ばれた状況は2006年の貸金業法の改正で収束したとはいえ、債務問題は「見えない借金」や「潜在的生活債務」へと広がっている。生活費や医療費の補てんなど借金の理由が複合化し、しかもキャッシュレス化によるデジタル信用が拡大した結果、気づけば多額の借金を負っていたという人たちが続出しているのだ。
はたして、借金はなにがなんでも返さなければいけないのか――。
ブレイディみかこさんが問う。
弱い立場の者ほど背負わされる「負債返済道徳」
――負債返済道徳は個人だけの問題ではありませんでしたね。たとえば、2009年ごろから始まった「欧州債務危機」(欧州各国で財政赤字が膨らみ、公的債務が拡大した)で、欧州連合(EU)や国際通貨基金(IMF)、とりわけドイツがギリシャに見せた強硬な姿勢には負債返済道徳が顕著に表れていました。
10年ほど前に私は『ヨーロッパ・コーリング』(2016年)という本を岩波書店から出しました。当時欧州では、反緊縮左派と呼ばれる人たちが出てきて盛り上がっていた時期でした。たとえば、イギリス労働党の党首になったジェレミー・コービンだったり、スペインの左派政党「ポデモス」の創設者・パブロ・イグレシアスというリーダーが出て話題になっていましたが、とりわけ有名になったのはギリシャの政党「シリザ」(急進左派連合SYRIZA)ですよね。

ギリシャが債務地獄に追い込まれたとき、当時シリザに所属していた経済学者・ヤニス・バルファキスが財務大臣になりました。ギリシャは対外債務の返済のために極端な緊縮財政をとらされて経済がボロボロになっていました。若年層の失業率が6割まで上がっていたし、学校も閉鎖、医療も回らず死者が増えるという悲惨な状況でした。
バルファキスは諸悪の根源である対外債務をなんとかしてほしいとEUに話をつけに行き、当時のドイツ首相・メルケルに「借りたものは返さなきゃいけません」という強硬な態度で冷たくあしらわれた。
「だって、借りているのだから」。
「たとえ国内が混乱して死者が出たとしても、それは債務があるのだからしかたがない。緊縮財政を続けなさい」というような態度でした。
あのときのドイツやEUの姿勢は、英国では「血も涙もない」と批判されました。あれが、その後のイギリスのEU離脱の一因になったのは間違いないと思います。
ドイツの態度は貧しい欧州国をいじめているようにしか見えませんでしたし、借金を返すことが人命より大事みたいな考え方っておかしくないか、財政の規律を緩めて国債を発行し、緊縮をやめ今苦しんでいる人たちを救うべきじゃないのか。
そのような訴えでEUやIMFの求める財政均衡に抵抗したのが、「反緊縮左派」だったのです。ある種の拝金主義への抵抗だったと言ってもいい。
借金で心を病んだ身内の姿を見ていた私は、「この人たちが言っていることは正しい」「人間がカネに壊されてはいけない」と強く感じる部分がありました。借金のために、つまりお金のために人間の生活や命が犠牲にされるというのは、ひどく倒錯していると思います。
デヴィッド・グレーバーの『負債論』
『私労働小説』の一作目は、人類学者のデヴィッド・グレーバー(1961~2020)の「ブルシット・ジョブ」(くそどうでもいい仕事)に触発されて、「シット・ジョブ」(報われない仕事)をテーマにしました。今回は彼の「負債論」をテーマにしたわけですが、どちらかといえば私にとってより切実に重要だったのはこちらでした。
――日本では『負債論―貨幣と暴力の5000年』(以文社)として、2016年に刊行されていますが、800ページを超える大著です。グレーバーは貨幣と人間の関係を根底から問い直したとされますが、どのような論考なのか、ご解説いただけますか。
アナキストとしても知られるグレーバーは、基本的に人が人を支配する構造が人を不幸にするという考え方を持っています。アナキストによく取り上げられるのが社会人類学者のマルセル・モース(1872~1950)の「贈与論」で、グレーバーも影響を受けました。

モースは、経済の起源を「物々交換」ではなく「贈与」に見いだして、それは単なる物と物との交換ではなく、人間と人間の関係が深くかかわってくるものなのだと指摘しました。日本で言えば、「お中元」や「お歳暮」がありますが、もらいっぱなしにすることは良くないと感じて、誰もがお返しをしようと考える。気前よく“あげている”ようにみえても、もらった側には“返礼の義務”が生まれているわけです。
そこにはギブ&テイクの人間どうしの交流が生まれるから、グレーバーもこの論に影響を受けつつ、返礼の義務について深く考察するんです。それは、貰ったらお返ししてという対等な“つきあい”を、“支配”の構図に変え得るものでもあるからです。
つまり、善意で“もらった”はずのものでも、返さなければメンツが潰れるとか、人として劣るという通念が生まれ、返礼が道徳的義務になり、さらにはルール化されてしまったら、与えた側が「まだお返しを貰っていないこと」を利用して受け取った側を支配できるようになります。こうなったら「負債」と同じですよね。返礼の義務があるところでは、返し終わるまで人間関係は対等ではなくなる側面がある。
グレーバーは『負債論』で、貨幣の起源は借用証書、つまり「負債の記録装置」だと書きました。借用証書が流通するようになって貨幣になったというのです。こうした貨幣制度は、借用証書を保証できる力と信用を持つ存在がなければ成り立ちません。その最も大きな信用力を持っているのは国家です。やがて貨幣を国家が独占し、流通させる借用証書=紙幣を発行するようになりました。国家は税を徴収し、軍事力を持つために貨幣を利用します。こうして貨幣は権力と暴力と結びついたわけですが、その瞬間、貨幣は「信頼」ではなく「服従」によって支えられるようになった。
現在の貨幣経済を見てみると、たしかに借用証書の機能にあふれています。借用証書を売り買いする市場まであるほどです。借りたものを返すことが個人の信用を膨らませ、逆に返さない人の信用は摩滅していく。こうして、「借金は何があっても返さないといけない」という負債返済道徳が人々の信用情報の基準になり、鉄壁のモラルになるのです。そんな“呪い”をかけることで、貨幣は人々を支配し、逃れられなくしている。でも、それは人を不幸にしかしないですよね。そろそろ解放されませんか――。
これがグレーバーが『負債論』で語りかけていることです。
きっかけは、彼がマラリアの撲滅活動のためにマダガスカルに滞在したことでした。負債が返済できないからIMFに緊縮財政を強いられ、活動プログラムが打ち切りになり、1万人が亡くなり、その半分は子どもだったそうです。
そんな悲惨な状況を目撃したグレーバーは、ロンドンで弁護士に「借金返済のために緊縮財政を強いられて、その一方で子どもがたくさん犠牲になっている」と訴えました。ところが、人道派を称するその弁護士ですら、「でも、借りたものは返さなくちゃいけませんよね」と冷たく言い放ったそうなのです。
人命よりも重視される負債とは、いったいどんな呪縛なんだと、グレーバーは『負債論』に取り組んだのです。
負債論の説くエッセンスは、いまの社会にとても重要なものだと思います。なぜなら、負債返済道徳という名の拝金主義は排外主義にも強く結びついているように思えるからです。
排外主義の裏にある「市場経済」の問題
――本作の第三話は、イギリスのアジアン・フュージョンレストランが舞台です。かつてはオリエンタリズムを感じることができるレストランが、やがて店員の大半がアジア系の移民に変わると“侵略”と解釈されるようになってしまった。
イギリスも、いまでは排外主義が盛り上がっていますが、かつてのアジアン・レストランでの経験にその兆しのような嫌な雰囲気があったなと思い出しながら書きました。
排外主義の裏にも経済的な支配構造を感じます。
欧州の右派ポピュリズム政党の台頭が著しいですが、イギリスでは「リフォームUK」が高い支持率を得ています。
彼らが「(移民の)永住権をなくす」と発表したんです。これまで付与されていた人たちの永住権も剥奪すると言うのですが、これは特に日本人にとっては深刻な問題なんですね。日本は二重国籍が認められていないので、イギリスの国籍を取らずに永住権で住んでいる人が多いからです。いま在留日本人社会はざわついていて「本当にリフォームUKが政権を取ったら日本に帰らなきゃいけないのかな」と不安に駆られています
でも、永住権を剥奪しても彼らは「一定の年収がある人には5年毎にビザを出すから残ってください」と言っているのです。その年収は、英紙が報じたところによると、年収で6万ポンド(約1200万円)以上なんだそうです。イギリスの人々の年収の中央値の2倍以上になります。
本当に外国人を排除するのが目的なら、所得が高かろうが低かろうが、永住権を取り上げるのではないかと思うのですが、でも、お金持ちだけはいてくださいって、これは単なる排外主義ではないし、何か別物ですよね。

白人至上主義のトランプが大統領のアメリカだって、海外の富裕層にビザを高額で販売すると報道されたりしていましたよね。結局は移民が問題なのではなくて、お金がない人たちは負担になるから要らないということじゃないでしょうか。
イギリスでは、格差がすごく広がって、お金のあるなしで住む地域が完全に分断されていて、それは「エコノミック・アパルトヘイト」と呼ばれているのですが、リフォームUKは、これをグローバルにやろうとしているのではないかと。「我が国には金持ちだけが住めばいいんです。お金がない人は、そういう人たちが集まるところに行ってください」ということです。
リフォームUKの党首・ナイジェル・ファラージは、英国のEU離脱を主導した人物でもあります。EU離脱で、EU圏から来た移民の多くが帰国しましたが、今度は建設作業員やトラックのドライバーなどエッセンシャルワーカーの人手不足に陥って、EU以外からの移民を入れなくてはならなくなった。すると今度は「肌の色の違う移民が増えていかん」「我が国の文化が……」などと言いだし、以前よりさらに差別的になった感覚はあります。
ア・ピンチ・オブ・ソルト!
なぜ、そこまで自分を追い詰めしまうのかと考えてみれば、それは周りから押し付けられた道徳というか、社会的通念に支配されていることに気づきます。本来は、そんな権利もない人たちが、あなたを責めているかもしれません。
だから、「こうあるべきなんだ」という一般的な通念を疑ってみることが大切だと思います。負債返済道徳はその好例で、「返さない人はろくでなし」と世間一般で言われてることを、本当にそうなんだろうか?とグレーバーのように疑い、深く考察してみると、これまで見えなかったことが見えてきたりするのではないでしょうか。

「貨幣は物々交換から生まれたもの」と言われてきたけど本当にそうなのかなと。「借金は何があろうと絶対に返さないといけない」というのがモラルになっているけど、これは常に、絶対にそうなのだろうかと。「外国人が増えると征服される」とすごく不安なんだけど、それってそもそも誰が何のために言い始めたことなんだろうかと。
本当は、世界のたった1%の人だけに富が集まっていることが深刻な問題なのに、それから目をそらさせるために、いろんなことを吹き込まれ、信じ込まされているんじゃないだろうかと。
イギリスには、「ア・ピンチ・オブ・ソルト」という言葉があります。ひとつまみの塩を持って、つまり何でも鵜呑みにしないで、少しばかりの猜疑心を持って物事を考えろという意味で使われます。
人間を救うのってこのひとつまみの塩ではないでしょうか。ひとつまみの塩を持って疑ってみれば、悩まされていたことが、じつは根拠のない不条理なことだったというふうに見えてくる。「なんでこんなことで悩んでいたんだろう」「それっておかしくない?」と。
同調圧力の強い日本では、「ア・ピンチ・オブ・ソルト」は嫌われる言葉かもしれません。でも、ちょっと疑いの目で見るぐらいでないと、世間的な通念に押しつぶされてしまうと思います。自分を責めるより、「ア・ピンチ・オブ・ソルト」です。
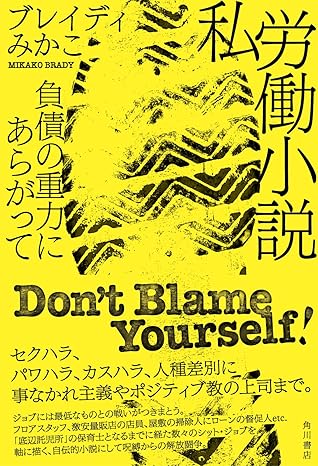
さらに『こき使われてたまるか!―「セックス・ピストルズ」と「クソ報われない仕事」が投げかける「この社会に本当に必要な仕事」』でも、ブレイディみかこさんの『私労働小説』を紹介しています。




