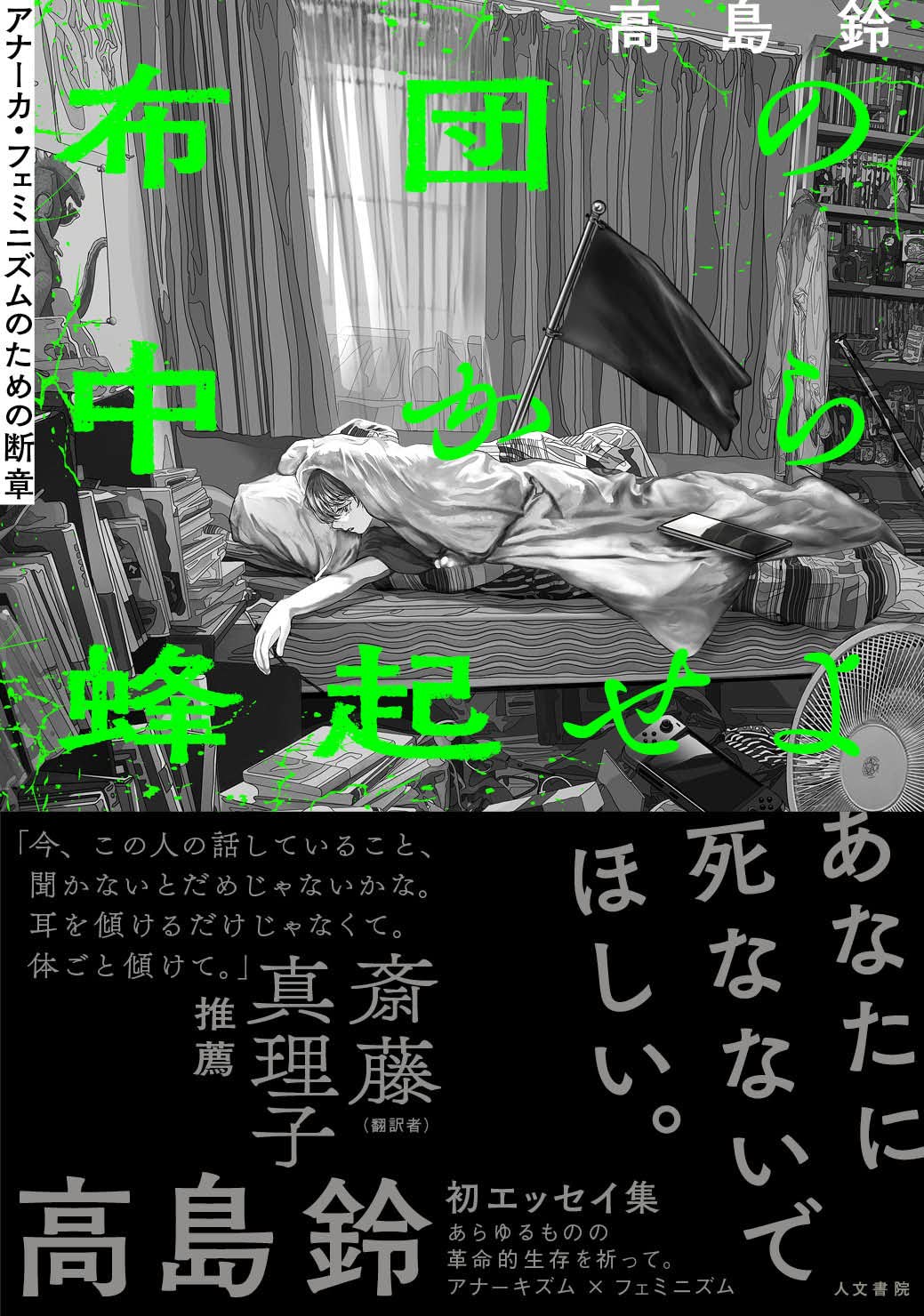紀伊國屋じんぶん大賞2023大賞『布団の中から蜂起せよ』著者で、アナーカ・フェミニスト、パブリック・ヒストリアンの高島鈴さんによるシリーズ「抵抗のための一人読書会」。
第1回(なぜ私たちは「対話」できなくなってしまったのだろう)から大きな反響をがありました。「イマジナリーフレンド」Qとの読書会、第2回目は「法律」をめぐる回です。どこに向かうのでしょうか?
法律に疲れている
Q:今日もなんだか頭を抱えているね。どうしたの?
――なんか、法律って嫌だなあ、と思って。
Q:急にどうしたの……っていうわけでもないか。前回がまさに、死刑制度の話だったもんね。そこから引きずっているってこと?
――それもある。でも、やっぱ自民党総裁選で結局高市早苗が勝っちゃって、あれだけ問題になった裏金議員のことをスルーしている人が総裁って、と思ったら、もう気が重くて。
Q:まあ、あの人たち、まだ裁かれてないもんね。どういう理屈なんだろうね。
――でしょ? やっぱり法律って明らかに不均衡だと思う。みんな知っている通り、ピルが保険適用じゃないとか、性暴力への量刑とか、つい最近まで優生保護法が存在していたこととか、なんかもう、全部おかしいよね。
Q:いきなり捲し立てるね。そんなに法律嫌いだったっけ。
――まあ平たく言って嫌いだけど、法律というもの自体には関心がある方だと思うよ。思想柄気にしないといけないものも多いし、もともと専門が中世法だったしね。
Q:なるほど。まあ実際過去の法律って今から考えると本当にヤバいものがあるよね。
――それは本当にそう。中世ってまず、そもそも法律が保存されないからね。
Q:どういう意味?
――そのまんま。出したら出しっぱなしなの。だから基本的に幕府の裁判官とかは法律のことをほとんど知らない。中世って自己弁護が基本だから、訴人(原告)がこの人はこの法律に違反していますって異議申し立てをするんだけど、「そもそもこの法律は実在しているのか」が論点になったりする。
Q:それで成り立つわけ?
――何がどうなったら「成り立つ」と言えるのかはわからないけど、まあ、人は生きていたよね。普通に。
Q:まあ、法に守られるばかりが人間ではないか。
――それはそう。ちなみに中世法に関しては、1938年に石井良助『中世武家不動産訴訟法の研究』っていう体系的な研究書が出ているんだけど、これが「中世人に裁判のやり方を教えてやるような本」と称されたくらい、中世には裁判の方法論がない。ちなみにこの本は長く絶版だったけど、名著すぎていまだに参照される内容だから、私が学生の頃に高志書院から80年越しで復刊された。1万2000円したけど、買いましたね。
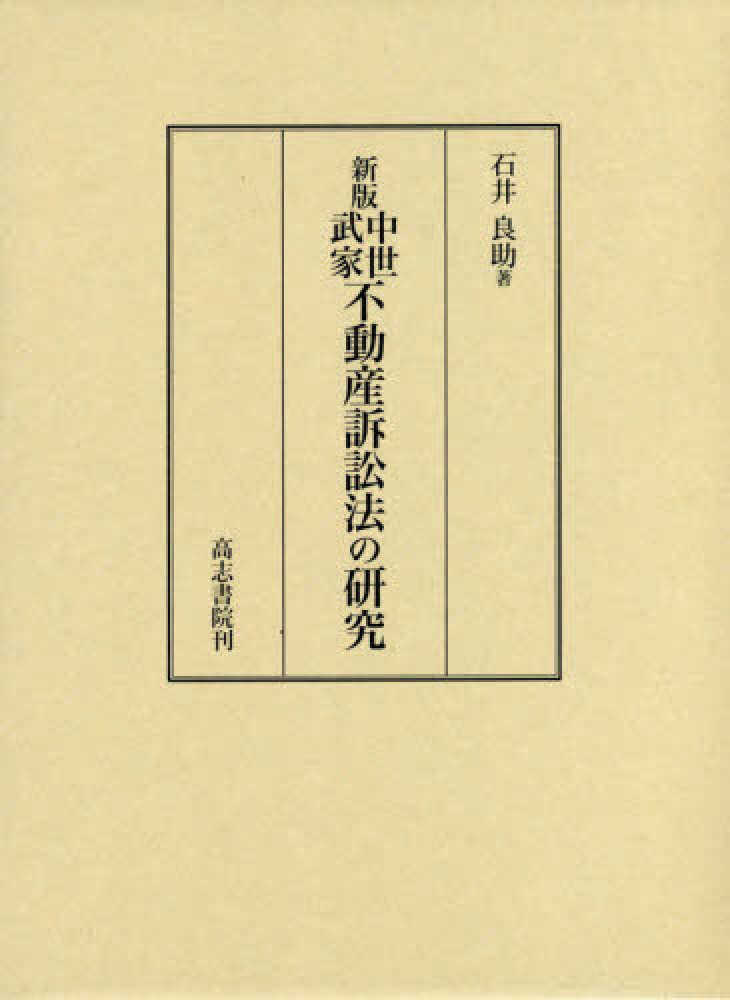
Q:思い出じゃん。まあでも確かに、そういう世界に鑑みると、現代的な法律の感覚って決して絶対ではないな、というのは分かるよね。きっとこの先十年二十年の単位で変化していくんだろうし、百年経ったらもっと常識ごと塗り変わっているだろうし。
――そう。今の状況がベストじゃないよねって思うのは、やっぱり歴史的に見て法律はとても時代的変化が強く出るものだから、という部分はある。例えば右翼が大好きな「武士道」精神って、実は法治の概念とすごく相性が悪いんだよ。
Q:何急に、どういうこと?
――ここ数ヵ月だらだら読んでいる小島毅『近代日本の陽明学』(講談社学術文庫)に書いてあったことなんだけど、近世〜近代の武家の人たちの間で支持された陽明学って、「自分を強く持って自分で自分を律していく」っていう考え方だから、法治じゃないの。自律なの。
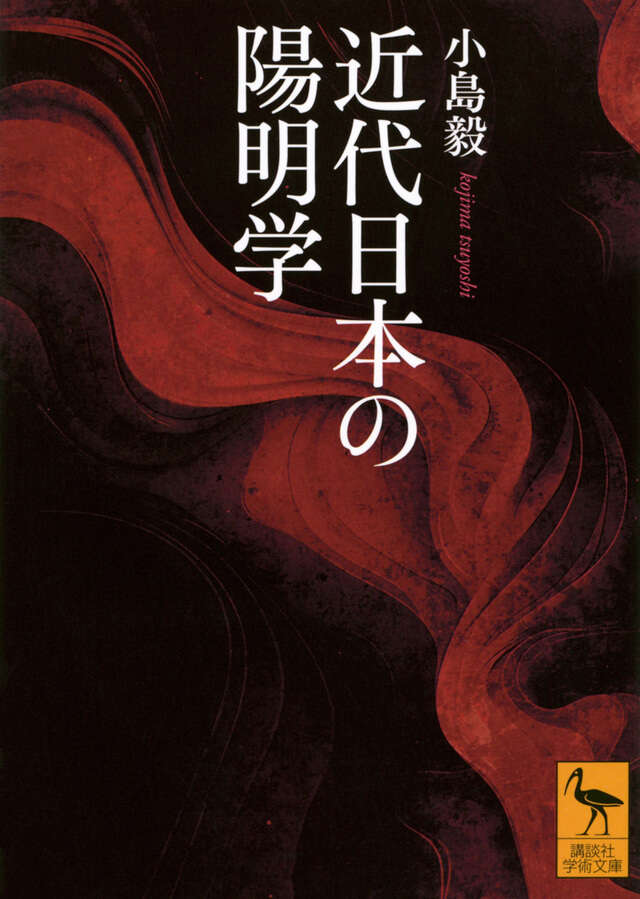
Q:あ〜、法に頼らず自力で自分を統治せよってこと?
――そう。近代になって日本はヨーロッパにおけるキリスト教みたいな独自の精神的支柱がないことに悩んで、対外的に「日本には武士道がある」みたいな説明を始めるんだけど、そこで持ち出されるのがそういう理屈なんだよね。自分で自分を律する、っていう。
Q:なんか現代に通じる話っぽい気もしてくる。やっぱ外圧があって初めて、自分たちには「伝統」がある、みたいなことを頑なに語る必要性が出てくるわけだよね。そこで対他存在としての「日本精神としての武士道」みたいなものが発生してくるんだ。
――まあ実際それはそうかも。ちなみに、当時は伊藤博文がドイツを参照して最初の大日本帝国憲法を作ったので、近代日本の西洋思想受容においてはドイツ哲学が一番重んじられたらしいんだけど、「自律する個人」っていう点ですごくカントに共鳴する思想家がいっぱいいたらしいよ。カントは全然知らないけど、『近代日本の陽明学』の小島さんはそこでカント-武士道-陽明学を連結させていて、すごく面白かった。
Q:武士道が《日本的なるもの》であるならば、陽明学もそうであるはずなんだけど、陽明学って当然ながら中国の王陽明に系譜があるわけで、なんか笑っちゃうな。
『チーズとうじ虫』過激な言説が暴いたもの
――なんか冒頭では裏金議員の話をしたんだけど、法律嫌だなって思う理由は他にも100個くらいあって。
Q:いきなりくるりみたいになったな。
――まあその一つを言うと、ヘイトデモのカウンターに出たとき、だいたいネトウヨから「道路交通法の許可を取ってない」って言って責められるわけ。
Q:デモって道路交通法の許可が必須なんだっけ?
――道路を使う場合は道路通行許可がいるね。デモだから許可がいるんじゃなくて、集団で道路を歩くから許可がいるってことで、なんか神社の祭礼行列とかも同じカテゴリらしいよ。ちなみに出発地点に公園とかを使う場合には、占有許可っていう別の許可を取る必要がある。
Q:カウンターは許可を取らないの?
――えー、今どうなのかよくわかんないけど、基本しないと思う。ヘイトデモっていつやりますよって発表が公になるのがギリギリだったりして、それに対処しようとするとやっぱり申請間に合わなかったりするんじゃないかなあ。私は書類書いたことないからわかんないけど。
Q:なるほどねえ。そこでカウンター側は、法律守ってないだろって責められるわけね。
――なんか、こっちからすると、目の前で隣人が迫害されているのを止める以上に道路交通法の書類を書くのが大事なんですか? そんなわけなくないですか? って思っちゃうんだよ。実際それは間違ってないと思うし。なんか、そういうときだけ法律を振りかざしてくる人っていっぱいいるじゃない。結局社会に対する異議申し立ての口を封じるための方便として法律が使われている場面って、法律自体の不均衡も相まって、めちゃくちゃ多いと思うんだよな。
Q:法律にのっとって「きちんと」異議申し立てをしようと思うなら、結局弁護士とか、法律の専門家が必要になるね。もちろん無償で動いてくれる人も少なくないけど、そういう一種のエリートを介さないと声を上げられないっていうのはなんだか変な話ではある。
――びっくりするんだけどさあ、それとほぼ同じことを言ってる人が、16世紀にいたんだよ。
Q:なんだそれ。
――カルロ・ギンズブルグの『チーズとうじ虫』(みすず書房)って本を最近読んでいるんだけど、これがすごくて。16世紀イタリアで火炙りになって死んだ、メノッキオっていう粉挽屋についての歴史書なんだ。
Q:なんかユニークなタイトルだけど、どういう意味なの?
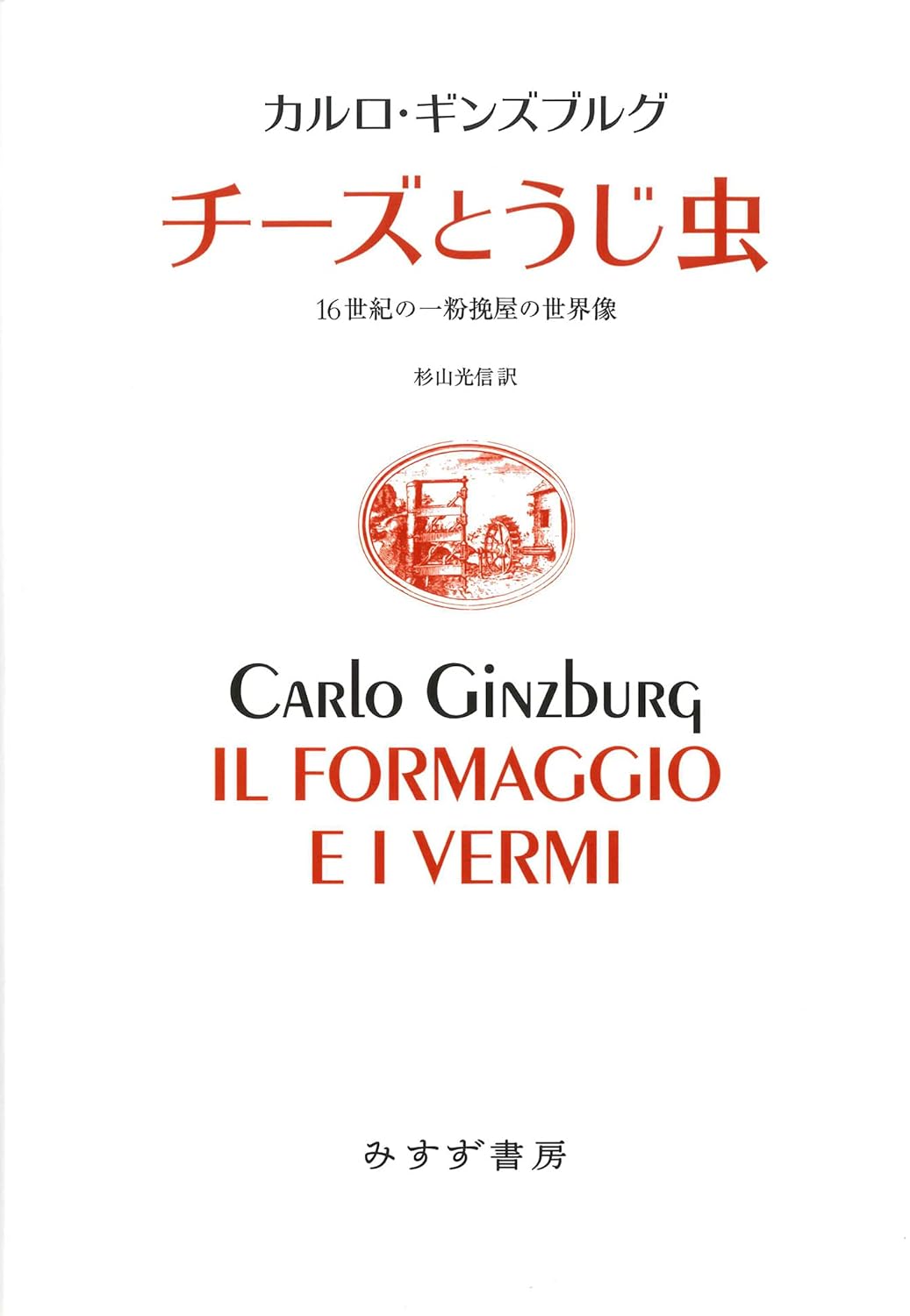
――それがまたすごくて。メノッキオってもともと村の重役も務めた妻子ある成人男性なんだけど、同時にすごい変わり者で、常に全身白い服を着て、周囲に「神って大地とか空気のことなんじゃないの?」みたいな、ローマ教会に反抗するオリジナルの神学議論をふっかけまくっていたらしい。それも二十年以上にわたって。
Q:全然話が見えないけど、メノッキオがスレスレで生きていた人なのは分かる。
――そうなんだよね。周囲はめっちゃ止めるんだけど、全然やめなくて、結局裁判にかけられてしまう。そこでメノッキオは、最初は悪霊に唆されたんだとか言うんだけど、だんだん開き直っていくんだよね。その過程で、「神や天使はカオスから生まれた。牛乳からチーズができ、チーズからうじ虫が湧いてくるように」みたいな、独自の宇宙論を展開し始めるんだよ。
Q:すげえ……それで『チーズとうじ虫』なわけね。しかしそのチーズとうじ虫って例え自体に、メノッキオという人の生活世界が表れているようにも感じるね。
――そう! それも面白いところ。で、裁判のある地点からメノッキオは開き直って自説を開陳していくんだけど、まず最初に法廷で使われる言語がラテン語というインテリ向け言語であることを痛烈に批判するんだ。
「私は、ラテン語で《話す》ということは貧乏人を欺くひとつの方法であると思う。なぜなら、裁判において貧しい人びとは言われていること、かれらが瞞されていることを理解できない。そして言うべきことが四言ほどでもあるなら、かれらは弁護士を必要とするからである」(前掲書、47頁)
すごくない? これじゃ貧乏人は弁護士なしじゃ何も言えない、それはおかしい、って言ってるんだよ。16世紀に。
Q:ええ、なんかマジで2025年に言われた言葉だと言われてもわりとラディカルに聞こえるんだけど。
――本当にそうなんだよね。この本を書いたギンズブルグは、序章で以下のように書いている。
社会的排除の犠牲者は、既存の社会にみられる嘘にたいするラディカルな返答であるような独自の言説の受託者なのである。(前掲書、10頁)
……これ、本当にいい文章じゃない? 読み始めてすぐにこんなのが目に入ったから、もうくらくらしちゃったよね。
Q:これはつまり、メノッキオみたいに排除された人たちの持っていた過激な言説こそ、マジョリティによって形成された社会の欺瞞を暴いている、ってことかな。
――そんなところだと思う。メノッキオはまさに過激な言説そのものによって有罪になって肉体ごと排除されたわけだけど、それ自体が法律が社会的マイノリティに対して冷酷であることの証左であるようにも見える。
Q:もちろん現代の法律とは違う、ということを念頭に置かないといけないけど、構造的な問題が16世紀イタリアでも現代日本でも似た部分を抱えていた、っていうのはかなり注目に値するかもね。
監獄廃止と修復的司法
Q:ちなみに法律の話に戻るけど、きみは監獄廃止派(アボリショニスト)だよね? さっき量刑の不均衡について言及があったけど、監獄廃止派でもそういう話はするんだ?
――まあ、そこについては単純に受け答えできる話じゃないよ、っていうのはまず言わないといけないね。そのうえで監獄廃止派がなんで監獄廃止を訴えるかって言ったら、それは罰を受ける側の不均衡があるからだよ。
Q:あ、ネトフリのドキュメンタリー「13th―憲法修正第13条―」で見たぞ、その話。
――そう、アボリションの本場であるアメリカだと、如実に収監者には白人より黒人のほうが多い。そのうえで収監者が格安の労働力として監獄と共謀した大企業に貸し出されているんだから、やっぱりおかしいんだよね。日本ではそこまで監獄と企業の癒着って露骨ではないけど、やっぱり東アジアルーツのルックスよりそれ以外にルーツを持つ人の方が職質を受けやすいとか、そういう「逮捕の契機」の違いってあるでしょ。
Q:それだけじゃ説明にならなくない? 加害者がどうなればいいと思ってるの?
――アナキストとして言えば、なんで被害者と加害者の間で起きたことが、国と加害者の話にすり替わるの?っていう疑問があるよね。本来一番尊重されるべき被害者が、そこでは置き去りにされているんじゃないかって。もちろんすべてが二者間でどうにかなればいいとは思わないんだけど、国が上から加害者を罰することが本当に再発防止や「償い」になっているのか、私にはよくわからない。法自体が不均衡であることを考えれば、むしろ問題をこじれさせているように見える。そもそも「償う」ってどういうことなのか、それも難しいんだけど。
Q:斉藤章佳・にのみやさをり『性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ』(ブックマン社)を思い出すね。あとは小松原織香さんの『当事者は嘘をつく』(筑摩書房)も重要かな。
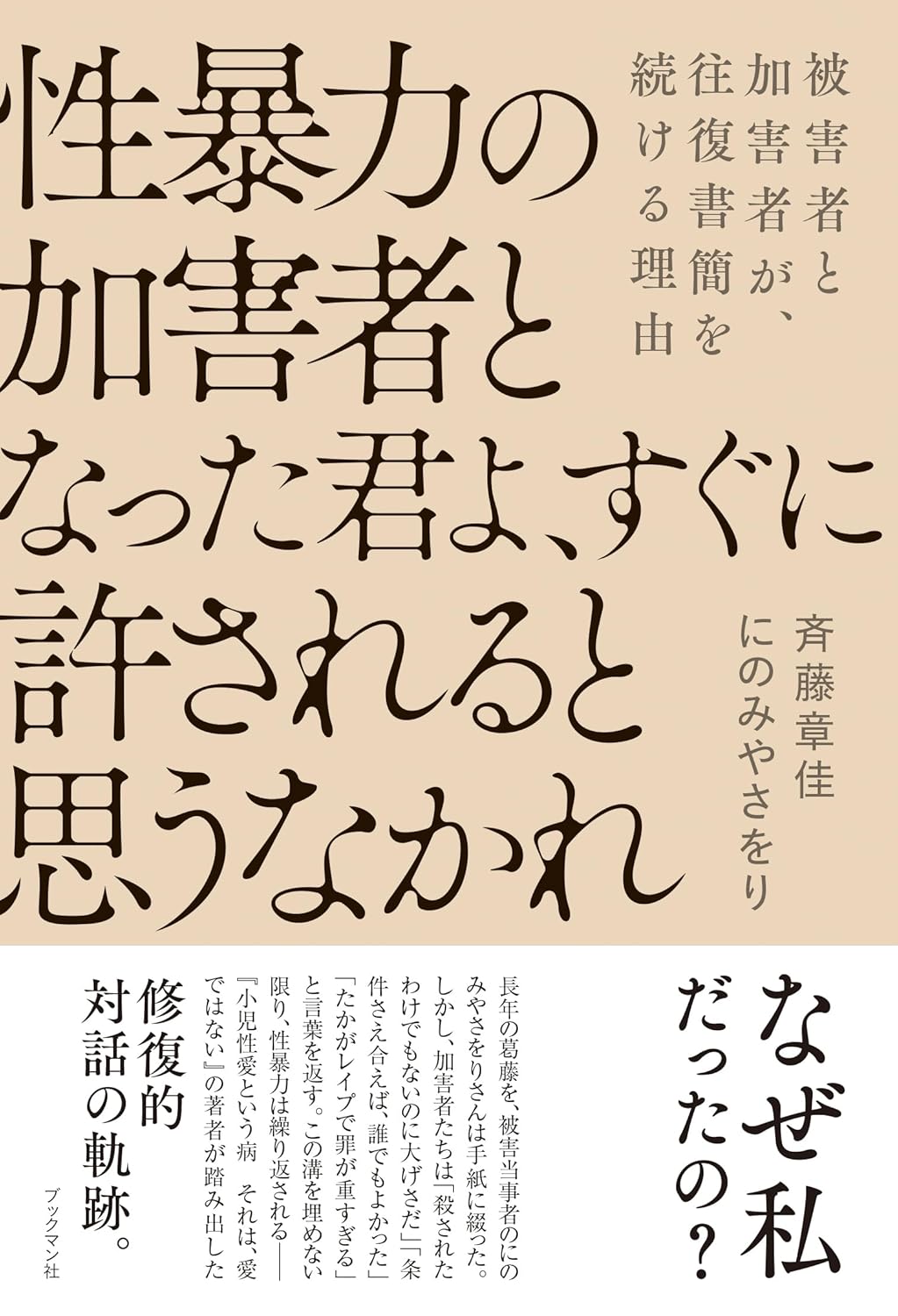
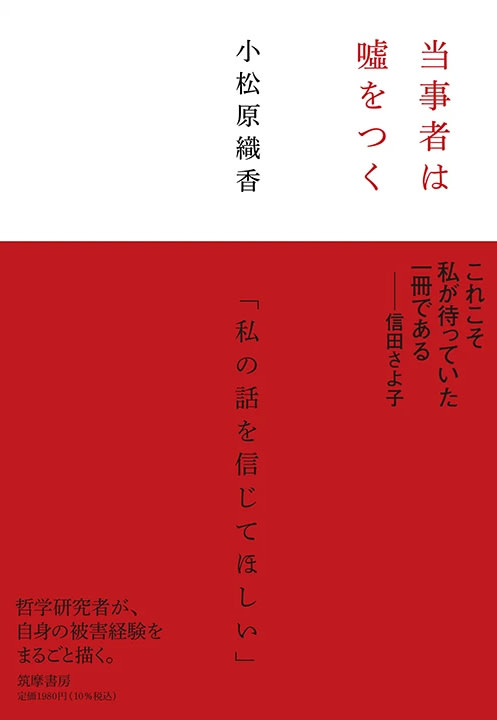
――そうだね。どちらも性暴力被害者による書籍だ。『性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ』では、性暴力被害者のにのみやさをりさんが、別の性暴力事件で加害者になった人たちと書簡をやり取りして、「加害者は被害者を知らず、被害者は加害者を知らない」状況を変容させようとする実践の話だった。『当事者は嘘をつく』も壮絶で、センセーショナルなタイトルだけど、まさに性暴力の被害者の経験は忘却しがたいのと同時に記憶しがたく、語りがたいものである、ということを示していたよね。
Q:そういえばどちらも「修復的司法」に意識が向いた本だ。
――まさに小松原さんの専門がそれだね。修復的司法の概念もすごく私は関心を持っている。修復的司法って、国家による罰ではなく、加害者と被害者が地域の中で対話を重ねて、再発を阻止しながら被害者のケアと加害者の孤立を防ぐ、っていう考え方なんだよね。すでにニュージーランドとか複数の地域で取り入れられているけど、現時点だと基本的には「服役を終えたあと」においてそれが実践される、って感じ。
Q:被害者の状況が本当に勘案されているのか?っていうのは、確かに現状の司法においてはかなり疑問だね。同時に報復を防ぐために法があるとも言えるわけだが。
――まあ、法律が持っている役目って一つではないし、私が批判しているのもすべての側面を網羅した話ではないよ。それにアナキストは無政府主義だけど無秩序主義じゃない。ルールを否定しているんじゃなくて、権力と一体化した司法のあり方に疑問を持っている。
Q:そこ誤解されがちだよね。全否定してるわけじゃないのに、「じゃあ法律全部なくせって言うのか」みたいな反論はよく受けるね。
――回りくどい言い方だけど、法律を守ることそのものが人間の生においてベストな選択であるわけではないでしょ、と思ってはいるから、反論したい人からすれば十分反社会的なのかもしれないけど。でも、社会って秩序を常に見直しながら変わっていくものだから、やっぱ既存の法律を守るだけで「よりよい未来」にアクセスできるとは、私は思わないんだよなあ。
Q:そのへんはどうにも両義的な態度しか取れないよね。ことはそう単純じゃないからこそ、長く考えていかないといけないし、ゆっくり変えていくしかないんだろうなあ。
――結論としてはそんなところだね。次回もぐだぐだ悩みながら、雑多に本に手を伸ばすことにするよ。