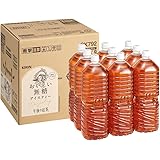2025年7月30日、気温の歴史が動いた。兵庫県丹波市・柏原で最高気温41.2℃を観測し、これまで埼玉県・熊谷と静岡県・浜松が持っていた歴代1位の記録である41.1℃を超えた。また、7月の日本の月平均気温の偏差は+2.89℃と統計開始以来最高となった。8月はさらなる高温により、この記録を打ち破る可能性はあるのか。長期予報を基に解説する。
31年ぶりに近畿地方で40℃超
7月30日は西日本で記録的な酷暑となった。兵庫県・柏原と西脇、京都府・福知山、岡山県・久世の4地点で40℃以上を観測し、兵庫県・柏原の41.2℃は国内の観測史上最高気温の記録を塗り替えた。西日本で40℃以上の高温になるのは珍しく、近畿地方では1994年8月8日に和歌山県・かつらぎで40.6℃を観測して以来、31年ぶり。中国地方では観測史上初めてのことだ。また、翌日31日も岡山県・高梁で40.4℃と、前日の岡山県史上最高気温を超える酷暑となった。

(画像)7月30日の最高気温 提供:ウェザーマップ
最も暑い7月になった
7月は記録的な高温となった。日本の7月の月平均気温の平年との差は+2.89℃で、1898年の統計開始以来最も高かった。地域ごとに見ると、北日本が+4.5℃、東日本が+2.7℃、西日本が+2.2℃と北ほど高温が顕著だった。太平洋高気圧の張り出しが平年より強く、梅雨前線の影響を受けにくかったために、常に真夏の空気に覆われたことが要因だ。ちなみに極端な少雨でもあり、東日本日本海側では月降水量平年比はわずか8%だった。

西日本よりも東日本の方が40℃にいきやすい?
過去の日本の歴代最高気温の順位を見ると、今回の西日本の観測を除けば、東海地方や関東甲信地方、北陸地方など東日本に集中している。なんとなく西に行くほど緯度が低くなり暑さが厳しくなるように感じるかもしれないが、地形が大きな鍵となっている。
40℃以上を観測するような顕著な高温が発生する時は、基本的にはフェーン現象が絡んでくる。フェーン現象とは、山の上から高温の風が吹き下りてくるものであり、山が高いほどその効果は大きくなる。東日本は日本最大の山岳地帯・日本アルプスを有しており、強いフェーンが働きやすい。西日本にも中国山地など高い山は存在するが、日本アルプスが3000メートル級の山を有しているのに対し、中国山地はせいぜい高くても1500メートル程度。この地形的要因が、西日本の高温の上限を決めていたのだ。

歴代最高気温が出た要因
今回の記録的高温は、複数の要因が絡み合った結果だ。まず大きな視点から見ると、上空の非常に高い所を流れる亜熱帯ジェット気流が、日本付近で北に蛇行していた。この偏西風の北偏により、気象環境場も北にシフトし、沖縄付近が熱帯、本州付近が亜熱帯のような気圧配置になった。このため、そもそも本州付近は気温が高かったのだ。
加えて、非常に背の高い高気圧に覆われたことも一因だ。時々天気予報で「ダブル高気圧」という言葉を耳にすると思うが、それと似たような気圧配置となっていた。まず、偏西風の北への蛇行はチベット高気圧の日本付近への張り出しの強まりに寄与する。さらに日本上空を亜熱帯高気圧が覆っていた。この時、台風8号が中国東岸に接近中で、台風周辺の上昇気流が日本付近に下降気流を作り出し、より亜熱帯高気圧が強められていた。この結果、非常に背の高い高気圧が形成され、日本付近の大気下層では空気が圧縮される「断熱圧縮」が発生し、強い暖気が形成された。

また、背の高い高気圧の位置も重要だ。大気下層の高気圧の位置は日本海で、西日本には北東か東の風が吹いていた。本来、太平洋高気圧はその名の通り日本の東の太平洋に中心を持つ。その環境なら、西日本には南か南東の風が吹くことが多いが、今回は北〜東系の風が入ったため、陸を渡る風の影響を受けやすかった。強いフェーンが効く状況ではなかったが、山越え気流となって高温の空気が入り込みやすい環境が日中続き、気温が上がりやすかったものと思われる。このようにさまざまな要因が重なり、今回の異常高温に繋がった。

8月の前半はかなり危険
気象庁は7月31日に1ヶ月予報を発表した。北〜西日本では平年よりも気温は高い予想だ。太平洋高気圧の西への張り出しが強く、日本の北は低気圧や前線が通過しやすい。このような気圧配置を「南高北低型」という。気圧の高い所から低い所に向かって風が吹くため、南高北低であれば南から暖気が流れ込みやすく、気温が高くなりやすい環境となる。特に8月前半はその傾向が強く、かなりの高温となる所もありそうだ。

(画像)7月31日発表1ヶ月予報 提供:ウェザーマップ
今回40℃を観測したのは西日本だったが、この8月はどうなるか。次は東日本で40℃台頻発の可能性が高い。理由は、これも高気圧の位置だ。8月は、これまで対流活動が活発だったフィリピンの東や日本の南の辺りで活動が不活発になり、この付近で高気圧が強まる。そうすると日本上空は北西の風が吹くことが増えてくる。北西の風は日本アルプスの影響で東海地方や関東甲信地方でフェーン現象を引き起こし、顕著な高温となることが多くなる。
一年で最も気温が高い時期に、他の高温因子が重なれば、40℃台の観測は難しくないだろう。北日本付近の前線が南下するタイミングであれば、上空の北西風はさらに強まり、フェーンが効きやすくなる。41.2℃を超えて、さらなる日本記録更新の可能性もあると考える。

40℃が当たり前の時代に
気象庁の地球温暖化の将来予測では、20世紀末と比べて21世紀末には日本の夏の平均気温が4℃前後上昇すると説明されている。過去最も暑い夏だった2024年夏の平均気温の平年との差は+1.76℃だったため、4℃上昇というのは、今とは大きく状況が異なることが容易に想像できる。
おそらくその前には、30℃以上は真夏日、35℃以上は猛暑日といったように、40℃以上にも名称が付けられているだろう。

ちなみに、気温というのは徐々に右肩上がりというよりも、段階的に上がっているように見ることもできる。日本の平均気温の平年差のグラフを見ると、全体としては右肩上がりになっているが、20年スパンで見ると階段状になっているように見える。これは「気候ジャンプ」といい、ある閾値を超えたときに次の気候ステージに移行する現象である。
この数年はまさにそのジャンプが見られ、次の高温ステージに入ったとみられる。40℃台を観測した地点であっても、もはや異常気象とは言えないような段階に入ってきたと考えるのが自然だ。暑さも災害であるという認識を、より一層強めていく必要がある。

(画像)日本の年平均気温偏差 出典:気象庁 一部筆者が加工